分離課税の確定申告とは?申告時の書き方や総合課税との違いを解説!
確定申告
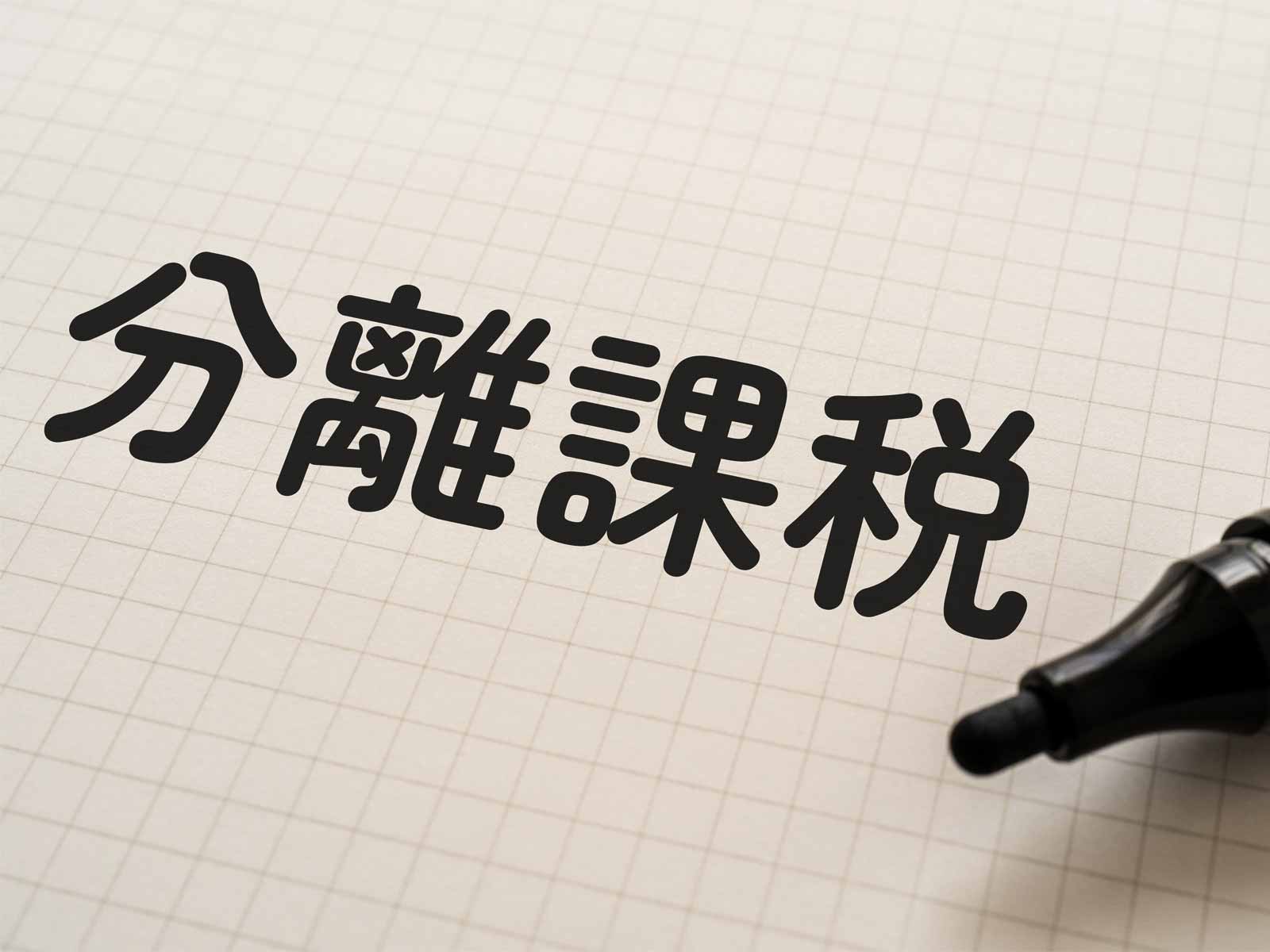
Contents
確定申告を行う際、所得税の計算方法として「総合課税」と「分離課税」の2種類があることをご存じでしょうか。総合課税は、すべての所得を合算して累進課税の対象とする方式ですが、一部の所得はこれと分離して独立した税率で課税される「分離課税」が適用されます。
本記事では、分離課税の仕組みや確定申告の方法について詳しく解説し、総合課税との違いや申告時のポイントを分かりやすく説明します。
そもそも分離課税とは?
分離課税は、特定の所得を他の所得と合算せず、独立した税率で課税する制度です。所得税の計算方法には、総合課税と分離課税の2種類の方式があります。
分離課税と総合課税、申告分離課税と源泉分離課税の違いについて詳しくみていきましょう。
分離課税とは
分離課税は、特定の所得を他の所得と合算せず、独立した税率で課税する制度です。税負担の公平性や、特定の所得に対する税率を一定に保つための措置として設けられています。
たとえば、給与所得と不動産売却益を合算して課税すると、一時的な収入増加によって累進課税の適用税率が上がり、納税者の負担が急激に増える可能性があります。そこで、一定の所得については総所得とは分離し、定められた税率で課税する仕組みが採用されています。
分離課税が適用される代表的な所得には、株式の譲渡益、FXや先物取引による所得、不動産の売却益、退職所得、山林所得などがあります。
分離課税と総合課税の違い
所得税の基本的な考え方としては、すべての所得を合算し、累進税率を適用する総合課税が原則となっています。総合課税では、給与所得、事業所得、配当所得(総合課税を選択した場合)などを合計し、課税対象となる総所得金額を算出したうえで、所得税を計算します。
累進税率が適用されるため、所得が増えるほど税率も高くなります。
一方、分離課税は特定の所得については総合課税に含めず、別途定められた税率で課税する方式です。たとえば、株式の売却益にかかる税率は一律20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)となっており、他の所得とは関係なく独立して計算します。
ただし、一部の所得については、総合課税と分離課税のいずれかを選択できます。たとえば、上場株式の配当所得は総合課税か分離課税かの選択が可能で、総合課税の場合は配当控除によって税負担を軽減できる可能性があります。
申告分離課税と源泉分離課税の違い
申告分離課税とは、特定の所得を他の所得とは分離して税額を計算し、確定申告で納税する方式です。総合課税とは異なり、一定の税率が適用されるため、他の所得と合算して税率が上がることを防ぐメリットがあります。
源泉分離課税は、所得を支払う者があらかじめ税金を源泉徴収し、それだけで納税が完結する方式です。対象となる所得の例は下記のとおりです。
- 一定の預貯金利子や公社債の利子
- 懸賞金付預貯金の懸賞金
- 定期積金の給付補てん金
- 割引債の償還差益
- 一時払養老保険・損害保険の差益(保険期間が5年以下のものなど)
申告分離課税と源泉分離課税の違いは下記のとおりです。
| 比較項目 | 申告分離課税 | 源泉分離課税 |
|---|---|---|
| 納税方法 | 確定申告が必要 | 所得支払時に源泉徴収で完結 |
| 税率 | 所得の種類ごとに異なる | 一律の税率(20.315%など) |
| 他の所得への影響 | 他の所得とは分離して税額計算 | 他の所得と合算されない |
| 対象となる所得 | 株式の譲渡益、土地の売却益など | 預貯金利子、一定の保険金など |
分離課税で確定申告をするべき具体例
分離課税で確定申告が必要な例は下記のとおりです。
| 所得の種類 | 概要 | 所得の計算方法 |
|---|---|---|
| 退職所得 | 退職金などの所得 | (退職金 - 退職所得控除額)÷ 2 |
| 山林所得 | 5年以上育成した山林を売却した際の所得 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円) |
| 譲渡所得(不動産) | 土地や建物を売却して得た所得 | 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除(3,000万円特別控除など) |
| 譲渡所得(株式) | 株式の売却益 | 売却額 - 取得費 - 売買手数料 |
| 利子所得 | 平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等にかかる利子所得 | 収入金額 そのままが所得(源泉徴収されるため申告不要の場合も) |
| 雑所得(先物取引) | 先物取引(FXや商品先物など)による所得 | 決済損益 - 必要経費 |
【第三表】分離課税の確定申告の書き方
分離課税対象の所得を申告する際には、確定申告書の「第三表(分離課税用)」を使用します。この表は、土地や建物の譲渡、株式の売却、退職所得など、他の所得と分離して課税される所得の詳細を記入するためのものです。以下に、第三表の作成手順を解説します。
①所得の種類を選択する
まず、申告する所得の種類を特定し、それに対応する計算明細書を作成します。計算明細書は、第三表に記入する所得金額の内訳を詳細に示す書類であり、正確な申告のために必要不可欠です。
たとえば、FX取引による所得を申告する場合は、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」を作成します。各所得に対応する計算明細書の種類や作成方法については、国税庁の公式サイトで確認できます。
②収入金額、必要経費、特別控除額を記入する
第三表に以下の項目を記入します。
- 収入金額:該当する所得の総収入額を記入します。
- 必要経費:収入を得るために直接かかった経費を記入します。
- 特別控除額:適用される特別控除がある場合、その金額を記入します。
これらの情報は、作成した計算明細書から転記します。たとえば、株式の譲渡所得を申告する場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」から各金額を正確に写します。
③所得金額を計算する
収入金額から必要経費と特別控除額を差し引いて、課税対象となる所得金額を算出します。計算結果は、第三表の「所得金額」欄に記入します。正確な計算のためには、各所得の種類ごとに定められた計算方法や控除額を確認し、適切に適用することが重要です。
④税額を計算する
所得金額が算出できたら、該当する税率を適用して税額を計算します。分離課税の税率は所得の種類によって異なるため、最新の税率を確認し、正確に計算してください。計算した税額は、第三表の「税額」欄に記入します。
分離課税の確定申告に関するよくある質問
分離課税に関するよくある疑問について解説し、適切な判断をするためのポイントを紹介します。
分離課税で確定申告した方がお得?
上場株式の配当所得を申告する際には、「総合課税」と「申告分離課税」のいずれかを選択できます。それぞれの制度には特徴があり、選択によって納税額が変わるため、自身の所得状況に応じて有利な方法を選ぶことが重要です。
総合課税を選択すると、配当所得は他の所得と合算され、累進課税の対象となります。この場合、配当控除を受けることができ、所得税や住民税の一部が軽減されます。ただし、総合課税では所得が多いほど高い税率が適用されるため、合算後の所得が高額になると税負担が増加する可能性があります。
一方、申告分離課税を選択した場合、配当所得は他の所得と分離して一律の税率(所得税15%+住民税5%)で課税されます。配当控除は適用されませんが、上場株式の譲渡損失と損益通算が可能です。つまり、株式の売却で損失が出た場合、その損失を配当所得と相殺することで、全体の税負担を軽減できます。
分離課税は住民税に影響する?
上場株式等の配当所得や譲渡所得を申告する際、総合課税または申告分離課税を選択すると、これらの所得は住民税の総所得金額や合計所得金額に加算されます。
この加算は、住民税の配偶者控除や扶養控除、非課税判定に影響を及ぼす可能性があります。
また、国民健康保険税(料)、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの各種保険料の算定にも関係してきます。
さらに、令和6年度以降、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。そのため、課税方式の選択がこれらの控除や保険料に与える影響を十分に考慮することが重要です。
申告分離課税のデメリットは?
申告分離課税は、特定の所得を他の所得と分離して課税する制度であり、税負担の軽減が期待できる一方、いくつかのデメリットも存在します。まず、他の所得との損益通算が制限される点が挙げられます。
また、申告分離課税の対象となる所得は多岐にわたり、それぞれの所得ごとに計算方法や適用税率が異なります。そのため、確定申告時には各所得に応じた詳細な計算が必要となり、手続きが複雑化する傾向があります。
まとめ
分離課税は、特定の所得に対して適用される独立した課税方式であり、総合課税とは異なる特徴を持っています。適用される所得の種類や計算方法を正しく理解し、適切に申告することで、税負担の最適化が可能です。また、総合課税と分離課税のどちらを選択するかによって、納税額が変わることもあるため、自身の所得状況に応じて慎重に判断することが重要です。
確定申告の時期が近づいたら、自分の所得状況を整理し、最適な課税方式を選択できるよう準備を進めておきましょう。
ABOUT監修者紹介
 税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士。公認会計士。
有限責任監査法人トーマツにて会計監査業務に従事。
23歳時、「日本一若い会計事務所」として”ACLEAN(アクリーン)会計事務所”を開業。スタートアップ、マイクロ法人を中心とした税務業務や補助金・融資等の資金調達支援、経理を対象とした業務改善コンサルティングを展開。
2023年に同事務所を”税理士法人グランサーズ”と統合。同法人の代表に就任。中小企業の税務顧問対応、内部統制構築支援、組織再編支援、事業承継・企業のクラウドサービス活用と経理効率化サービスも提供。また、自身のボディメイクの経験を活かした健康経営に関するコンサルティングも得意としている。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」絶賛配信中!
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
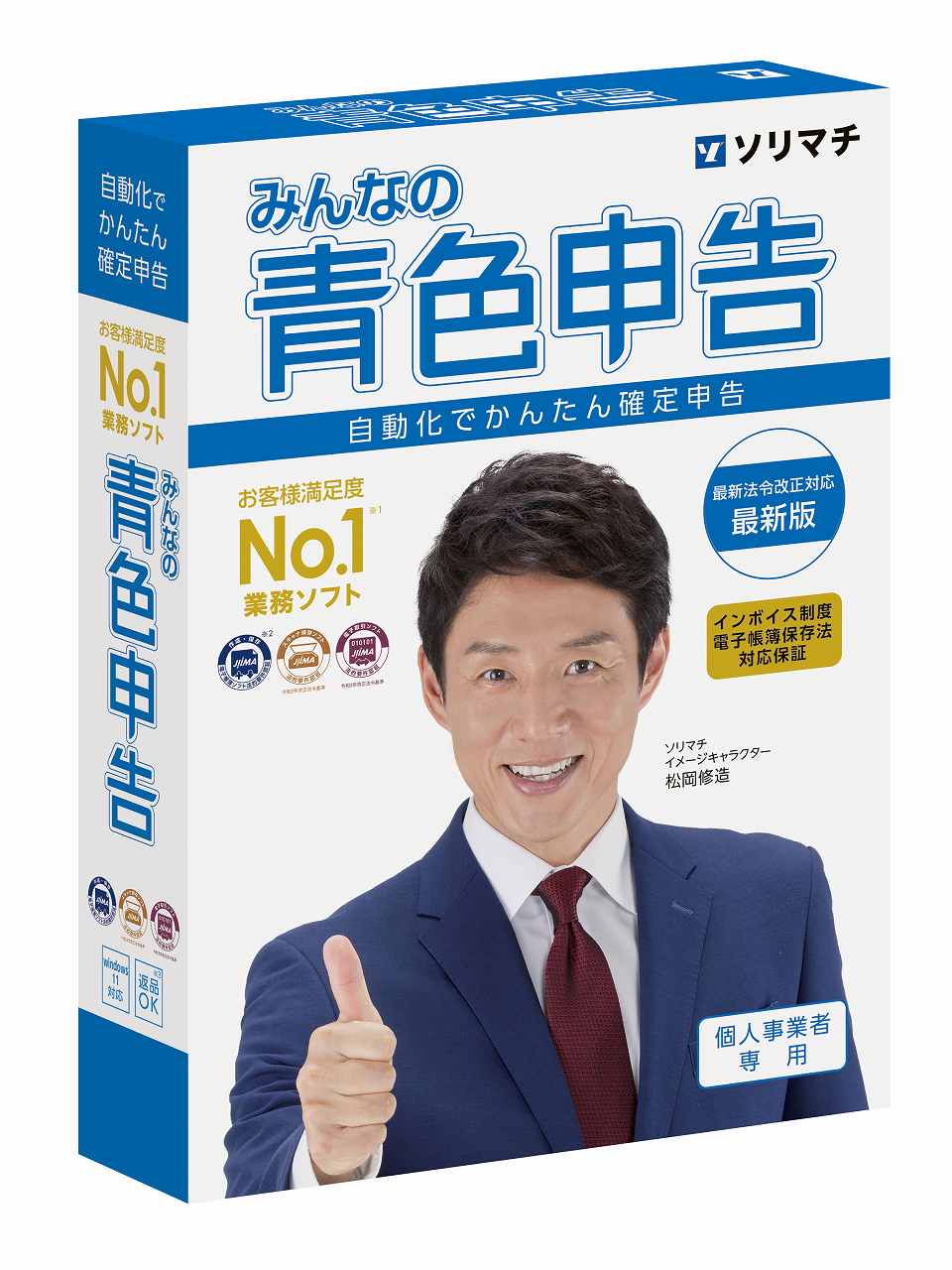 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。








