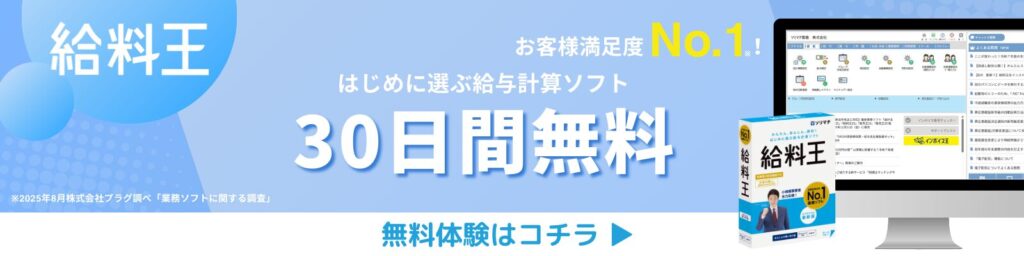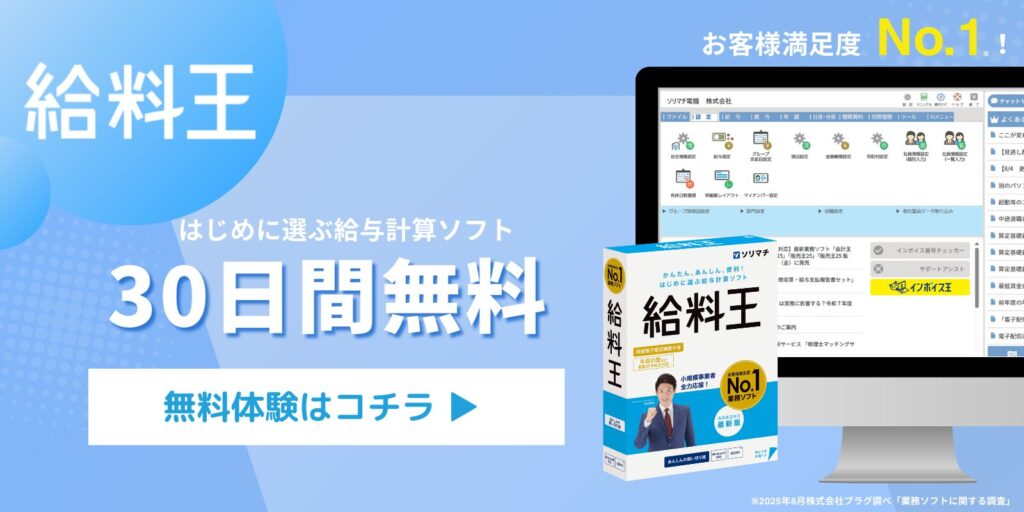「NISAなどの金融所得があると社会保険料が増やされる」って本当?
社会保険ワンポイントコラム

社会保険料負担の増加に関わる制度の見直しが検討されているという。対象は「金融所得」がある人の社会保険料。一体、どのような趣旨で見直しが計画されているのだろうか。開始時期はいつからか。今回はこの点を整理してみよう。
不公平な社会保険料計算
現在、金融所得の社会保険料への反映の仕組みが見直されようとしている。理由は金融商品から得られた所得のうち上場株式の配当など、確定申告するかどうかを本人が選択できる所得は、当該所得額が社会保険料の算定基礎に含まれるケースと含まれないケースとがあるためである。
投資商品の取引に際して金融機関で「源泉徴収ありの特定口座」を利用すると、確定申告は不要になる。この場合、得られた金融所得が社会保険料の算定基礎に含まれることはない。一方、「源泉徴収なしの特定口座」を利用した場合には確定申告が必要であり、申告をすれば金融所得が一部の社会保険料の算定基礎に含まれる。
その結果、同様の金融所得を得ていても、「確定申告をした人のほうが、社会保険料負担が重くなる」という現象が生じがちである。そこで、金融所得の社会保険料への反映の仕組みについて、公平性の観点からの見直しが検討されることになったものだ。
対象は国民健康保険、後期高齢者医療制度、介護保険の保険料
なお、全ての社会保険制度の保険料が対象になるわけではない。公的な医療保険制度のうち、保険料額が前年の所得状況に応じて決定される以下の制度が対象である。
- 自営業者などが加入する「国民健康保険」
- 75歳以上の人が加入する「後期高齢者医療制度」
- 「介護保険」のうち上記2制度の加入者が入るケース
公的医療保険制度の中でも民間企業の勤務者が加入する「健康保険」や公務員が加入する「共済組合」は、所属組織から支払われる給与等のみが保険料の算定基礎となる。そのため、確定申告の有無によって保険料額が変わることはない。民間企業勤務者や公務員が「介護保険」に加入する場合も同様である。従って、これらの制度は今般の見直しの検討対象とはなっていないようだ。
実施について2028年度までに検討
金融所得に関わる制度見直しの検討は、政府が昨年12月22日に決定した『全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)について』の中で、「2028年度までに実施について検討する取組」の1項目として掲げられたものである。具体的には、医療・介護保険における金融所得の勘案として、以下のとおり示されている。
国民健康保険制度、後期高齢者医療制度及び介護保険制度における負担への金融所得の反映の在り方について、税制における確定申告の有無による保険料負担の不公平な取扱いを是正するため、どのように金融所得の情報を把握するかなどの課題も踏まえつつ、検討を行う。
今回の検討の目的は「確定申告の有無による不公平性の是正」にある。従って、非課税であるために確定申告の影響を受けないNISA(少額投資非課税制度)については、現時点では社会保険料への反映の対象外とする方向で議論が進んでいるようだ。つまり、「金融所得がNISAによる所得の場合には、社会保険料負担は増加しない」となる可能性が高いといえよう。
制度の見直しが「新たな問題」を見える化する?
仮に、制度見直しの内容が「金融所得を確定申告しない場合であっても、当該所得額を国民健康保険・後期高齢者医療制度・介護保険の保険料の算定基礎とする」という仕組みであったとする。この場合には、「確定申告の有無による不公平性の是正」は実現できるであろう。
ところが、別の問題が明確化することになる。「自営業者と給与所得者との間の不公平性」という問題だ。前述のとおり、民間企業勤務者や公務員が加入する公的医療保険制度では、上場株式の配当などの金融所得が保険料算定に全く反映されないからである。
この点も踏まえ、果たして2028年度までにどのような制度見直しが検討・決定されるのか、今後の動向が見逃せないといえよう。
【参 考】
内閣官房ホームページ:「全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)」について(PDF)
自由民主党ホームページ:社会保険料等に金融所得の適切な反映を ~確定申告の有無による保険料の算定等の不公平の解消に向け議論実施~
ABOUT執筆者紹介
コンサルティングハウス プライオ 代表 中小企業の経営支援団体にて各種マネジメント業務に従事した後、組織運営及び人的資源管理のコンサルティングを行う中小企業診断士・社会保険労務士事務所「コンサルティングハウス プライオ」を設立。『気持ちよく働ける活性化された組織づくり』(Create the Activated Organization)に貢献することを事業理念とし、組織人事コンサルタントとして大手企業から小規模企業までさまざまな企業・組織の「ヒトにかかわる経営課題解決」に取り組んでいる。一般社団法人東京都中小企業診断士協会及び千葉県社会保険労務士会会員。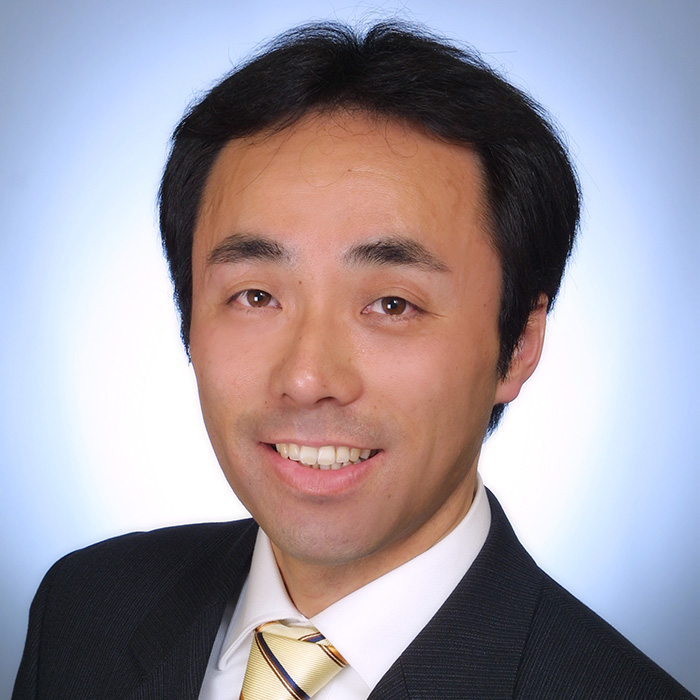 大須賀信敬
大須賀信敬
(組織人事コンサルタント/中小企業診断士・特定社会保険労務士)