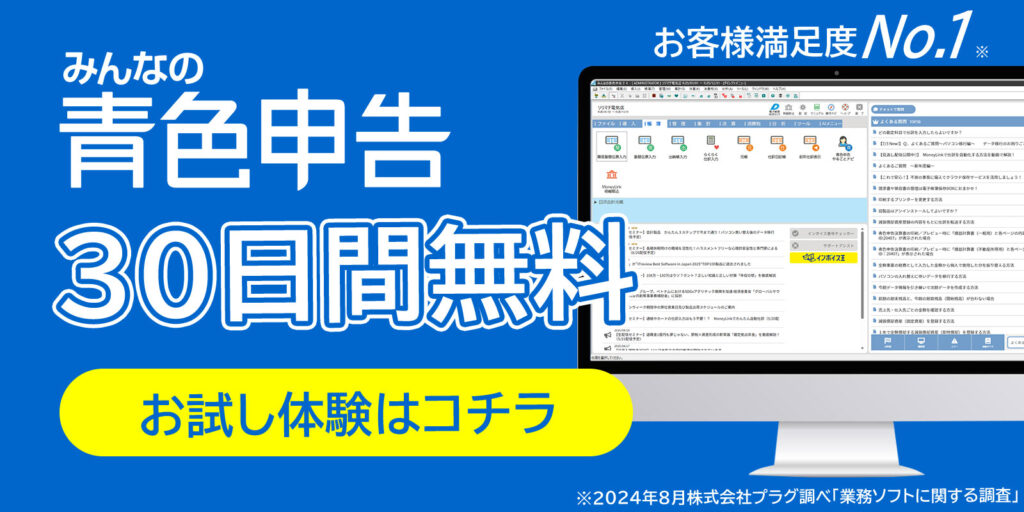確定申告がめんどくさいと感じる理由は?簡単にするために試したい方法も解説!
確定申告

Contents
確定申告は、個人事業主や副業をしている人にとって避けて通れない手続きですが、多くの人が「めんどくさい」と感じています。実際にやってみると、書類の準備や計算の手間がかかるだけでなく、税制の変更や専門用語の多さに戸惑うこともあるでしょう。
本記事では、確定申告が面倒に感じる理由と、少しでも楽に行う方法について解説します。
確定申告がめんどくさいと感じる6つの理由
確定申告がめんどくさいと感じる理由は、次の6つです。
- 簿記の知識が無く何からやれば良いか分からない
- 専門用語が多すぎる
- 税制が頻繁に変わる
- 必要書類をまとめるのが大変
- 記入ミスしたときの修正が大変
- 誰に質問すれば良いが分からない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①簿記の知識が無く何からやれば良いか分からない
確定申告では、収入や経費を計算する必要がありますが、簿記の知識がないと「売上」「仕入」「控除」などの区別が分からず、どこから手をつければいいのか悩むことが多いでしょう。
たとえば、フリーランスで仕事をしている人が、銀行口座に振り込まれた金額をそのまま売上に計上してしまったり、実際には経費として計上すべき支払いを見落としたりすることもあります。
②専門用語が多すぎる
「青色申告」「白色申告」「控除」「課税所得」など、確定申告では普段聞き慣れない専門用語が多く出てきます。特に初めて申告をする人にとっては、用語の意味を調べるだけでも手間に感じることがあります。
たとえば、「青色申告承認申請書を提出していないと、青色申告の65万円控除が受けられない」といったルールの確認が必要です。
③税制が頻繁に変わる
税制は頻繁に改正されるため、昨年と同じように申告しようとしてもルールが変わっていることがあります。たとえば、電子帳簿保存法の改正により、領収書の管理方法や要件が変わりました。また、例外事項などもあり、それらをすべて把握することは困難です。
また、特定の業種に適用される税制優遇措置が変わることもあり、知らずに処理すると、後から修正が必要になる場合もあります。
④必要書類をまとめるのが大変
確定申告の際、必要書類の整理は多くの人にとって大きな負担となります。たとえば、売上を証明する請求書や経費の領収書、給与所得者であれば源泉徴収票など、多岐にわたる書類を年度末に一度にまとめようとすると、紛失が発覚することも少なくありません。
また、オンラインで受け取った請求書と紙の領収書が混在している場合、保管場所や形式が異なるため、管理が煩雑になりがちです。
⑤記入ミスしたときの修正が大変
確定申告書に記入ミスがあると、修正申告や更正の請求をしなければなりません。特に、税額の計算ミスや経費の誤申告は、延滞税や加算税が発生します。
たとえば、交際費として計上した支出が実際には私的な出費と見なされると、後から税務署から指摘され、修正することになりかねません。また、所得の申告漏れがあった場合、追徴課税につながります。不要な税金の支払いを避けるためにも、記入ミスを防ぐことが大切です。
⑥誰に質問すれば良いかが分からない
確定申告に関する疑問があっても、誰に相談すればよいか分からないと手続きが滞ります。税務署で無料相談を受けることはできますが、申告時期になると混雑し、すぐに対応してもらえないこともあります。
また、税理士に相談するという方法もありますが、費用が発生するうえに、どこまで依頼すべきか判断が難しいでしょう。
市区町村の役場や商工会議所などでも相談窓口を設けていますが、これらの情報が十分に周知されておらず、どこに相談すればよいのか分からない人は少なくありません。このように、確定申告に関する疑問を解消するための適切な相談先が見つからないことが、手続きの遅れやストレスの原因となっています。
そもそも確定申告をやらなければいけない理由
確定申告は、日本の税制において重要な手続きであり、適切に行うことで税務上のトラブルを避けることができます。確定申告が必要な理由や申告が必要な人・不要な人について詳しく解説します。
確定申告は所得税などの税額を決める手続き
確定申告は、1年間の所得をもとに税額を計算し、納めるべき税金を確定させるための手続きです。会社員の場合は年末調整を行うため、確定申告を行わずとも税額が確定します。しかし、個人事業主や副業をしている人、会社員でも医療費控除や寄附金控除を受けたい方などは、確定申告をしなければなりません。
確定申告が必要な人
確定申告が必要な人の例は下記のとおりです。
- 個人事業主やフリーランス(所得48万円を超える)
- 副業で年間20万円超えの所得がある会社員
- 同族会社の役員やその親族で、会社から給与以外に貸付金の利子や賃貸料などを受け取っている人
- 給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 不動産所得がある人
- 株式や仮想通貨で利益を得た人
他にも確定申告が必要なケースがあります。詳しくは国税庁のWebサイトで確認しましょう。
確定申告が不要な人
一方で、以下のような人は確定申告が不要です。
- 会社員で年末調整が済んでいる人(医療費控除やふるさと納税による寄附金控除などが不要)
- 副業の所得が年間20万円以下の人(住民税の申告は必要)
- 公的年金のみで収入が一定額以下の人
- 所得が48万円以下の個人事業主やフリーランス(48万円の基礎控除があるため)
確定申告をやらないとどうなる?
確定申告は、多くの人にとって煩雑で手間のかかる作業と感じられます。しかし、適切な対策を講じることで、その負担を軽減することが可能です。
以下に、確定申告を行わない場合の影響と、申告を簡単にするための方法について具体的に解説します。
追加で税金を納めなければならない
確定申告を期限内に行わない場合、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
無申告加算税は、申告期限を過ぎてから申告した際に課されるもので、税務署からの調査通知前に自主的に申告した場合、納付すべき税額に対して5%が加算されます。
一方、調査通知後に申告した場合は、納付すべき税額のうち50万円までは10%、50万円を超える部分には15%の無申告加算税が適用されます。さらに、2024年1月1日以降に法定申告期限が到来する国税は、納付すべき税額が300万円を超える部分に25%の無申告加算税が課されます。
延滞税は、納付すべき税金を期限内に納めなかった場合に発生し、延滞期間に応じて加算されます。具体的な税率は、納期限の翌日から2ヶ月間は年7.3%と「特例基準割合+1%」のいずれか低い方が適用され、2ヶ月以降は年14.6%と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い方が適用されます。
納税証明書が発行されない
確定申告を行わないと、納税額や所得金額が記載された納税証明書が発行されません。納税証明書は、ローンの申請や各種手続きで必要となる書類です。たとえば、住宅ローンを組む際には、過去の納税状況を証明するために納税証明書の提出が求められることがあります。
申告を怠ると、これらの手続きがスムーズに進まなくなるでしょう。
住民税も未納付になる
確定申告を行わないと、所得税だけでなく住民税の未納にもつながります。住民税は、確定申告で報告された収入や経費などの情報を基に各自治体が課税額を算定します。そのため、確定申告を怠ると自治体が正確な所得を把握できず、住民税の納付通知が届かない、あるいは適切な課税が行われない可能性があります。
確定申告を行わない場合は、住民税申告を行います。
確定申告がめんどくさい人が試したい 簡単にする方法
確定申告は、個人事業主や副業で20万円超えの所得がある会社員などにとって、毎年避けて通れない手続きです。しかし、その煩雑さや手間から、つい後回しにしてしまう方も少なくありません。適切な方法やツールを活用することで、確定申告の負担を大幅に軽減することが可能です。
確定申告がめんどくさい人におすすめな効率化・簡便化の方法を紹介します。
会計ソフトを活用する
会計ソフトを利用することで、日々の取引の記録や申告書類の作成が自動化され、作業効率が大幅に向上します。たとえば、銀行口座やクレジットカードと連携できるソフトを使用すれば、取引データが自動的に取り込まれ、入力の手間が省けるだけでなく、記入ミスや漏れを防ぐことができます。
売上や経費を手作業で入力する場合、誤った金額を記録してしまう可能性がありますが、会計ソフトを導入すれば、リアルタイムで正確なデータを管理できるため、確定申告の際に慌てることがありません。
さらに、レシートや領収書をスマートフォンで撮影してデータ化できる機能を備えたソフトもあり、紙の書類を管理する手間が削減されます。
また、手作業では消費税の税率の改正があるたびに対応が必要ですが、会計ソフトを利用すれば、最新の税率に自動でアップデートされ、控除や税額計算のミスを防ぐことができます。
作成した申告書をそのままオンラインで提出できる会計ソフトを選べば、申告の手間をさらに効率化できます。
領収書をこまめに整理しておく
日々の経費に関する領収書やレシートは、後でまとめて整理するのではなく、日々のうちに整理・保管する習慣をつけましょう。たとえば、月ごとや取引先ごとにファイルや封筒に分けて保管することで、後から必要な書類をすぐに見つけることができます。
また、スマートフォンのアプリを活用して、領収書を撮影・デジタル保存する方法も効果的です。さらに、会計ソフトと連携する機能を持つアプリを活用すれば、確定申告の際に経費を自動集計し、スムーズに申告書を作成できます。
税務署に相談する
税務署では、無料で確定申告に関する相談を受け付けています。特に申告時期(通常2月16日から3月15日)は混雑が予想されるため、各自治体のホームページで相談日時や予約方法を確認しましょう。
確定申告会場への入場には、入場できる時間枠を区切った入場整理券が必要です。入場整理券は相談会場で当日配付されますが、LINEを通じたオンライン事前発行もされています。
個別の節税対策や専門的な税務相談については対応範囲が限られているため、詳細なアドバイスを求める場合は税理士への相談が必要です。
税理士に依頼する
確定申告の手続きを専門家である税理士に依頼することで、自身の負担を大幅に軽減できます。税理士は最新の税法に精通しており、適切な節税対策や申告書の作成を代行してくれます。
ただし、依頼には費用が発生するため、事前に料金を確認し、予算と相談して検討することが重要です。たとえば、個人事業主の場合、年間の売上や取引の複雑さによって報酬が変動することがあります。
確定申告に関するよくある質問
確定申告に関して、多くの方が疑問を抱くポイントがあります。確定申告に関するよくある質問とその回答を以下にまとめました。
赤字は確定申告しなくても良い?
青色申告においては、事業所得が赤字の場合でも、確定申告を行うことで翌年以降の黒字と相殺できる「純損失の繰越控除」を受けることが可能です。たとえば、今年100万円の赤字が出た場合、翌年に100万円の黒字が出た際に相殺され、課税対象額を減らすことができます。したがって、赤字であっても確定申告を行うことが大切です。
確定申告を20万円以下でしないとどうなる?
給与所得者が副業で年間20万円以下の所得を得た場合、所得税の確定申告は不要とされています。しかし、住民税については別途申告が必要です。
住民税を申告しない場合、無申告加算金や延滞金などのペナルティが課されるリスクがあるため、副業の所得が20万円以下であっても、住民税の申告を忘れずに行うことが重要です。
無申告はなぜバレる?
確定申告を行わない「無申告」の状態は、さまざまな経路で税務当局に発覚する可能性があります。主な理由として、取引先が税務署に提出する「支払調書」があります。
支払調書は企業や個人事業主が誰にいくら支払ったかを報告する書類で、税務署はこれを基に各個人の所得を把握しています。そのため、受け取った報酬を申告しないと、支払調書との照合で無申告が明らかになります。
また、税務署は必要に応じて個人の銀行口座の動きを調査する権限を持っています。口座への定期的な入金や大口の取引が確認されると、申告内容との不一致が疑われ、無申告が発覚するリスクが高まります。
さらに、周囲の人々からの通報が税務調査のきっかけとなるケースもあるようです。
このように、無申告は多方面から明るみに出る可能性が高いため、適切に確定申告を行うことが重要です。
実際、国税庁の「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」によれば、実地調査による申告漏れ所得金額は5,516億円、簡易な接触による申告漏れ所得金額は4,448億円と報告されています。
ペナルティを課せられて本来よりも高い税金を支払うことにならないためにも、確定申告は行うことが大切です。
まとめ
確定申告は、個人事業主や副業を行う方にとって避けて通れない手続きです。しかし、その複雑さや手間から「めんどくさい」と感じる方も多いでしょう。
会計ソフトの活用や領収書の整理、税務署や税理士への相談など、適切な対策を講じることで、確定申告の手続きをスムーズに進めることが可能です。今回、解説した内容を参考に、確定申告の負担を軽減しましょう。
ABOUT監修者紹介

税理士 北川知明
1998年横浜市立大学商学部経営学科卒業。2003年税理士登録。2014年に会計事務所を退職、北川税理士事務所開設。スタートアップから上場後のさらなる発展段階のステージまで、企業の成長とともに各ステージのニーズに応じたサービス提供に定評がある。
北川税理士事務所
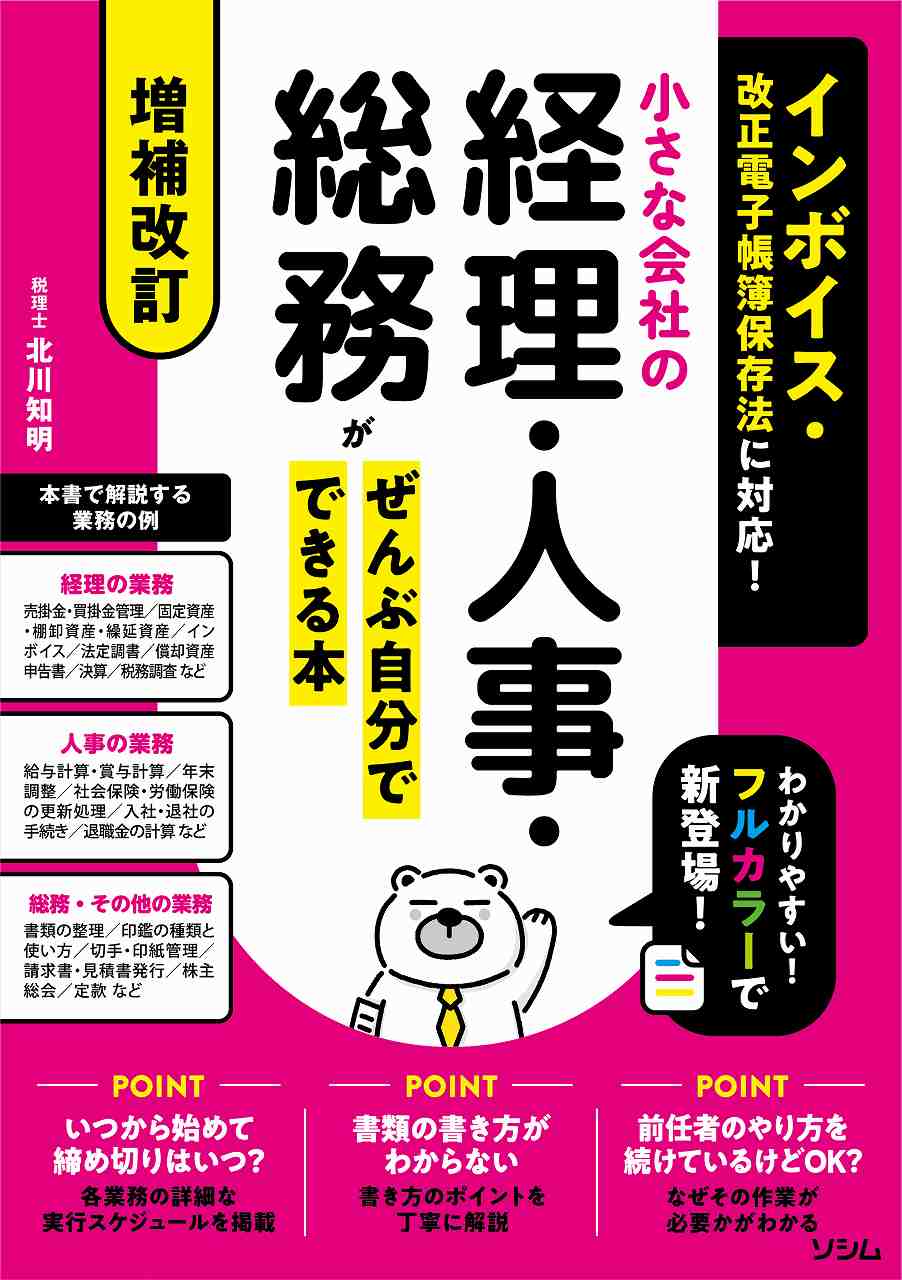
「【増補改訂】小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本」 |
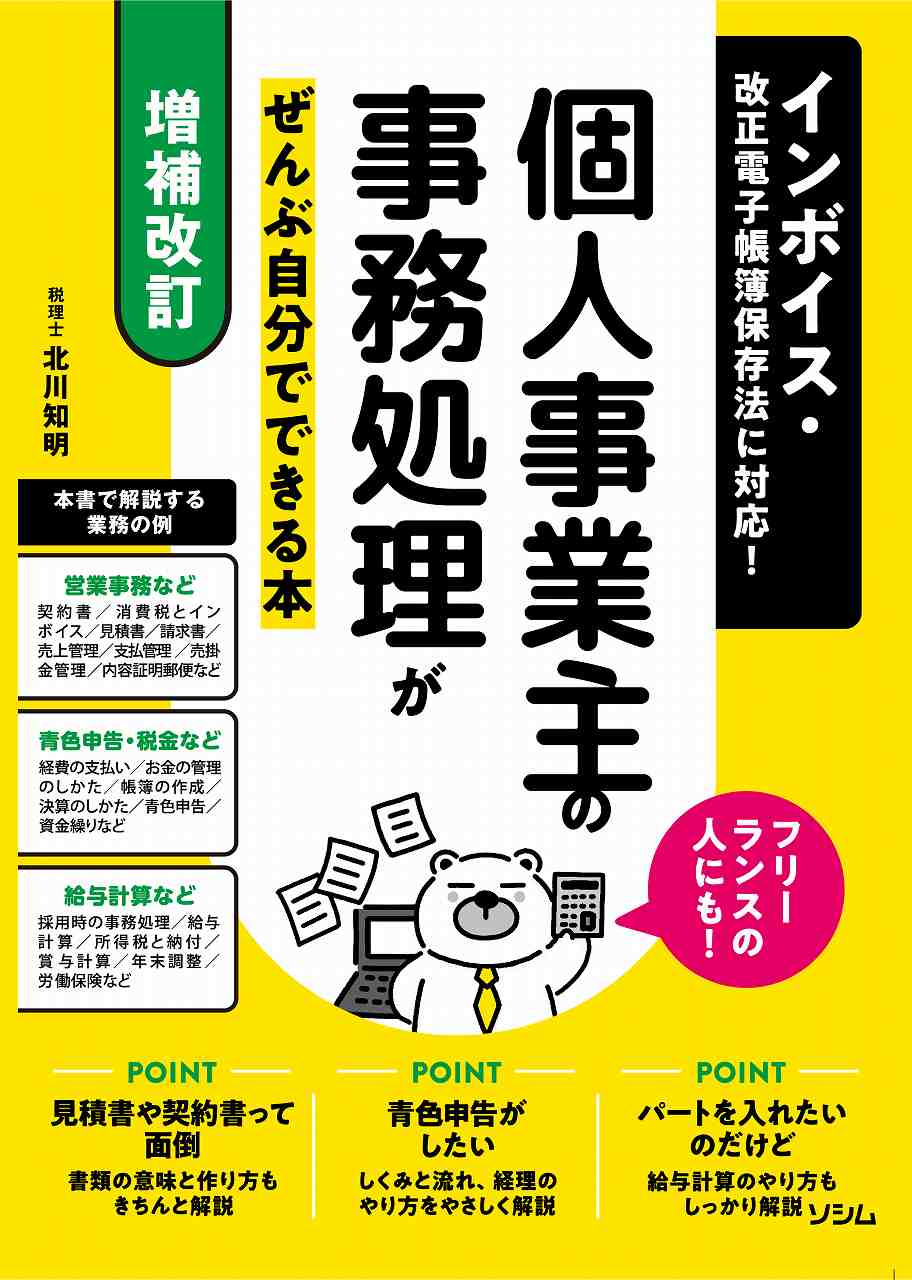
「【増補改訂】フリーランスの人にも!個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」 |
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、