個人事業主・自営業のための確定申告完全ガイド|やり方や必要書類を解説
確定申告

Contents
個人事業主やフリーランス、自営業として働く方の多くが毎年頭を悩ませるのが確定申告です。税務署からの案内も複雑で、書類の準備や提出方法、控除の取り扱いなど、初めての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
しかし、正しい手順を知り、早めに準備を始めれば、確定申告はそれほど難しいものではありません。
本記事では、個人事業主や自営業者の方に向けて、確定申告の基本から実際の手続き、青色申告・白色申告の違い、必要書類やよくある質問まで解説します。
確定申告とは?個人事業主や自営業者には必要?
確定申告は、個人が1年間(1月1日から12月31日まで)に得た所得の金額と、それに対する所得税などを自ら計算して確定させる手続きです。
個人事業主、自営業者は商品の仕入れや原材料費などの売上原価、または売上に直接かかわる支出のほか、通信費や水道光熱費、消耗品費など、事業を継続する上で発生した費用を必要経費として売上から差し引くことができます。
個人事業主が確定申告すべきケース
個人事業主やフリーランスとして所得を得ている場合、課税される所得が基礎控除額を超えると確定申告が必要になります。これは開業初年度であっても同様で、事業から利益が出ていれば申告が義務付けられます。
基礎控除とは、確定申告において所得税額の計算をする際に、総所得金額などから差し引くことができる控除です。合計所得金額に応じて控除額が異なり、以下のように定められています。
- 合計所得金額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
- 132万円超~336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 336万円超~489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 489万円超~655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
- 655万円超~2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)
個人事業主が確定申告しなくてよいケース
個人事業主であっても、所得の状況によっては確定申告が不要となる場合があります。たとえば、所得税額が発生しないときなどが該当します。
まず、各種の所得(譲渡所得や山林所得を含む)の合計額から、基礎控除や配偶者控除、社会保険料控除などの所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。次に、その課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を計算します。
さらに、この所得税額から配当控除額を差し引いた結果、税額がゼロとなる場合には、確定申告の義務はないとされています。
青色申告と白色申告の違い
「青色申告」と「白色申告」は、帳簿の記載方法や受けられる控除、手続きの手間などに違いがあります。以下の表では、それぞれの違いを項目ごとにわかりやすく整理しました。
| 比較項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 不動産所得・事業所得・山林所得がある個人 | 同左 |
| 届出の要否 | 必要(原則として、青色申告しようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出) | 不要 |
| 記帳方法 | 原則:複式簿記 単式簿記でも可 |
簡易な単式簿記(合計記帳など可) |
| 帳簿保存期間 | 7年(書類によっては5年) | 法定帳簿:7年 その他の帳簿・書類:5年 |
| 特典①:青色申告特別控除 | 最大65万円控除(複式簿記および、e-Tax or 電子帳簿保存が条件) | 控除なし |
| 特典②:青色事業専従者給与 | 要件を満たせば経費として全額計上可能 | 一定額(事業専従者控除)のみ |
| 特典③:貸倒引当金 | 売掛金等の債権残高の5.5%相当額まで経費算入可 | 不可 |
| 特典④:純損失の繰越・繰戻し | 繰越:3年(特定非常災害による純損失は5年) 繰戻:前年分の還付請求が可能 |
繰越:災害による純損失のみ3年 (特定非常災害による純損失は5年) 繰戻:不可 |
青色申告と白色申告については、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。どちらで申告しようか悩んでいる人はチェックしておきましょう。
青色申告と白色申告の特徴について解説します。
青色申告の特徴
青色申告は、一定水準以上の帳簿記帳を行うことにより、所得税の計算においてさまざまな特典が認められる制度です。最大65万円の特別控除をはじめ、家族への給与を必要経費に算入できる「青色事業専従者給与」や、赤字を翌年以降に繰り越せる「純損失の繰越控除」など、白色申告に比べて大きな節税効果が期待できます。
ただし、青色申告を利用するためには事前に所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、提出期限は原則として青色申告により申告しようとする年の3月15日までとされています。1月16日以降に新たに開業した場合は開業から2か月以内の提出が求められます。期限を過ぎてしまうと、その年は白色申告となるため、計画的な手続きが重要です。
また、青色申告が認められるのは事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある個人事業者に限られます。給与所得や雑所得しかない場合は対象外となるため、利用できるかどうか事前の確認が必要です。
青色申告特別控除については、こちらの記事で詳しく解説しています。
白色申告の特徴
白色申告は、青色申告に比べて手続きが簡単で、開業届を提出すれば特別な申請なしで利用できる申告方法です。
日々の取引を簡易な方法で記録することが認められており、複式簿記のような専門的な知識までは求められません。記帳内容は、売上・仕入・経費などの金額を日々まとめて記載する程度で足りるため、負担は比較的軽めです。
ただし、白色申告には特別控除や赤字の繰越、家族への給与の必要経費化といった節税メリットがありません。
確定申告に必要な書類
確定申告には申告書のほか、日々の取引を記録した帳簿や領収書などの書類と、保険料払込証明書や医療費の領収書など各種控除の証明書類が必要です。確定申告に必要な書類について、青色申告と白色申告に分けて解説します。
青色申告の必要書類
青色申告を行う際は、事前に「青色申告承認申請書」の提出を済ませておく必要があります。そのうえで、確定申告時には以下の書類を提出します。
- 申告書(第一表・第二表)
- 青色申告決算書(一般用・農業所得用・不動産所得用などから選択)
青色申告決算書には、損益計算書や貸借対照表が含まれ、正規の簿記(複式簿記)によって記帳された帳簿をもとに作成します。簡易な記帳(単式簿記)の場合は、貸借対照表を作成できず、控除額も少なくなります。
また、青色申告で使用する帳簿は、仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などです。
白色申告の必要書類
白色申告では、以下の書類が必要です。
- 申告書(第一表・第二表)
- 収支内訳書(一般用・農業所得用・不動産所得用などから選択)
収支内訳書では、売上や経費の金額、仕入や人件費の内訳などを記載する必要があります。収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)をもとに申告書を作成します。
確定申告に必要な書類については、こちらの記事もご覧ください。
【青色申告】個人事業主の確定申告のやり方
青色申告を行うには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。原則として、その年の3月15日までに提出しなければ、該当年分は白色申告扱いになりますので注意が必要です(新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内)。
個人事業主の青色申告の方法について詳しく見ていきましょう。
①日々の取引を記帳する
日頃から帳簿付け(記帳)をしておくことが重要です。
現金出納帳や売上帳、経費帳などを使い、売上や支出を漏れなく記録しましょう。青色申告の場合は複式簿記での記帳が必要です。領収書や請求書など証拠書類も整理・保存しておきます(青色では原則7年間の保存義務、一部書類は5年)。
日々の記帳をスムーズに行いたいという人は、会計ソフトの利用がおすすめです。銀行口座やクレジットカードとの連携により、自動で仕訳入力ができるものもあります。
②1年間の収入と経費を集計する
帳簿への記帳をもとに、1月1日から12月31日までの収入と経費を集計し、年間の「事業所得」を算出します。
事業所得 = 総収入金額 - 必要経費
この所得金額がその後の控除計算や納税額の基礎となるため、正確に集計することが重要です。
③所得金額と控除額を計算する
事業所得を算出したら、そこから各種所得控除を差し引いて、課税所得を求めます。所得控除とは、納税者の生活状況や支出内容に応じて、一定の金額を所得から差し引く制度であり、所得税の負担を軽減する役割を持っています。
それぞれの所得控除には適用要件があるため、自分の状況に合った控除を確認し、合計所得金額から適用可能な控除額を差し引くことが大切です。
主な所得控除の種類は以下のとおりです。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除(ふるさと納税など)
- 障害者控除
- 寡婦控除・ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除・配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
④税額を計算する
所得控除を適用したあとの「課税所得金額」に対して、所得税の税率を掛けて所得税額を算出します。所得税は累進課税制度を採用しており、所得が多くなるほど適用される税率が高くなるのが特徴です。
下記の表は、課税所得金額ごとの所得税率と控除額をまとめたものです(令和6年分時点の税率)。
| 課税所得金額(A) | 所得税額の計算式 |
|---|---|
| ~1,949,000円 | (A) × 5% |
| 1,950,000円~3,299,000円 | (A) × 10% - 97,500円 |
| 3,300,000円~6,949,000円 | (A) × 20% - 427,500円 |
| 6,950,000円~8,999,000円 | (A) × 23% - 636,000円 |
| 9,000,000円~17,999,000円 | (A) × 33% - 1,536,000円 |
| 18,000,000円~39,999,000円 | (A) × 40% - 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | (A) × 45% - 4,796,000円 |
⑤申告書類を作成する
青色申告を行うには、各種帳簿や集計データをもとに、確定申告に必要な書類を作成します。国税庁ホームページにある「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが便利です。
画面の案内に沿って金額や必要事項を入力するだけで、確定申告書や青色申告決算書などの書類を作成できます。入力した内容に応じて、必要な付表や明細書も自動的に生成されるため、書類の漏れや記載ミスの防止にも役立ちます。
⑥申告書類を提出する
作成した申告書類は、次のいずれかの方法で提出します。
- e-Taxで申告する
- 郵便または信書便で、所轄税務署または業務センターに送付する
- 所轄税務署の窓口に提出する
- 所轄税務署の時間外収受箱に投函する
⑦税金を納付する
確定申告を行ったあとは、所得税などの税金を自ら納付する必要があります。以下のいずれかの方法で期限内に納付を行いましょう。
- 振替納税(預貯金口座からの自動引落し)
- ダイレクト納付(e-Taxから即時または日付指定で引落し)
- インターネットバンキングやATMでの電子納税
- クレジットカード納付(決済手数料が別途必要)
- スマホアプリ納付(Pay払い、30万円以下)
- コンビニ納付(QRコード使用、30万円以下)
- 金融機関や税務署窓口での現金納付
個人事業主の確定申告に関するよくある質問
Q1. 所得が少ない年も確定申告しなければいけない?
課税所得がゼロ以下で税金が発生しない年は、基本的に確定申告の義務はありません。
ただし、青色申告の場合は赤字でも確定申告をしておくことで、翌年以降に損失を繰り越せる「純損失の繰越控除」が受けられるなどのメリットがあります。
Q2. これから青色申告を始めたいが、どうすれば良い?
青色申告を始めるには、所轄税務署へ「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。対象となるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある方(非居住者の場合は国内で業務を行っている方)です。
提出期限は以下のとおりです。
- 原則:その年の3月15日まで
- 1月16日以降に開業・賃貸を始めた場合:開始(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2ヶ月以内
- 相続で事業を承継した場合:死亡日に応じて4ヶ月以内〜翌年2月15日で規定
申請は、e-Taxソフト(WEB版)の「マイページ」からオンラインで手続きできます。
Q3. 確定申告についてどこかで相談できる?
確定申告に関する相談は、税務署で無料で受けられます。
窓口での対面相談のほか、電話での問い合わせも可能です。
また、国税庁のチャットボット(ふたば)を利用すれば、土日や夜間でも確定申告に関する基本的な疑問を解消できます。
確定申告をスムーズに行うなら会計ソフトの活用がおすすめ
確定申告は、個人事業主やフリーランス、自営業者にとって毎年欠かせない手続きです。
青色申告を選ぶことで得られるメリットは大きいものの、申請期限や帳簿付けなどのルールを守る必要があります。一方で、白色申告は手間は少ないですが、控除の面では不利になる可能性もあります。
帳簿付けから電子申告まで自動化できる会計ソフトを活用すれば、初心者でもスムーズかつ正確に申告できます。
ソリマチの青色申告ソフト「みんなの青色申告」なら、直感的に日々の帳簿を作成でき、確定申告書類の作成や申告までをスムーズに行えます。
今なら30日間の無料体験も利用できるので、まずは実際に使ってみてはいかがでしょうか。
ABOUT監修者紹介
 税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
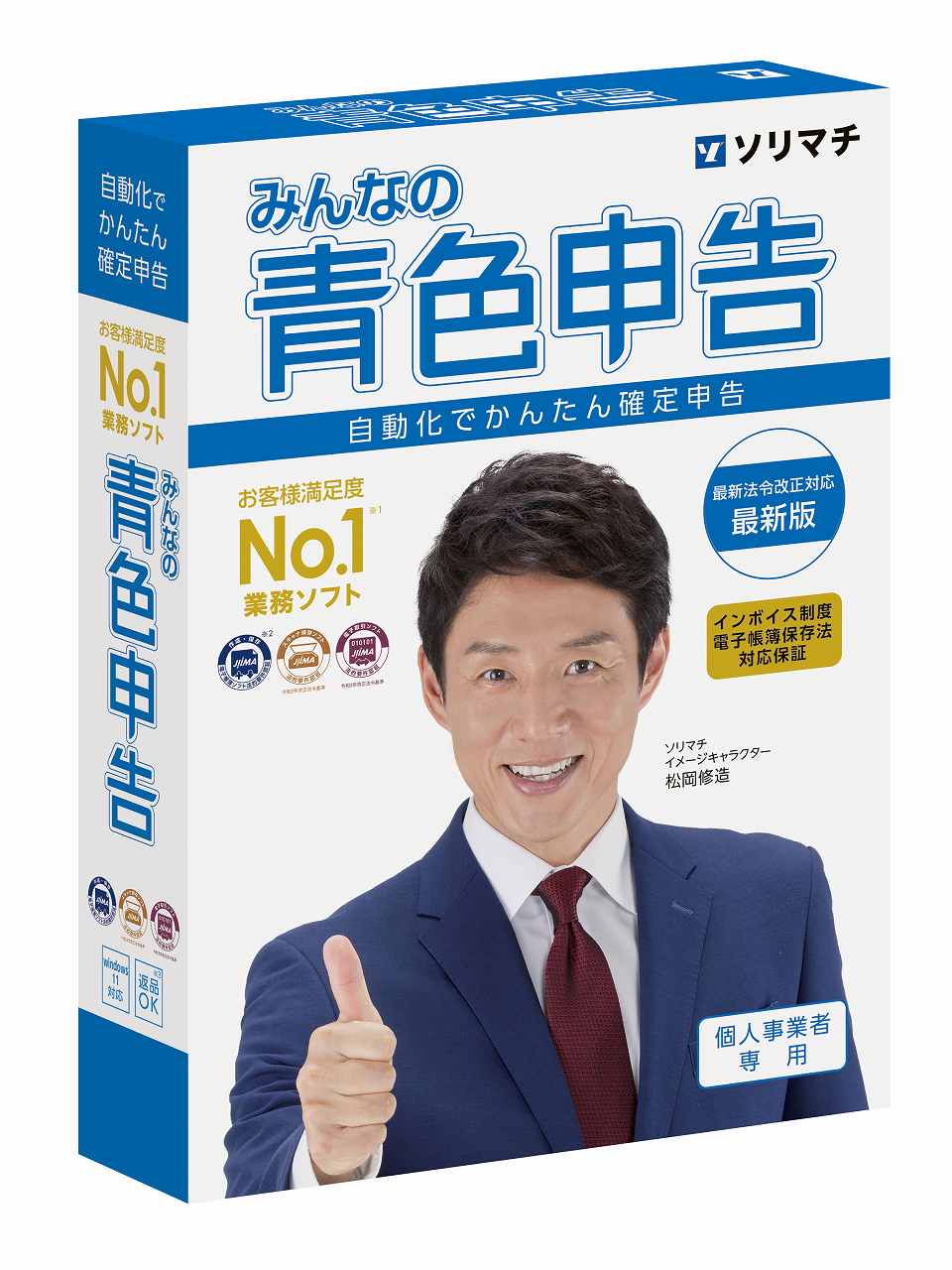 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。







