税理士監修|青色申告特別控除とは?65万円控除や55万円控除を受ける条件をわかりやすく解説
確定申告

Contents
確定申告の際に、節税メリットが大きいのが「青色申告特別控除」です。個人事業主や不動産収入のある方が最大65万円の控除が受けられる制度として知られていますが、控除額によって適用条件が異なるため、正しく理解しておくことが重要です。
本記事では、青色申告特別控除の基本から、55万円・65万円・10万円の控除を受けるための条件、注意点などについて詳しく解説します。
ソリマチの青色申告ソフト「みんなの青色申告」なら65万円控除の条件を満たした確定申告が可能です!安定した操作性と手厚いサポートで、皆さんの確定申告をサポートします。
青色申告特別控除の基本
青色申告特別控除は、青色申告を行う個人事業主や不動産所得者などが、正確な帳簿付けと適切な手続きを行うことで所得から控除を受けられる制度です。最大で65万円の控除が受けられることから、節税効果が非常に高く、個人事業者にとっては大きなメリットとなります。
ただし、控除額によって求められる要件は異なり、帳簿の付け方や提出方法、電子申告の有無などが影響します。また、対象となる所得の種類や、事前の申請手続きも重要なポイントです。
ここでは、青色申告特別控除の仕組みや対象となる所得、控除額の種類、控除を受けるために必要な準備について、順を追ってわかりやすく解説します。
青色申告特別控除とは
青色申告特別控除とは、青色申告を行う個人事業主や不動産所得のある方が、一定の条件を満たすことで所得から差し引くことができる控除制度のことです。
以下、3種類の控除があります。
- 65万円控除
- 55万円控除
- 10万円控除
対象となる所得は「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみ
青色申告特別控除は、すべての所得に対して適用されるわけではありません。控除の対象となるのは、次の3つの所得に限られます。
事業所得:個人事業主やフリーランスなどが事業活動によって得た所得
不動産所得:賃貸住宅や貸地などの不動産から得られる収入
山林所得:山林を伐採・譲渡したことによって得られる所得(5年以上保有していたものに限る)
たとえば、給与所得や配当所得、株の譲渡所得などは青色申告の対象外であり、青色申告特別控除の適用も受けられません。
また、不動産所得については事業的規模であるかどうかによって適用される控除額が変わってきます(詳細は後述)。したがって、自分の収入がどの所得に該当するかを正しく分類することが、控除を受ける第一歩です。
事前に届出が必要
青色申告特別控除を受けるには、単に帳簿をつけるだけではなく、所轄の税務署に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。この申請をして初めて、青色申告が認められ、各種の控除を受けることができるようになります。
申請書の提出期限は以下のとおりです。
- 青色申告をする年の3月15日まで(例:2027年分の青色申告をしたい場合は2027年3月15日)
- 青色申告をする年の1月16日以後に事業を開始したり不動産を貸し付けたりした場合は、事業開始した日
この期限を過ぎてしまうと、その年分については青色申告が認められず、特別控除を受けることができません。
55万円控除の条件
青色申告特別控除のうち、55万円控除を受けるには、一定の条件を満たす必要があります。65万円控除に比べると電子申告等の要件はありませんが、正確な帳簿管理と期限内の申告が求められます。
以下が要件です。
- 不動産所得または事業所得があること
- 正規の簿記の原則による記帳(一般的には複式簿記)
- 帳簿に基づいた財務書類の添付(貸借対照表および損益計算書)
- 確定申告期限までに申告書を提出する
55万円控除を受けるうえで注意すべき点がいくつかあります。まず、現金主義による所得計算の特例を選択している場合は、たとえ帳簿付けなどの他の要件を満たしていても55万円控除を受けることはできません。
また、控除を適用できる金額にも上限があります。不動産所得と事業所得の合計額が55万円未満である場合は、控除額もその合計額が上限となります。ここでいう合計額とは、損益通算前の黒字部分の金額を指し、もし一方の所得に赤字が出ていたとしても、その損失は控除額の計算には影響しません。
65万円控除の条件
青色申告特別控除の中で最も大きな節税効果を得られるのが、65万円控除です。ただし、その分だけ要件は厳格に定められており、正しい帳簿付けに加えて電子化への対応も求められます。
まず、65万円控除を受けるためには、55万円控除の要件をすべて満たしていることが前提となります。つまり、事業所得や不動産所得があり、複式簿記で正確に帳簿を付け、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して、申告期限までに提出する必要があります。
そのうえで、さらに65万円控除を受けるには、次のいずれかの条件を満たしていることが求められます。
ひとつは、事業に関する仕訳帳および総勘定元帳について、電子帳簿保存法の要件を満たして電子的に保存していることです。
単にパソコンで記録しているだけでは足りず、「優良な電子帳簿」として認められる水準で保存していることが求められます。具体的には、データの訂正・削除履歴が残ることや、検索機能が備わっていることなどの技術的要件を満たし、届出書を税務署に提出する必要があります。ただし、過去にすでにこの制度を利用していた方で、その後も要件を満たし続けている場合は、改めて届出をする必要はありません。
もうひとつの条件は、確定申告書や添付書類一式をe-Taxを通じて電子申告することです。帳簿類を紙ではなく電子データとして、所定の形式で国税庁に送信します。ただし、PDFやスキャン画像などの「イメージデータ」で送信するのではなく、e-Taxが定める形式で正確にデータを提出する必要があります。
10万円控除の条件
10万円控除が適用されるのは、複式簿記による記帳をしていない場合や、作成した帳簿が保存要件を満たしていない場合、あるいは電子申告を行っていないなど、上位の控除に該当しない青色申告者です。
また、不動産所得が事業的規模に満たないケースも該当します。たとえば、賃貸物件を数室しか所有していないような小規模経営の場合には55万円や65万円の控除は受けられず、10万円控除にとどまることになります。
また、控除できる金額は一律ではなく、所得の状況によって変動します。不動産所得、事業所得、山林所得の合計が10万円未満であれば、その合計額が控除の上限となります。なお、この合計額は損益通算前の黒字分のみを対象とするため、事業所得が赤字で不動産所得が黒字の場合には赤字分は差し引かれず、黒字部分のみで控除額が決まります。
控除の適用順にも一定のルールがあります。複数の所得がある場合は、不動産所得から順に事業所得、山林所得という順番で適用されます。
なお、山林所得については、10万円控除の対象にはなり得るものの、事業所得や不動産所得で55万円または65万円控除を適用している場合には、その年分の山林所得について10万円控除を併用できません。
青色申告特別控除を受けるときの注意点
青色申告特別控除を確実に受けるためには、条件を満たすだけでなく、いくつかの重要な注意点を理解しておくことが必要です。以下のポイントを押さえて、控除の適用漏れや不備を防ぎましょう。
65万円控除と55万円控除は複式簿記での記帳が必要
65万円控除と55万円控除を受けるための最も基本的な要件は、複式簿記による帳簿付けです。単式簿記とは異なり、取引を「借方」「貸方」の両側から記録し、資産や負債、収益、費用の動きを正確に把握できるのが特徴です。
また、複式簿記で作成した帳簿をもとに、損益計算書と貸借対照表を作成し、確定申告書に添付する必要があります。帳簿や財務諸表の形式に不備があると、控除が適用されない可能性もあるため、会計ソフトなどを活用して正確な帳簿管理を行いましょう。
申告期日や添付書類を守る
青色申告特別控除を受けるには、確定申告の提出期限(原則として3月15日※土日祝日の場合は翌日)を厳守する必要があります。期限を過ぎると、どれだけ帳簿を正確に作成していても、65万円または55万円の控除を受けることはできず、10万円控除となります。
さらに、提出する申告書には必要な書類(損益計算書・貸借対照表など)を添付することも重要です。申告内容に不備があれば、税務署から問い合わせが入ったり、控除が認められなかったりする可能性もあるため、期限と内容の両方に注意しましょう。
不動産所得が事業的規模でない場合は10万円控除
不動産所得においては、「事業的規模」であるかどうかによって、適用される控除額が大きく異なります。
一般的に、5棟10室基準(アパートなら10室以上、戸建てなら5棟以上)が事業的規模の目安とされており、これを満たさない場合は、たとえ複式簿記で帳簿を付けていたとしても、55万円控除や65万円控除は受けられず、10万円控除が上限となります。
所得控除の順番は不動産所得から
確定申告では、複数の所得区分がある場合、青色申告特別控除は不動産所得から先に適用されるルールがあります。
たとえば、事業所得と不動産所得の両方がある場合、不動産所得に青色申告特別控除がまず充当され、残りが事業所得に適用されます。この順序は原則であり、納税者が自由に選ぶことはできません。
青色申告特別控除を受けるなら会計ソフトの利用がおすすめ
青色申告特別控除、とくに55万円控除や65万円控除を受けるには、複式簿記での記帳や正確な帳簿管理、申告書類の作成が不可欠です。しかし、これらの作業は手作業では煩雑で、ミスのリスクも高まります。
そこでおすすめなのが、青色申告対応の会計ソフトの活用です。たとえば「ソリマチの青色申告専用の会計ソフト『みんなの青色申告』」のようなソフトを使えば、次のようなメリットがあります:
- 複式簿記に対応した入力支援機能で、初心者でも安心して帳簿がつけられる
- 損益計算書・貸借対照表が自動で作成可能なので、帳簿の提出もスムーズ
- e-Taxとの連携により電子申告も簡単に実現できるため、65万円控除の条件も満たしやすい
- 操作に不安があってもサポート体制が充実しているので、困ったときも安心
複式簿記や電子申告に不慣れな方でも、こうしたソフトを活用することで、制度を最大限に活用した節税対策が可能になります。
まとめ
青色申告特別控除は、個人事業主や不動産所得のある方にとって、非常に効果的な節税制度です。最大65万円の控除を受けるには、複式簿記や電子申告といった一定の要件を満たす必要がありますが、その分メリットも大きくなります。
55万円控除、10万円控除についても、それぞれの条件や対象所得に応じて使い分けることで、確定申告をより有利に進めることができます。
会計ソフトを活用すれば、煩雑な記帳や申告作業も簡単になり、控除要件もクリアしやすくなります。特に、「ソリマチの『みんなの青色申告』」のようにサポートが充実したソフトを使えば、初めての方でも安心して65万円控除を目指せるでしょう。
節税対策の第一歩は、制度を正しく知り、しっかり活用することです。ぜひこの記事を参考に、ご自身に最適な青色申告の形を見つけてください。
ABOUT監修者紹介
 税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士。公認会計士。
有限責任監査法人トーマツにて会計監査業務に従事。
23歳時、「日本一若い会計事務所」として”ACLEAN(アクリーン)会計事務所”を開業。スタートアップ、マイクロ法人を中心とした税務業務や補助金・融資等の資金調達支援、経理を対象とした業務改善コンサルティングを展開。
2023年に同事務所を”税理士法人グランサーズ”と統合。同法人の代表に就任。中小企業の税務顧問対応、内部統制構築支援、組織再編支援、事業承継・企業のクラウドサービス活用と経理効率化サービスも提供。また、自身のボディメイクの経験を活かした健康経営に関するコンサルティングも得意としている。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」絶賛配信中!
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
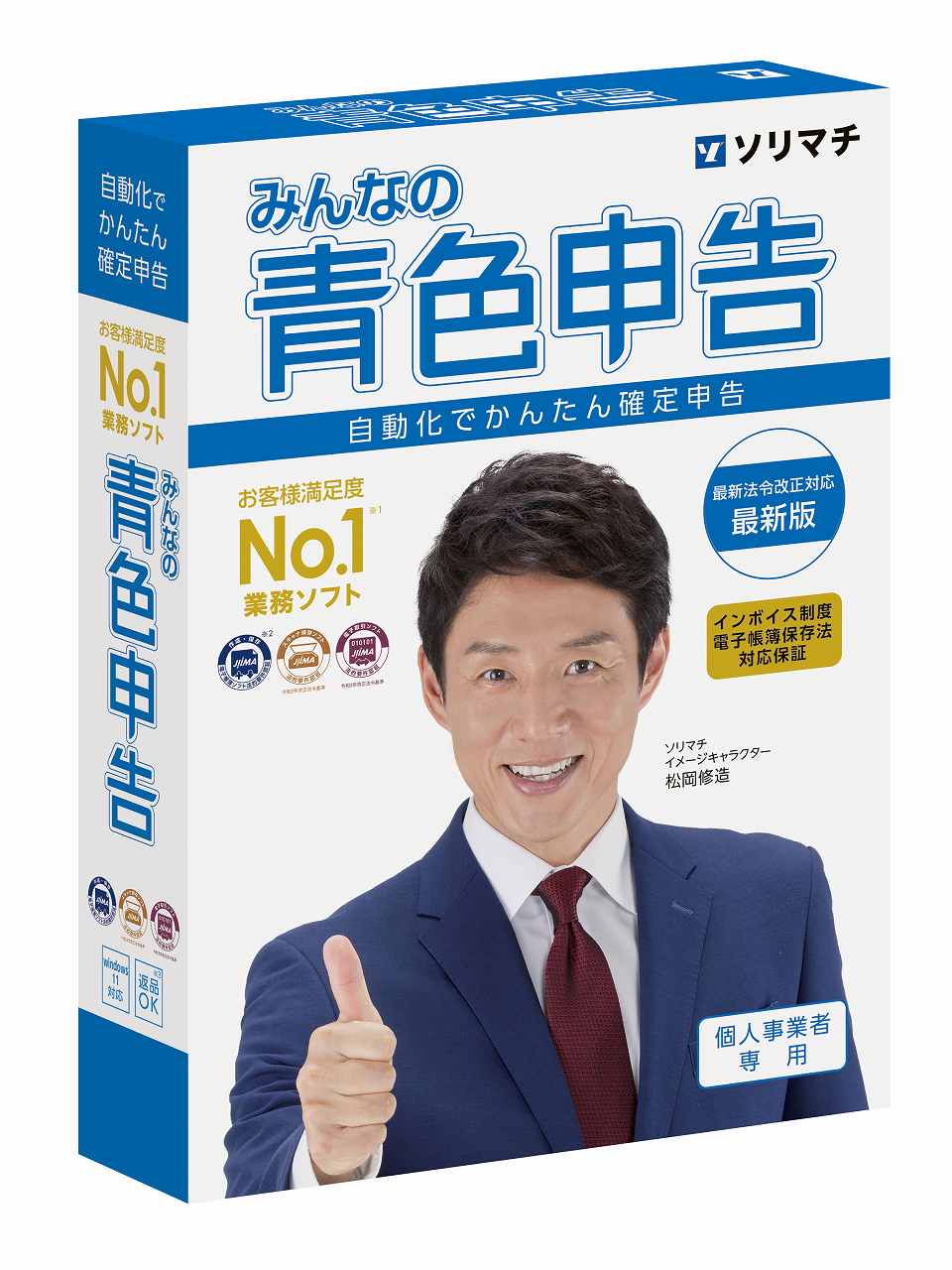 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。








