ダブルワークの確定申告のやり方は?必要書類や書き方、申告をしないとどうなるか解説
確定申告

Contents
パートやアルバイトなど、複数の職場で働く「ダブルワーク」の人が増えています。特に非正規雇用を掛け持ちしている場合、「税金はどうなるのか」「確定申告は必要なのか」といった疑問を抱えることも多いでしょう。
通常、会社員であれば勤務先が1か所のみであれば年末調整で所得税の精算が済み、自分で確定申告を行う必要はありません。しかし、複数の収入源があるダブルワークの場合は事情が異なります。
本記事では、ダブルワークにおける確定申告の必要性や、年末調整との違い、税金の計算方法など、基本的な仕組みをわかりやすく解説します。
ダブルワークの確定申告とは?年末調整との違いと税金の基本
近年、生活費の補填やスキルアップ、副業解禁の流れなどを背景に、「ダブルワーク(複数の仕事の掛け持ち)」をする人が増えています。特に、パートやアルバイトなどの非正規雇用を複数掛け持ちしている方にとって、年末が近づくと気になるのが「税金の手続き」ではないでしょうか。
税金の処理については、「年末調整で済むのか」「確定申告が必要なのか」といった判断が重要です。ひとつの職場でしか働いていない場合は、会社が税額の精算をしてくれる年末調整で完結することが一般的ですが、ダブルワークの場合はその限りではありません。
まず理解すべきは、年末調整は1人につき1社のみが対象であり、2か所目以降の勤務先では年末調整が行われないという点です。たとえば、平日は主婦としてパート勤務、土日は別のアルバイトをしているようなケースでは、片方の職場でしか年末調整が受けられないため、もう一方の給与については自分で所得税を計算しなければならなくなります。
その結果、年間の全収入を合算したうえで、納めるべき税額を正しく計算し、自分で確定申告を行う必要が生じます。
ダブルワークで確定申告が必要になるケース
ダブルワークをしているからといって、すべての人に確定申告の義務があるわけではありません。確定申告が必要かどうかは、収入の種類や金額によって決まります。ここでは、パートやアルバイトなど複数の勤務先から給与を受け取っている人が、確定申告の対象になる代表的なケースを整理します。
副収入が年間20万円を超える場合
2か所以上の勤務先から給与の支払いを受けている人で、かつ給与のすべてが源泉徴収の対象となっている場合、年末調整がされなかった給与収入と、給与所得や退職所得以外の所得との合計額が年間20万円を超えると、確定申告を行う必要があります。
2か所以上で年末調整を受けてしまった場合
原則として、年末調整は1人につき1か所の勤務先でしか行えません。2か所以上の勤務先に扶養控除等申告書を提出してしまい、双方で年末調整を受けてしまった場合は、本来調整されるべきでない税額が控除されていることになり、正しい税額と差が生じます。
このような場合、税務署としては年末調整のやり直しはできないため、自分で確定申告をして税額を再計算・精算する必要があります。
給与所得以外の所得がある場合
本業・副業を問わず、給与以外の所得(事業所得、雑所得、不動産所得、配当所得など)の合計額が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年間の収入が2,000万円を超える場合
ダブルワークの形態や職種によっては、2か所以上の勤務先からの給与収入の合計が2,000万円を超えるというケースも考えられます。たとえば、本業が高収入の正社員で、副業として専門性の高い業務(コンサルティング、医師の当直、士業など)を行っているような場合が該当します。
このように、給与収入の年間合計額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象外とされ、自分で確定申告を行うことが義務付けられています。
ダブルワークで確定申告が不要となるケース
ダブルワークをしている場合でも、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。副収入の金額や全体の年収、控除の適用状況などによっては、確定申告が不要とされるケースもあります。
ここでは、確定申告が不要となる条件について解説します。
副収入が年間20万円以下の場合
本業の勤務先で年末調整を受けており、かつ副業などで得た給与以外の所得(雑所得・事業所得など)の合計が年間20万円以下にとどまる場合は、所得税の確定申告は不要とされています。
年収が基礎控除内に収まる場合
そもそもダブルワークの年間収入が低く、確定申告をせずとも適用される所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)を差し引いた後の「課税所得」がゼロ以下となる場合も、確定申告の必要はありません。
特に、学生や主婦などでパートやアルバイトを複数掛け持ちしているものの、全体の収入が少ないケースではこの条件に該当することがあります。
2025年(令和7年)度の税制改正では、物価上昇への対応や低所得層への配慮を目的に、基礎控除の上限が大きく引き上げられました。
改正後:最大58万円に引き上げ(物価動向に応じた10万円の上乗せ)
さらに、低〜中所得者層には階層別で最大37万円の控除上乗せが認められる新制度も導入されています。
下記の関連記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてください。
なお、確定申告を省略できるケースであっても、年末調整されていない所得については住民税の申告が必要です。この点については後述します。
また、副収入20万円以下の人でも、医療費控除や寄附金控除などを受けたい場合はあえて確定申告を行うケースもあります。
ダブルワークで確定申告をしないとどうなる?
ダブルワークをしていると、本業では年末調整が済んでいても、副業の収入については自分で確定申告をしなければならないケースがあります。しかし「収入が少ないから大丈夫だろう」「バレなければ問題ない」といった理由で、確定申告をしないまま放置してしまう人も少なくありません。
しかし、確定申告を行わないことには税務上の重大なリスクが伴います。
追徴課税(無申告加算税・延滞税)が発生する……期限後に申告したり、税務調査で発覚した場合は、税額に応じて最大25%の加算税が課される。延滞が長引くと利息分(延滞税)も増える。
住民税の課税・納付が遅れる……確定申告の内容をもとに住民税は算定されるため、申告しないと課税がされず、後日まとめて請求されるケースもある。
納税証明書・所得証明書が発行できない……住宅ローンや保育園の申請など、各種手続きで必要な証明書が発行されず、生活に支障が出る可能性がある。。
行政サービス・扶養控除などに影響が出る……正確な所得を申告しないと、扶養控除の不適用や国民健康保険料の誤算定など、他の行政制度にも影響する。
ダブルワークの確定申告のやり方・手順
ダブルワークをしている人のうち、確定申告が必要な場合には、税務署への申告手続きが必要になります。とはいえ、「確定申告は難しそう」と感じる方も多いかもしれません。ここでは、ダブルワークを前提とした確定申告の基本的な流れと準備すべき書類、申告の時期などについて解説します。
確定申告の時期と期限
所得税の確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの間に行うと法律で定められています(所得税法第120条)。この期間内に税務署への申告および納税を済ませる必要があります。
なお、3月15日が土曜日・日曜日にあたる場合は翌週の月曜日が申告期限となります。
確定申告に必要な書類
ダブルワークでの確定申告を正確に行うには、収入や控除、本人情報などを証明する各種書類が必要です。以下に、代表的な必要書類を整理します。
源泉徴収票
主たる勤務先だけでなく、副業先を含むすべての勤務先の源泉徴収票を手元にそろえることが必要です。
各種控除証明書
確定申告では、適用できる控除の証明書が必要です。たとえば以下のようなものが該当します。
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書
- 社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
- 寄附金受領証明書(ふるさと納税等)など
本人確認書類
マイナンバーカード、またはマイナンバー通知カード+運転免許証などのパターンで本人確認書類を添付します。
その他の書類
副業が給与所得以外に該当する場合は、以下のような帳簿や明細書が必要です。
- 事業所得の場合:収支内訳書(白色申告)または青色申告決算書(青色申告)
- 不動産収入がある場合:不動産所得の収支明細書または青色申告決算書(青色申告)
- 株式取引を行っている場合:特定口座年間取引報告書や譲渡損益計算書
確定申告書の書き方と提出方法
パートやアルバイトを掛け持ちしている人が確定申告をする場合、まずは勤務先ごとの源泉徴収票をすべて集めます。1社分だけではなく、掛け持ちしているすべての勤務先から受け取るのが基本です。年末に「源泉徴収票がまだ届いていない勤務先」があれば、早めに依頼して入手しておきましょう。
申告書は国税庁の「確定申告書等作成コーナー」やe-Taxで作成するのが最も簡単です。質問に答えるだけで自動計算されるため、手書きよりもミスが少なく、控除額や所得税額も自動で反映されます。
記入するのは、第一表と第二表の2つです。まず、第一表の「収入金額等」の「給与(オ)」欄には、掛け持ちして得たすべての勤務先の給与収入を合算した金額を記入します。次に、「所得金額等」の「給与(6)」欄には、合算した給与収入から給与所得控除を差し引いたあとの金額(給与所得)を記載します。
続いて、第二表の「所得の内訳」欄に、それぞれの勤務先ごとの収入金額と源泉徴収税額を記入します。ここは源泉徴収票に記載されている「支払金額」と「源泉徴収税額」をそのまま転記すれば問題ありません。
申告書の作成が終わったら、提出方法を選びます。提出方法は、電子申告(e-Tax)、郵送、税務署への持参の3通りがあります。最も便利なのはe-Taxによる電子申告で、マイナンバーカードやスマホの電子証明書を使って、自宅から簡単に提出できます。
郵送の場合は、完成した申告書と必要書類を封筒に入れ、住所地を管轄する税務署に送付します。
ダブルワークの確定申告で注意すべきポイント
ダブルワークでの確定申告は、複数の収入を合算して申告する必要があるため、思わぬ記入漏れや税務上のトラブルにつながることがあります。ここでは、申告時によくある見落としや、忘れがちなポイントを解説します。
確定申告不要でも住民税の申告は必要
前述のとおり、副業などの所得が年間20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。しかし、本業の給与が年末調整で処理されていても、副業で得た収入がある場合は、毎年1月〜3月頃に各自治体が受付する「住民税申告(市区町村への申告)」を行う必要があります。これは、住民税は所得税とは異なり「申告省略」という特例が無いためです。
専従者として働いている場合は注意
ダブルワークの中には、家族が経営する事業を手伝いながら、別の勤務先でパートやアルバイトをしているケースもあります。このように「事業専従者」として働く場合は、いくつか注意すべき税務上のルールがあります。
青色申告者の事業専従者として給与の支払いを受けている、または白色申告者の事業専従者となっている人は、配偶者控除や扶養控除の対象にはなれません。
さらに、専従者が外で働いて収入を得ている場合には、事業主側での専従者給与の必要経費算入、もしくは専従者控除が認められない可能性もあります。
つまり、家族経営の手伝いと外でのパート勤務を同時に行うことは法律上禁じられてはいませんが、税制上の優遇が受けられなくなるリスクがあります。専従者として届け出ている家族がダブルワークを検討している場合は、事前に税理士や税務署へ相談しておくことが大切です。
その他の注意点(確定申告書の記入漏れなど)
最後に、申告書の記入漏れ・添付漏れにも注意が必要です。特にダブルワークの人に多いのが、副業分の所得を第二表「所得の内訳」欄に記入し忘れるミスです。勤務先ごとに源泉徴収票が発行されるため、1社分だけ記入して終わってしまうケースが少なくありません。
すべての勤務先分の収入と源泉徴収税額を正確に合算し、給与所得以外に雑所得や事業所得がある場合は、それぞれの欄にも記載しましょう。
また、医療費控除や寄附金控除、雑損控除など、年末調整では申告できなかった控除を適用する場合は、必ず明細書や証明書を添付します。e-Taxを利用すれば、医療費や寄附金の控除データをマイナポータル経由で自動反映できるため、添付漏れの防止にもつながります。
まとめ
パートやアルバイトなど、複数の勤務先で働く「ダブルワーク」は、収入が増える一方で、税金の取り扱いが複雑になりがちです。特に、1社目では年末調整が行われても、2社目以降の勤務先では年末調整がされないため、複数の収入を合算して自分で確定申告を行う必要が生じるケースがあります。
確定申告を怠ると、追徴課税(無申告加算税・延滞税)や住民税の遅延、証明書の発行不可、副業の発覚リスクなど、思わぬ不利益を受ける可能性もあります。本記事で解説した内容を参考に、適切に確定申告を行いましょう。
会計ソフト「みんなの青色申告」で確定申告もラクラク
ダブルワークの方が確定申告を効率的に行うには、会計ソフトの活用がおすすめです。
特に、副業で事業所得や雑所得がある場合、日々の収支管理から申告書作成までを一貫してサポートしてくれる会計ソフトは強い味方になります。
ソリマチ株式会社の「みんなの青色申告」は、青色申告専用の会計ソフトとして個人事業主やフリーランスの方々に好評をいただいています。
「みんなの青色申告」は初心者にもやさしい操作性を重視しており、初めて確定申告をする方でも直感的に使えます。
電話での直接相談もユーザー登録から最大15か月は無料でご活用いただけますので、不明点があっても安心です。
まずは、30日間のお試し体験で、実際に使いやすさを体感してみてください!
ABOUT監修者紹介
 税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
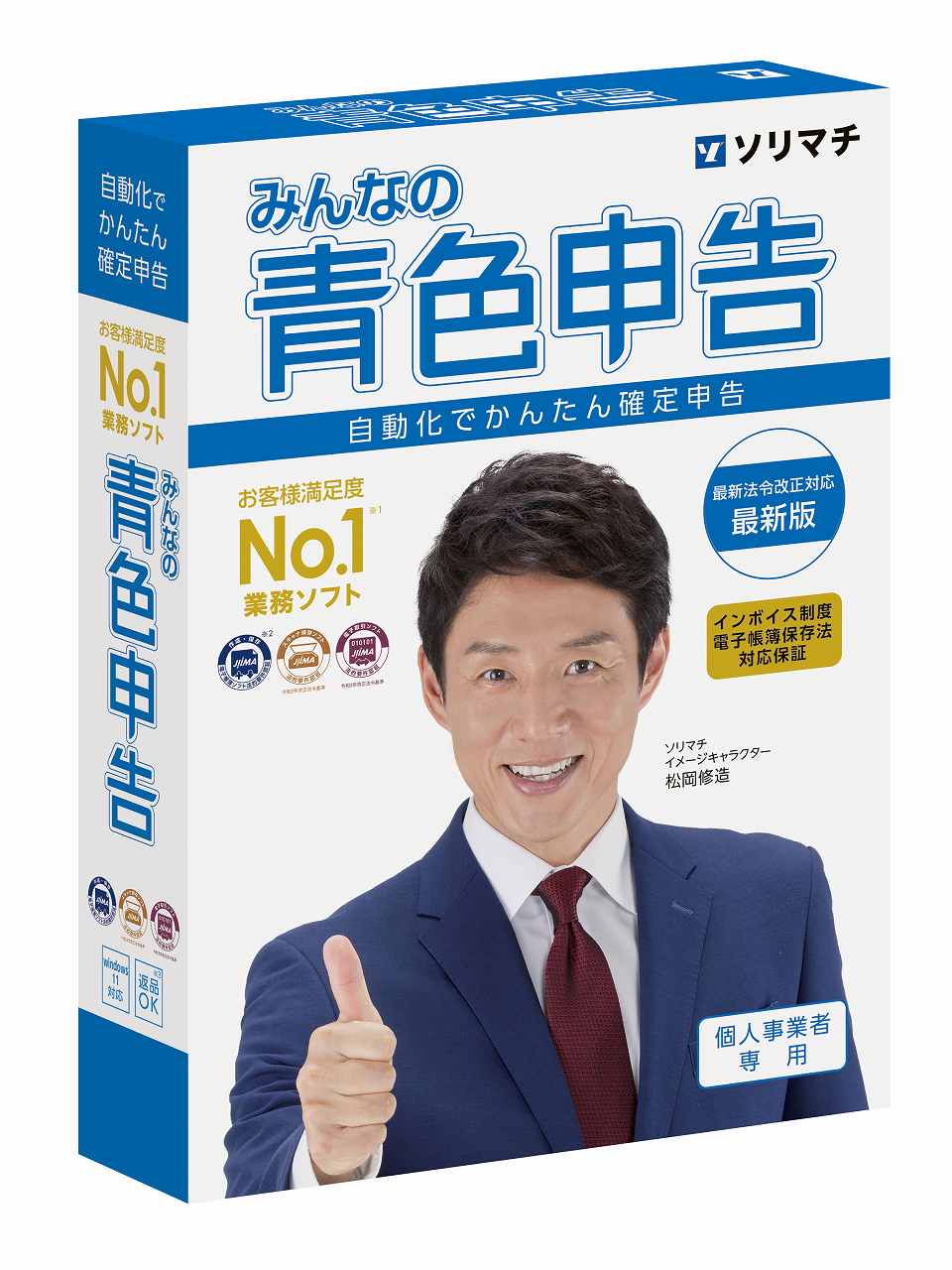 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。







