ストレスチェック後の職場改善
社会保険ワンポイントコラム

仕事や職業生活に関して「強い不安、悩み、ストレスとなっていると感じる事柄がある」と答えた人は、コロナ禍前は50%強程度を推移していたのが、令和4年度に80%と急上昇し最新のデータでも80%台と変わっていません。
ストレスチェックは、このような職業上のストレスに早期対応するために導入されました。しかし、「実施するだけ」になっている会社が散見されます。どこかのストレスチェック請負会社に頼んで実施し、高ストレス者には産業医への面談を案内する。その程度で終わっていませんか?
今回は、ストレスチェックの有効活用に関するお話です。
ストレスチェックには目的が2つある
ストレスチェックの2つの目的をあらためて確認しておきましょう。
1つ目は「受検者自身が強いストレスを受けていることに気づく」ことです。強いストレス状態が続くとメンタルヘルス不調に陥る危険が高まります。それを予防するためにまず自分のストレス状態を知ろうというのが第一の目的です。ストレスがかかっていること、あるいはメンタルヘルス不調に陥っていることに自分では気づきにくい面があるからです。
強いストレスがある場合、まずは自分で自分のストレス状態をケアする「セルフケア」がお勧めです。筋トレ、ジョギング、ヨガ、アロマ、庭いじりなど、何であれその時間を過ごした後「あ、今の時間自分は仕事のことが全く頭に浮かんでなかったな」と思える活動を探してみましょう。
2つ目の目的は職場改善です。よりストレスの少ない職場にするため、ストレスチェックを集団で分析して職場環境の改善に組織的に取り組むものです。個人的にはこれこそがストレスチェックの一番重要な使い方だと思っています。実際これを行った企業では、労働者のストレスの低下や生産性の向上がみられるという研究結果が複数あり、厚生労働省のサイトに掲載されています。
つまりストレスチェックは、労働者の健康にも、会社の業績向上にも役立つのです。
職場改善の3つのやり方
とはいえ、どのように職場改善を行えばいいのでしょうか?これに関しても厚生労働省は以前から資料を出しています。「こころの耳」というサイトをご覧ください。ストレスチェックだけでなく、職場のメンタルヘルスに関して役に立つ資料が多く掲載されておりますので、メンタルヘルス問題で悩む企業の担当者は必読です。
さて、ストレスチェックの集団分析結果による職場改善の方法は大きく3つあります。経営層主体の方法・現場管理職主体の方法・従業員参加の方法の3つです。
どのやり方でも、重要なのはPDCAのサイクルを回すということです。職場改善のためのプランを立てて実行⇒翌年のストレスチェックの結果を評価⇒新たなアクションを決定。目に見える効果が出るには少なくとも3年はかかりますが、この文化が根付いてしまえば自然に働きやすい環境が続くというのが産業医としての実感です。
① 経営層主体の方法
ストレスチェックの集団分析結果を見て、経営者が例えば「うちの会社では残業が多い人が多いから水曜日はノー残業デイにしよう」とトップダウンで決める方法です。実行の力はあるのですが、必ずしも正鵠を得ているとは限らないというのが欠点です。
②現場管理職主体の方法
各課長が自分の部下たちがどこにストレスを抱えているかを考え、それに対して対策を打っていきます。ここで重要になるのは他部署の課長との情報交換です。他部署の好事例などを参考にすることで独りよがりの対策になることを防ぐことができます。このやりかたは現場に近いので効果的ですが、課長への負担が過重になる欠点があります。
③従業員参加型
一番効果があるといわれています。詳しいやり方は先述の「こころの耳」に載っていますからここでは簡単に説明します。
まず各課くらいの単位で、自分たちの職場のいいところをそれぞれ投票し、さらに改善したい点も投票して、1時間程度の会合を持ちます。そこでさらに話し合って、この職場をもっと働きやすくするにはどうすればいいか、そのために何をするか、だれが責任者になるかを決め、半年以上をかけてその目標を達成していきます。

従業員参加型のコツ
ただし、従業員参加型は結構コツが要ります。
1つ目は、だれかであれ、会社の方針であれ、悪者にしないことです。「悪者探し」を始めてしまうと建設的な議論になりません。そのため、まずは自分の部署の優れたところに目を向け、そこからさらにどうすればもっと良くなるかということを考えるのです。
2つ目は、課長は基本的に発言しないことです。会社は指揮命令で動いていますから課長の言葉は部下にとってはすごく重いのです。ですから課長は、議論が本来の方向と違うところに流れていきそうなときにくぎを刺すくらいに留めます。
3つ目は、職場改善責任者にみんなで協力する雰囲気を作り上げることです。話し合いがうまく進むとふさわしい人が責任者になり、自然とみんなで協力しようという雰囲気になります。逆に、責任者を押し付けあうような雰囲気になっているときは話し合いがうまくいっていない可能性があります。
従業員参加型の職場改善は結構難しいですが、チャレンジする価値はあります。いきなりやるのは大変なので、職場の産業医などに指導を受けながら始めるのがいいでしょう。初年度は一つの課で行い、その結果を全体に広げていくのがお勧めです。
ABOUT執筆者紹介
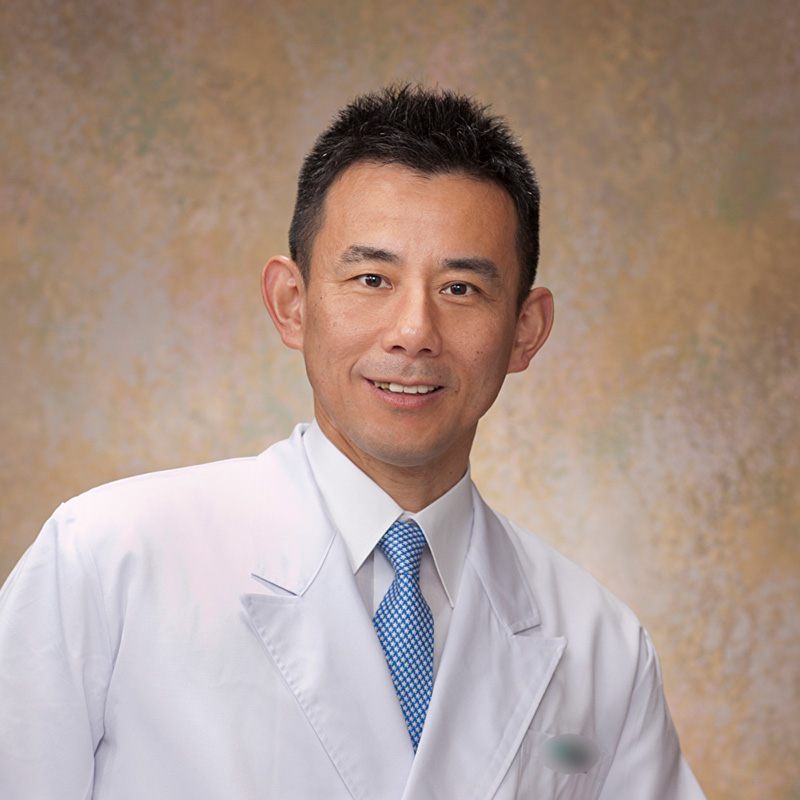 神田橋 宏治
神田橋 宏治
総合内科医/血液腫瘍内科医/日本医師会認定産業医/労働衛生コンサルタント/合同会社DB-SeeD代表
東京大学医学部医学科卒。東京大学血液内科助教等を経て合同会社DB-SeeD代表。
がんを専門としつつ内科医として訪問診療まで幅広く活動しており、また産業医として幅広く活躍中。
















