残業代が増えたら社会保険料も上がるのか?その時、必要な届出とは
社会保険ワンポイントコラム
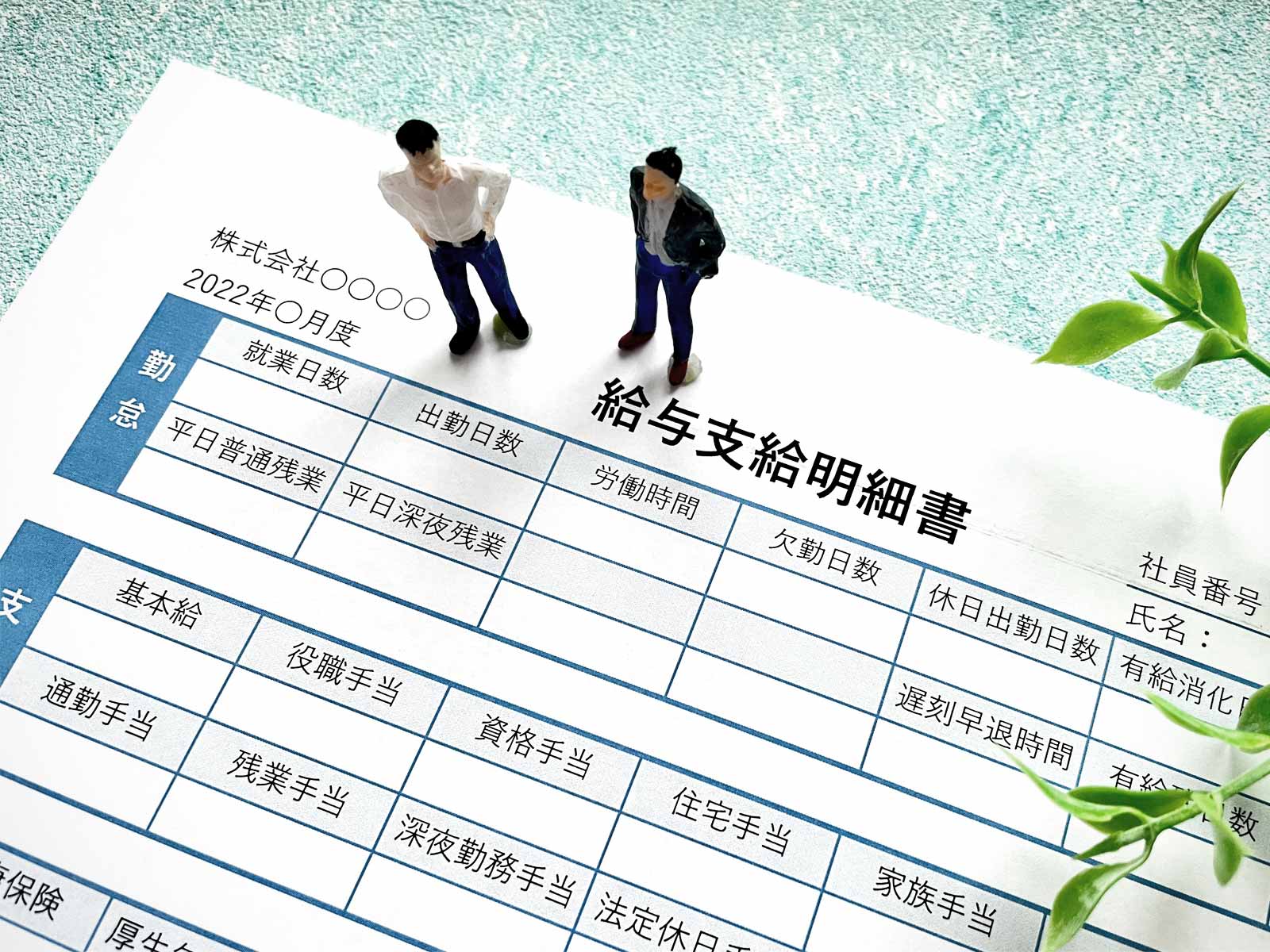
Contents
「今月は残業が多かったから」と期待して給与明細を見たら、思ったより手取りが増えていなかった…。そんな経験はありませんか?
この原因のひとつが「社会保険料の決まり方」にあります。給与が増減した場合には、「月額変更届(随時改定)」を提出し、社会保険料の見直し手続きが必要になることがあります。
では、残業代が増えたときもこの手続きは必要なのでしょうか?
本コラムでは、社会保険料の決定方法から、残業代増加時の実務判断まで、分かりやすく解説します。
社会保険料はどうやって決まる?
社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)は、「標準報酬月額」に基づいて決定されます。標準報酬月額は毎月の給与額そのものではなく、一定の幅に応じた「等級」に基づく金額です。
「標準報酬月額」の決定には、大きく分けて次の4つの方法があります。
1.資格取得時の決定
新たに採用された従業員については、契約時の給与額に基づいて標準報酬月額を決定します。通勤手当等諸手当や、予定される残業代や歩合給も含む必要がありますので注意が必要です。
2.定時決定(算定基礎届)
毎年4月~6月に支払われた報酬の平均額に基づいて7月に届出を行い、9月から翌年8月までの標準報酬月額が決定されます。この期間に残業代が多ければ、それを含めた等級で保険料が決まるため、9月以降の社会保険料が上がる場合もあります。
3.随時改定(月額変更届)
「固定的賃金」(基本給・通勤手当など毎月固定で支払われる賃金)に変更があり、次の要件すべてを満たす場合、4か月目から標準報酬月額を見直し、月額変更届の提出が必要になります。
・その変動以後3か月間の報酬平均額が2等級以上変動していること
・その3か月すべての支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は11日以上)あること
4.産前産後休業/育児休業等 終了時改定
産前産後休業や育児休業などからの復帰後、短時間勤務等で報酬が変わった場合に申出により標準報酬月額を見直すことができます。
なお、標準報酬月額の等級は1等級から50等級(厚生年金は32等級)に区分されており、決定された等級に応じて保険料が変動します。
残業代が増えたとき、随時改定となるかの判断ポイントは?
残業代が増えたことだけでは、月額変更届の提出は原則不要です。なぜなら、随時改定の要件には「固定的賃金の変動」が含まれているためです。残業代は「変動的賃金」に該当し、単独での変動では随時改定の対象外となります。
ただし、固定的賃金が増加した時期に、たまたま残業が多く報酬平均額が大きくなった場合には、随時改定の3要件を満たしてしまい、結果的に届出が必要になるケースがあります。
図は随時改定判定表ですが、残業代が増額しても、固定的賃金の変動がない場合は、社会保険料改定の対象とはなりませんし、固定的賃金の変動月から3か月の報酬平均額が従前に比べて2等級差が出なければ対象となりません。
なお、固定的賃金の変動について、複数の手当に変動があった場合は、全ての手当額を合算し、全体の額の増減で判定します。

見落としやすい変更例として、以下のようなケースがありますので、該当する場合はご注意ください。
・通勤手当の廃止・支給方法の変更
・賃金制度の見直し(手当体系の変更など)
月額変更が必要かどうかは、次の手順で確認すると良いでしょう。
① 給与計算時に固定的賃金の変更があったかを確認。
② 変更後の3か月間の報酬平均額を算出。
③ 現在の標準報酬月額と比べて2等級以上の差があるかを確認。
④ 支払基礎日数が各月17日(または11日)以上であるかを確認。
⑤ すべて満たす場合、4か月目に月額変更届を提出。
残業代が増えたとしても、それ単独では社会保険料が即座に変わるわけではありません。随時改定が必要になるのは、あくまでも「固定的賃金」に変動があった場合です。
制度の理解が不十分だと、届出を怠ることで後にさかのぼり訂正が必要になったり、逆に不要な届出によって保険料が過大となる恐れもあります。
実務担当者としては、こうした制度の仕組みを正しく理解し、必要に応じて社会保険労務士などの専門家に相談しながら、確実な対応を心がけましょう。
ABOUT執筆者紹介
 松田法子
松田法子
人間尊重の理念に基づき『労使双方が幸せを感じる企業造り』や障害年金請求の支援を行っています。
採用支援、助成金受給のアドバイス、社会保険・労働保険の事務手続き、給与計算のアウトソーシング、就業規則の作成、人事労務相談、障害年金の請求等、サービス内容は多岐にわたっておりますが、長年の経験に基づくきめ細かい対応でお客様との信頼関係を大切にして業務に取り組んでおります 。





