青色申告とは?白色申告との違いやメリット・65万円控除の条件などを分かりやすく解説
確定申告

Contents
確定申告の方法には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。中でも青色申告は、正確な帳簿をもとに申告を行うことで、65万円の控除をはじめとした多くの節税メリットが受けられる制度です。
一方で、「具体的に何をすればいいの?」「白色申告との違いがわからない」といった疑問を抱える個人事業主の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、青色申告の仕組みやメリット、手続きの流れ、白色申告との違いなどを初心者にもわかりやすく解説します。
青色申告とは
確定申告は、1年間の所得と税額を計算し、納税額の精算を行う手続きです。青色申告は、確定申告において一定のルールに基づいて帳簿を作成し、正確な申告を行うことで税制上の優遇が受けられる制度です。
青色申告の概要や白色申告との違いについて解説します。
青色申告の概要
青色申告は、日々の取引を一定のルールに従って帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しく所得や税額を計算・申告することで、税制上の優遇措置を受けられる制度です。
白色申告との違い
青色申告と白色申告は、記帳の内容や控除額、事務負担の程度などに大きな違いがあります。以下の比較表で、両者の特徴をわかりやすく整理しました。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 所定の申請手続きを行った個人事業主等 | 個人事業主等(手続き不要) |
| 特典 | 最大65万円の青色申告特別控除、赤字の繰越控除、青色事業専従者給与の経費算入 | 白色申告者に係る事業専従者控除 |
| 記帳の方法 | 複式簿記または簡易帳簿(特別控除額に影響) | 簡易な帳簿(単式簿記)で可 |
| 帳簿の保存義務 | 7年間(帳簿および決算関係書類、現金預金取引等関係書類)
5年間(その他の書類) |
7年間(収入金額や必要経費を記載した帳簿)
5年間(業務に関して作成した上記以外の帳簿、決算に関して作成した棚卸表その他の書類、業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類) |
| 提出書類の内容 | 申告書第一表・第二表のほか、青色申告決算書の提出が必要 | 申告書第一表・第二表のほか、収支内訳書を提出 |
| 電子申告との関係 | 一定の要件を満たした電子帳簿保存またはe-Taxによる提出で控除上限(65万円)が適用 | 控除制度なし |
青色申告と白色申告の違いについてこちら記事でより詳しく解説しています。
青色申告のメリット・特典
青色申告を行うと税金面で大きな節税効果が得られます。主な特典として、所得金額から最高65万円が控除される「青色申告特別控除」や生計を一にする配偶者・親族への給与を必要経費として計上できる「青色事業専従者給与」などの優遇措置があります。
これらの特典により、結果的に所得税(および住民税・事業税)を節税できるのが青色申告の大きなメリットです。
それぞれについて詳しくみていきましょう。
最大65万円の青色申告特別控除
青色申告には、所得金額から一定額を差し引くことができる「青色申告特別控除」という制度があります。この控除額は、申告者の記帳方法や提出方法によって異なり、最大で65万円の控除が認められる仕組みです。
まず、事業所得や不動産所得を得ている青色申告者が、正規の簿記(複式簿記)に基づいて帳簿をつけ、その帳簿から作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して、提出期限内に提出した場合には、最大55万円の特別控除を受けることができます。
さらに、仕訳帳及び総勘定元帳について優良な電子帳簿の要件を満たしたうえで、電子データによる備付け及び保存を実施し、確定申告期限までに届出書を提出した場合、またはe-Taxによる電子申告を期限内に行った場合は、最高65万円を控除できます。
青色事業専従者給与の必要経費算入
青色申告者が、家族に支払う給与を必要経費として計上できる制度が「青色事業専従者給与」です。
具体的には、15歳以上の家族が青色申告者の事業に従事している場合、その家族に実際に支払った給与を「専従者給与」として必要経費に算入することが認められます。ただし、この制度を利用するには、税務署へあらかじめ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は、適用を受けようとする年の3月15日までであり、1月16日以降に事業を開始した場合は、開業日あるいは専従者がいることとなった日から2か月以内の提出が求められます。
また、給与額にはいくつかの制限があります。まず、その金額が実際の労働時間や仕事内容に見合った「労務の対価」として適正であることが必要です。具体的には、勤務期間や従事した仕事の内容・程度、その事業に従事する他の従業員の給与水準、業種の特性や収益状況などと比較して、妥当な額であるかどうかが問われます。
届出書に記載された金額の範囲内であり、かつ実態に即した金額であれば、専従者への給与は全額が必要経費として認められます。
ただし、例外もあります。不動産賃貸業を営んでいる場合で、その規模が事業的と認められない場合には、この専従者給与の制度は利用できません。
純損失の繰越と繰戻し
青色申告者には、事業で赤字(損失)が出た場合に、その損失を他の年の所得と相殺できる「純損失の繰越控除」や「繰戻し還付」といった特例があります。これにより、赤字を翌年以降の黒字と相殺したり、過去の所得と相殺して税金の還付を受けたりすることが可能です。
まず、「純損失の繰越控除」とは、ある年に発生した赤字(純損失)を、翌年以後3年間にわたり、順番に各年の所得から差し引くことができる制度です。これにより、たとえば初年度に赤字が出ても、翌年以降の利益と相殺することで課税対象となる所得が減り、税負担を軽減することができます。事業の立ち上げ期や一時的な不振期において、大きな救済策となり得る制度です。
純損失の生じた年に青色申告を行い、その後も続けて確定申告をしている必要があります。
一方、すでに前年も青色申告をしていた方は、「純損失の繰戻し還付」を選択することもできます。これは、損失が生じた年の赤字を、前年の所得金額にさかのぼって控除し、すでに納めた所得税の一部または全額の還付を受けるという仕組みです。資金繰りが厳しい場合などには、還付によって即時の資金回収が可能になる点が大きなメリットです。ただし、繰戻しを適用するためには、損失が発生した年の確定申告書を提出期限内に提出していることが前提となります。
また、特例として、事業用資産の一部が特定非常災害によって損害を受け、その損失割合が10%以上である場合には、純損失の繰越期間が通常の3年から5年に延長されます。損失割合が10%未満の場合でも、特定被災事業用資産による損失に限り、5年間の繰越しが認められます。
貸倒引当金の必要経費計上
青色申告者は、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5パーセント以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れることが可能で、その場合はその金額が必要経費として認められます。ただし、金融業の場合は 3.3パーセントになります。
少額減価償却資産の特例制度
個人事業主が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その取得価額を即時に全額必要経費として計上できる「少額減価償却資産の特例」が利用できます。対象期間は2025年度末、すなわち2026年3月31日までで、1年間の上限は合計300万円です。
この制度は、原則として減価償却によって数年にわたり経費化される資産について、取得した年度に全額を損金算入できる点が大きなメリットです。税務上の節税効果やキャッシュフローの改善に貢献するため、設備投資を行う個人事業主にとって有効な手段といえるでしょう。
青色申告の節税効果
青色申告を活用することで、個人事業主はさまざまな節税メリットを享受できます。特に「青色事業専従者給与」の制度を利用すれば、家族への給与を必要経費として計上できるため、課税対象を大きく減らすことが可能です。
ここでは、配偶者が事業に専ら従事している場合を想定した具体的なシミュレーションを見てみましょう。
個人事業主の年間事業利益(収入-必要経費)が600万円で、配偶者が青色事業専従者に該当し、1年間で120万円の給与を支給しているケースを挙げます。その他、以下のような控除も適用されます。
- 社会保険料控除:40万円
- 生命保険料控除:12万円
- 地震保険料控除:5万円
- 基礎控除:48万円(2024年分の所得税まで)
白色申告の場合
白色申告の場合は配偶者への給与を必要経費に算入することはできませんが、代わりに最高 86 万円を必要経費として差し引くことができます。これを「事業専従者控除」と呼びます。事業専従者控除額86 万円を差し引いて計算した結果、所得税、復興特別所得税、事業税及び住民税の各税の合計額は、934,700 円となります。
青色申告の場合
e-Tax による申告(電子申告)又は優良な電子帳簿保存を行って 65 万円の青色申告特別控除の適用を受けた場合、配偶者に支払う青色事業専従者給与の金額 120 万円を事業の利益から差し引いて税額を計算した結果、各税の合計額は、636,900 円となります。
※詳しい計算式を確認したい方は、引用資料の5~6ページをご確認ください。なお、基礎控除は令和7年度より改定されていますが、このシミュレーションは令和6年度の数字にのっとって構成されています。
青色申告を受けるための条件・注意点
青色申告を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。詳しく見ていきましょう。
事前に青色申告承認申請書を提出する
青色申告の節税効果を受けるには、まず「所得税の青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出する必要があります。青色申告ができるのは、事業所得・不動産所得・山林所得がある人に限られます。
この申請書の提出期限は、青色申告を始めようとする年の3月15日までです。ただし、その年の1月16日以降に新たに事業を始めた場合は、開業の日から2か月以内が提出期限となります。
さらに、配偶者などの親族に対して「青色事業専従者給与」を支払い、必要経費として算入したい場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出も必須です。この届出をしていないと、たとえ給与を支払っていても経費として認められないため注意が必要です。
青色事業専従者給与の届出書も、原則として対象となる年の3月15日までに提出しなければなりません。なお、1月16日以降に開業した場合や、新たに専従者が加わった場合は、その日から2か月以内が提出期限です。
提出方法は、パソコンからe-Taxソフトを使って電子申請するか、書面を作成して税務署へ持参または郵送する方法が選べます。e-Taxを利用する際は、利用者識別番号の取得が必要です。
また、専従者給与に関して給与規程を別途定めている場合は、その写しの添付も必要になります。
所得の種類は事業所得・不動産所得・山林所得
青色申告を行うには、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のいずれかがあることが条件です。これらの所得は、種類ごとに性質や計算方法が異なります。
事業所得
事業所得とは農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業など、継続して営まれる事業活動から得られる所得を指します。自営業者や個人事業主の多くはこの区分に該当します。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による収入は、たとえ事業として行っていたとしても、原則として事業所得ではなく、不動産所得または山林所得として区分されます。
不動産所得
不動産所得は、以下のような不動産や権利の貸付けによって得られる所得です。
- 土地や建物の貸付け
- 借地権など不動産上の権利の設定・貸付け
- 船舶や航空機の貸付け
不動産の売却などによる譲渡益は不動産所得ではなく譲渡所得となる点に注意が必要です。
山林所得
山林所得は、山林を伐採して売却したり、立木のまま譲渡することで得られる所得です。
ただし、山林を取得してから5年以内に譲渡した場合は、山林所得ではなく事業所得または雑所得となります。また、山林を土地ごと譲渡した場合は、土地部分の所得は譲渡所得として扱われます。
青色申告決算書を作成して申告する
青色申告を行う際には、青色申告決算書を作成し、確定申告書とともに税務署へ提出する必要があります。これは、1年間の収入・経費・利益の状況を帳簿に基づいてまとめた書類であり、青色申告特別控除などの適用を受けるためにも欠かせないものです。
青色申告をするまでの流れ
青色申告を始めるには、あらかじめ申請が必要です。また、申告までには帳簿の記帳、決算処理、必要書類の作成といったステップを順に踏む必要があります。ここでは、青色申告を行うための基本的な流れを4段階で解説します。
①事前の申請手続きをする
青色申告を利用するには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。申請期限は以下のとおりです。
- その年の1月1日から事業を行っている場合:3月15日まで
- 1月16日以降に開業した場合:開業日から2か月以内
また、配偶者や親族に給与を支払い、必要経費として計上したい場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」も同様の期限で提出が必要です。これらの申請がなければ青色申告の特典を受けられないため、忘れずに済ませておきましょう。
②日々の取引を記帳する
青色申告では、日々の取引を帳簿に正確に記録する義務があります。65万円または55万円の特別控除を受けるには、複式簿記で記帳する必要があります。
なお、最高55万円または65万円の青色申告特別控除を受けるには、正規の簿記に基づく帳簿を備え、適切に記録・保存することが条件です。さらに、e-Taxによる電子申告などを行えば、控除額が65万円まで引き上げられます。
帳簿や書類の保存期間は原則7年間ですが、種類によって保存期間が異なります。
まず、青色申告をしている方が作成・保管すべき「帳簿」には、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などが含まれます。これらの帳簿は、事業活動を正確に記録し、税務署の調査にも対応するための基礎資料となるため、7年間の保存が義務付けられています。
次に「書類」に分類されるものには、さらに3種類があります。
1つ目は「決算関係書類」で、損益計算書、貸借対照表、棚卸表などが該当します。これらは事業の収支状況や資産・負債の状況を明らかにするための資料で、保存期間は7年です。
2つ目は「現金預金取引等関係書類」で、領収書、小切手控、預金通帳、借用証など、金銭のやり取りに関する証憑類が含まれます。これらも原則として7年間の保存が必要です。ただし、前々年の事業所得や不動産所得が300万円以下の事業者については、保存期間が5年間に短縮されます。
3つ目は「その他の書類」で、取引に関連して作成または受領した請求書、見積書、契約書、納品書、送り状などが該当します。これらの書類は、5年間の保存が求められています。
日々の記帳は会計ソフトを活用することで大幅に効率化できます。
ソリマチの青色申告専用の会計ソフト「みんなの青色申告」なら初めてでも使いやすい充実した機能が揃っています。
③決算処理をする
1年間の取引を締めくくり、正確な所得や経費を算出するためには、年末に「決算処理」を行う必要があります。青色申告の決算では、次のような作業を行います。
棚卸表の作成……商品や消耗品の年末在庫を実地で調査し、棚卸高を算出します。
収入・経費の整理……未収入金や未払経費、前受金や前払経費を整理し、帳簿を正しく調整します。
減価償却費の計算……取得した事業用資産について、法定の償却方法・耐用年数に基づき減価償却を行います。
帳簿の確認と累計……帳簿の記載ミスや漏れを修正し、1月~12月の収支を勘定科目ごとに合計します。
青色申告決算書の作成……損益計算書や貸借対照表を作成し、確定申告書に添付するための決算書類を完成させます。
④確定申告をする
青色申告を行う個人事業主は原則、毎年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書と青色申告決算書を提出する必要があります。
確定申告の際には、以下の書類をそろえて提出または保管しておく必要があります。
青色申告決算書
本人確認書類(マイナンバーカード、または通知カード+身分証)
各種控除証明書(社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除など)
紙で提出する方法と、e-Taxによるオンライン提出のどちらでも対応可能です。e-Taxを利用すれば、マイナンバーカードを使ってスマホやパソコンから申告ができます。
確定申告の必要書類については、こちらの記事もご覧ください。
はじめての青色申告なら「みんなの青色申告」がおすすめ
青色申告には、特別控除や赤字の繰越控除など、多くの節税メリットがあります。一方で、帳簿の記帳や決算書の作成といった手間も必要となるため、初めての方にとってはハードルが高く感じられるかもしれません。
これからはじめて確定申告をするという人には、ソリマチの青色申告専用の会計ソフト「みんなの青色申告」がおすすめです。
みんなの青色申告は、発売から30年を誇る青色申告ソフトで、最新の法改正にもばっちり対応しています。
直感的に操作できるデザインや常に進化し続ける機能で多くのユーザーに愛される製品です。30日間の無料体験も利用できるので、まずは操作性を試してみてください。
ABOUT監修者紹介
 税理士 鈴木まゆ子
税理士 鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
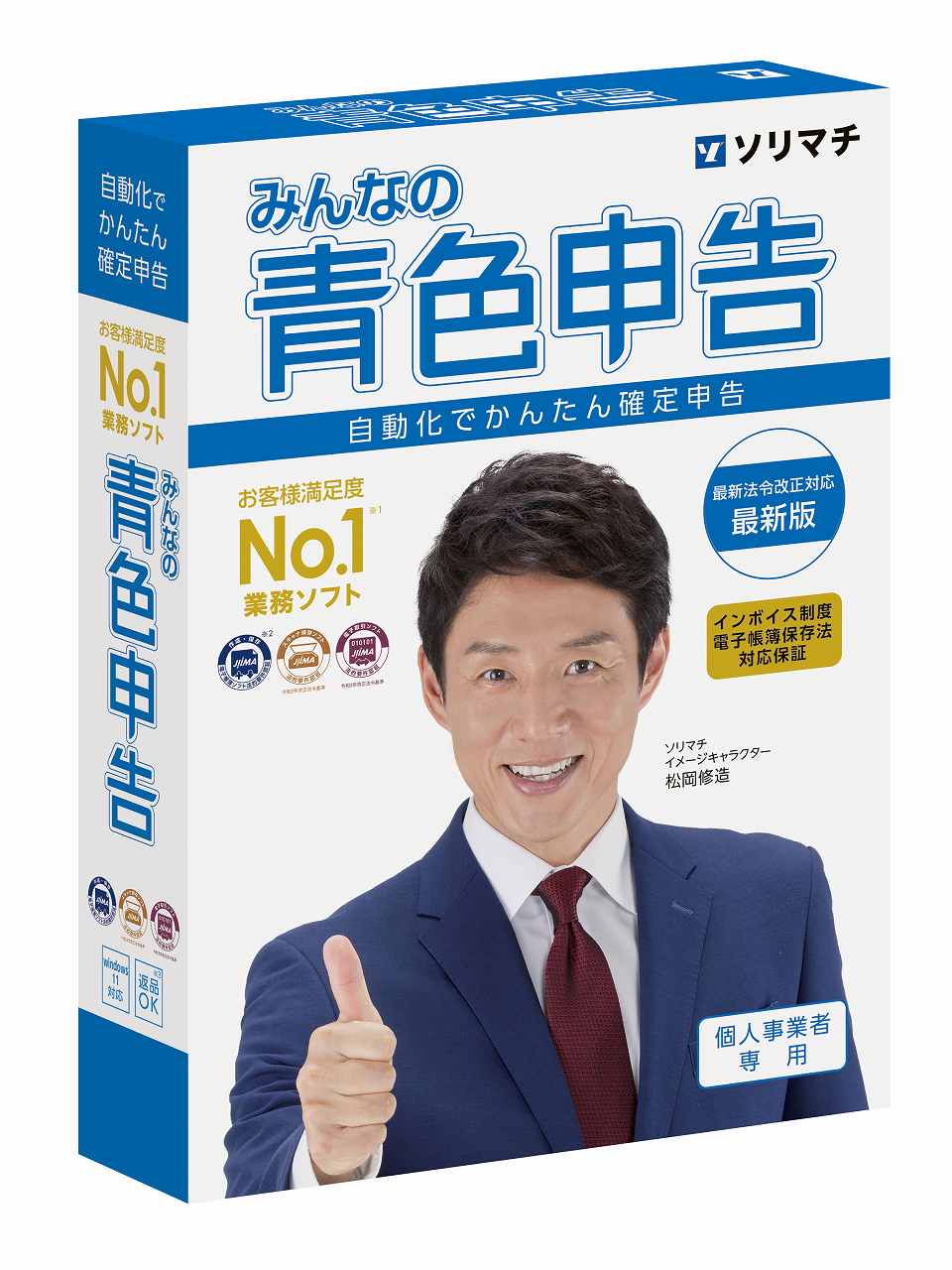 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。








