【2022年 年末調整】年末調整って何?経理初心者が知っておきたい基本をざっくり解説
税務ニュース
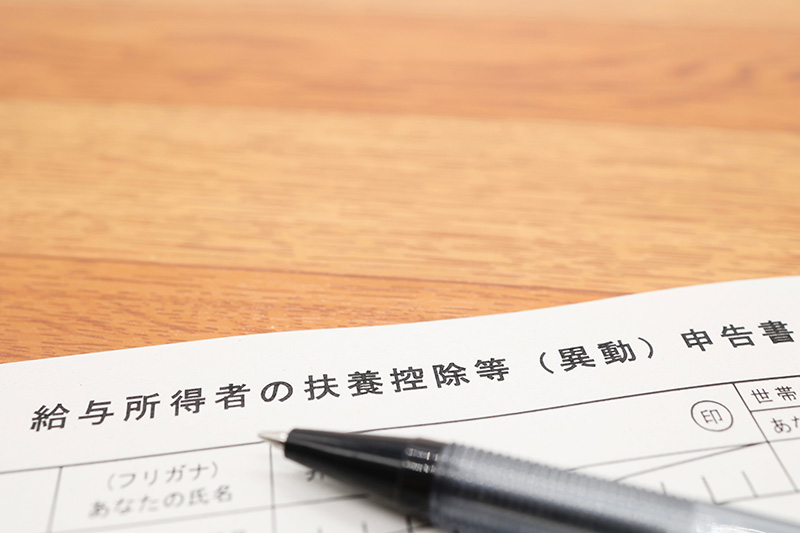
11月になると、多くの企業や会計事務所がソワソワし始めます。経理になったばかりの方だと不思議に思うかもしれません。ソワソワの理由は「年末調整」です。
年末調整とは何でしょうか。なぜ会社が行うのでしょうか。今回は、経理1年目の方に向け、年末調整の基本をざっくり解説します。
年末調整とは何か
年末調整とは、給料や賞与から預かった所得税の合計額と、1年間の給与全体にかかる本来の所得税額とを比べ、その差額を精算する手続きをいいます。
会社の役員や従業員が受け取る役員報酬や給与・賞与は、決まった金額そのままを受け取るのではありません。社会保険料や所得税、住民税が源泉徴収(天引き)されています。支給されるのは、源泉徴収後の残額です。
源泉徴収される所得税は、扶養している家族の数と課税される給与額の額の2つだけで決めた概算額です。1年ベースで見た所得税を考えると、少し多めに徴収されています。
一方、1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる所得税は「年の途中で扶養する家族の数に変更があった」「住宅ローンを支払っている」「本人や家族が障害者である」といった事情を考慮した上で計算した本来の納税額です。
この概算額と本来の納税額の差を調整するのが、年末調整となっています。
なお、給与所得者の中には、年明けに確定申告を行う人もいるはずです。しかし、そういう人でも会社に勤務をしているなら、原則として年末調整の対象者となります。
年末調整はなぜ行うのか

年末調整は、給与所得を支払うすべての事業主において義務とされています。なぜでしょうか。それは、納税事務の円滑化と徴税コストの軽減、そして納税者の負担軽減のためです。
2022年3月に国税庁が公表した「2020年分(令和2年分)申告所得税標本調査」 によると、申告納税者数は657万人となっています。そのうち、給与所得者数は258万人です。一方、同庁による「2020年分(令和2年分)民間給与実態統計調査」 を見ると、2020年12月末日時点での給与所得者の数は5928万人、1年を通して勤務した給与所得者の数は5245万人、そのうち年末調整を受けたのが4854万人となっています。申告納税者の全体数より、年末調整を受けた給与所得者の数の方が圧倒的に多いのです。
もし会社で源泉徴収も年末調整を行わず、すべて確定申告をするとなったら、税務行政は混乱するでしょう。税務署の窓口が混雑するだけでなく、e-taxも頻繁にサーバーダウンするかもしれません。申告内容の確認にも、膨大な手間と時間がかかります。給与所得者が合間を縫って申告作業を行うのも大変です。
少子高齢化が進んで現役世代が年々減ったとは言え、日本の全人口の半分近くは給与所得者で占められています。混乱を避け、税務行政を円滑に進めるには、源泉徴収と年末調整が欠かせないのです。
年末調整の流れ
年末調整は次の流れで行います。
- 各種書類の配布
最後の給与支払日の25日前~1か月前 - 各種書類の回収
最後の給与支払日の約15日前 - 回収した書類の確認
最後の給与支払日の約10日前 - 各種書類の作成
最後の給与支払日の約5日前 - 給与の支払い
最後の給与支払日当日★ - 納付書の作成と納付
翌年1月10日まで(納期の特例は1月20日まで)★ - 各種法定調書と給与支払報告書の作成・送付
翌年1月末日まで★
「★」がついているものは、法定の期限です。どの事業主も厳守しなくてはなりません。それ以外はおおよその目安です。事業主ごとに異なります。
なお、ここでいう「各種書類」とは、2022年現在、次を言います。
- 扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
- 保険料控除申告書
こういった書類は、年内最後の給与支払い日の約25日前~1か月前に配ります。つまり12月支給の給与の約1か月前には配るわけです。冒頭でお伝えした「11月頃になると経理内がソワソワする」のは、このためです。
それぞれのステップの詳細は、次回以降の記事で解説します。
年末調整を行う人、行わない人
年末調整を行う人
年末調整の対象となるのは「扶養控除等(異動)申告書」を提出した給与所得者のみです。この扶養控除等(異動)申告書を提出するのは、「ウチの会社が主たる勤務先となっている役員や正社員、バイト・パート」です。給与や賞与から天引きされる源泉所得税を、源泉徴収月額表の甲欄で計算している人に限られます。
ただし、扶養控除等(異動)申告書を提出していても、年末調整を行わない人もいます。次のような人です。
年末調整を行わない人
- 給与年収2000万円超の人
- 年の途中で退社し、年末に在籍していない人
- 災害減免法により、源泉所得税の納税の猶予あるいは還付を受けている人
- 会社での勤務をかけもちしていて他社で年末調整を受ける人(本来、源泉徴収月額表の乙欄となる人)
- 日雇労働者(本来、源泉徴収月額表の丙欄となる人)
また、最近は業務委託契約の方も増えていますが、彼らも原則、年末調整の対象から外れます。彼らが受け取っているのは給与所得ではなく業務の報酬だからです。
年末調整の対象となる所得
年末調整で扱うのは、基本的に会社が本人に支給した給与所得です。役員報酬や正社員の給料・賞与だけでなく、パート・アルバイトの日給や時間給も含みます。ただし、年の途中で入社してきた人については、前の職場で受け取っていた給与も含めて年末調整をします。
なお最近、正社員の副業が増えていますが、副業収入は年末調整の対象になりません。
今回は、年末調整のおおまかな内容についてお伝えしました。次回以降、手続の内容をお伝えしていきます。
ABOUT執筆者紹介
 税理士 鈴木まゆ子
税理士 鈴木まゆ子
税理士・税務ライター|中央大学法学部法律学科卒。ドン・キホーテ、会計事務所勤務を経て2012年税理士登録。ZUU online、マネーの達人、朝日新聞『相続会議』、KaikeiZine、納税通信などで税務・会計の記事を多数執筆。著書に『海外資産の税金のキホン』(税務経理協会、共著)。
[democracy id=”258″]
















