【2025年版】確定申告の必要書類/添付書類一覧
確定申告

Contents
確定申告は、1年間の所得と税額を計算し、税務署に申告する手続きです。2025年(令和7年)の申告期間は、2025年2月17日(月)~3月17日(月)です。
個人事業主やフリーランス、副業をしている会社員、各種控除を適用したい方など、状況に応じて必要書類が異なります。
本記事では、確定申告の必要書類をケース別に紹介します。
確定申告とは
確定申告は、1年間の所得と税額を計算し、税務署に申告する手続きです。
個人事業主、フリーランス、副業収入のある会社員、特定の控除を受けたい方などが対象となります。
確定申告の必要書類一覧
確定申告で必要な書類は、個人の状況によって異なります。共通して必要な書類、個人事業主・会社員・アルバイト・年金受給者に応じた書類を紹介します。
共通で必要な書類
共通で必要な書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 用途 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 確定申告書(第一表・第二表) | 所得税の申告に必要な書類で、収入・所得・控除・税額などを記入し、税務署に提出します。 | 国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)または税務署で入手可能 国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)上で、e-Taxを利用して電子申告が可能 |
| 本人確認書類 | マイナンバーカードまたは運転免許証+マイナンバー通知カード。本人であることとマイナンバーの確認のために必要です。 | マイナンバーカードは市区町村役場で申請 運転免許証は警察署や運転免許センターで取得可能 |
| 銀行口座情報 | 還付金を受け取る場合に必要です。口座情報を記入し、税務署に還付金の振込先を指定します。 | 銀行の通帳やインターネットバンキングの画面で口座情報を確認 |
| 収入証明書類 | 給与所得者:源泉徴収票(勤務先から発行) 個人事業主:売上や経費の帳簿(会計ソフトのデータや手書き帳簿など)。所得額を正しく申告するために必要な書類です。 年金受給者:源泉徴収票 |
給与所得者:年末に発行される 個人事業主:会計ソフトや手書きで売上・経費を記録し作成 |
| 控除証明書類(該当する場合のみ) | 医療費控除:医療費の領収書や「医療費控除の明細書」 生命保険控除:生命保険料控除証明書(保険会社が発行) 寄附金控除:寄附金の領収書や「ふるさと納税」の証明書。各種控除を適用するために必要な証明書類です。 |
医療費控除:病院や薬局で領収書を受け取り、明細書を作成 生命保険控除:保険会社から年末に送付される証明書を利用 寄附金控除:寄附先の自治体や団体から発行される証明書を保管 |
個人事業主・フリーランスに必要な書類
個人事業主・フリーランスの確定申告の必要書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 用途 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 青色申告決算書(青色申告の場合) | 青色申告者が所得や経費をまとめて申告するための書類 65万円控除などの特典を受けるために必要 |
国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)や税務署で入手 会計ソフトを利用すると自動作成可能 |
| 収支内訳書(白色申告の場合) | 白色申告者が年間の収入と経費を記載する書類 青色申告より控除額が少ないが、帳簿付けの負担が軽い |
国税庁の確定申告書等作成コーナー(オンライン)や税務署で入手 手書きや会計ソフトで作成可能 |
| 帳簿・仕訳帳・総勘定元帳 | 売上や経費の記録を管理するための帳簿類 税務調査時に必要になる |
会計ソフトやExcelを使用して作成 紙の帳簿でも可 |
| 事業用口座の通帳コピー | 事業の売上や経費の入出金記録を明確にするために必要 | 事業用銀行口座の通帳をコピー、またはオンラインバンキングで取引履歴をダウンロード |
| 請求書・領収書の控え | 取引先に対する売上の証明に必要 税務調査時の証拠にもなる |
請求書は会計ソフトやExcelで作成し、発行後に控えを保管 領収書は取引先に渡したものの控えを保管 |
| 必要経費の領収書 | 事業運営に必要な経費を計上するための証明書類 | 交通費、通信費、消耗品費などの領収書を受領し、整理・保管 |
| 固定資産台帳(減価償却する場合) | 減価償却資産(パソコン、車両、事務所設備など)の取得日・金額・償却額を記録する台帳 | 会計ソフトで自動作成、またはExcelで管理 資産購入時の領収書や契約書をもとに作成 |
会社員・給与所得者が確定申告をする場合の必要書類
会社員は通常、勤務先で行われる年末調整によって所得税が精算されます。しかし、以下のケースに該当する場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
- 医療費控除を受ける
- ふるさと納税をした
- 住宅ローン控除を受ける
- 副業収入がある
- 自然災害や盗難の被害を受けた
それぞれのケース別に必要書類について紹介します。
医療費控除を受ける場合の必要書類
医療費控除は、1年間に支払った医療費のうち、一定の金額を超える部分を所得控除として申告できる制度です。この「一定の金額」とは、10万円または総所得金額等の5%(総所得金額等が200万円未満の場合)です。
確定申告の際には、「医療費控除の明細書」の作成と添付が必要です。明細書には、受診した医療機関や支払額を記入します。従来は領収書の提出が必要でしたが、現在は提出不要となっています。ただし、税務署から求められた際には提示できるよう、5年間保管しておく必要があります。
また、健康保険組合から送付される「医療費のお知らせ」(医療費通知)がある場合は、それを添付することで明細書の作成を省略できます。ただし、「医療費のお知らせ」にはすべての医療費が記載されているとは限らないため、未記載の分は別途明細書を作成しなければなりません。
ふるさと納税をした場合の必要書類
ふるさと納税を行った場合、控除を受ける方法には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2種類があります。
ワンストップ特例制度は、寄附先が5自治体以内であり、確定申告が不要な給与所得者向けの制度です。しかし、6自治体以上に寄附をした場合や、他に確定申告をする理由がある場合は、確定申告が必要になります。
確定申告を行う場合、ふるさと納税の寄附金受領証明書を添付し、寄附額から2,000円を引いた金額を「寄附金控除」欄に記入します。
必要書類は各自治体から発行される「寄附金受領証明書」です。
住宅ローン控除を受ける場合の必要書類
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、自宅を購入した際に年末の住宅ローン残高の一定割合が所得税から控除される制度です。2年目以降は勤務先の年末調整で控除が受けられますが、初年度は確定申告が必要になります。
住宅の種類(新築、中古、認定住宅など)によって必要な書類は異なりますが、基本的な書類として、下記のような書類が必要です。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁HPからダウンロード可)
- 住宅ローンの年末残高等証明書(金融機関が発行)
- 建物・土地の登記事項証明書(法務局で取得)
- 建物・土地の売買契約書または請負契約書の写し
- 特定増改築等住宅の場合、増改築等工事証明書
中古住宅の場合は追加で複数の書類が必要です。
必要書類や諸条件について詳しくは、国税庁のホームページを参照してください。
副業収入がある場合の必要書類
副業などで複数の勤務先から給与を受け取っている場合、年末調整を受けていない給与の金額(収入金額)が20万円を超えると確定申告が必要になります。この場合、すべての勤務先から発行される源泉徴収票をもとに申告書を作成します。
源泉徴収票は確定申告書に添付する必要はありませんが、申告書作成時にすべての金額を正しく記入する必要があります。
自然災害や盗難の被害を受けた場合(雑損控除)
確定申告における所得控除の1つに「雑損控除」があります。これは、地震や火災、害虫被害などの自然災害や、盗難・横領などによる損害を受けた場合に適用できる所得控除です。ただし、詐欺や恐喝による損害は雑損控除の対象外となるため注意が必要です。
雑損控除では、以下の①または②のうち、大きい金額が控除額として適用されます。
① (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
② (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
ここでいう「損害金額」は、災害発生直前の資産価値(時価)をもとに計算される金額です。また、「災害関連支出」とは、住宅の取り壊し、土砂など障害物を除去するための費用などの支出を指します。
必要書類は下記のとおりです。
| 書類名 | 用途 | 取得方法 |
|---|---|---|
| 雑損失の金額の計算書 | 雑損控除の適用を受けるために必要な計算書 | 国税庁の公式サイトからダウンロード |
| 損害の状況を証明する書類 | 被害の発生を証明するために必要(罹災証明書、盗難届など) | 火災の場合は消防署、盗難の場合は警察署で発行 |
| 損害に関連する領収書 | 取壊し費用や災害関連支出を証明するための書類 | 工事会社から発行された領収書を保管 |
| 損害に対する保険金の支払い通知書 | 保険金の補填額を証明するために必要 | 加入している保険会社から発行 |
アルバイト・パートの確定申告
アルバイトやパートで働いている場合、基本的に勤務先が一つで年末調整を受けていれば、確定申告を行う必要はありません。しかし、アルバイト先が2か所以上ある場合や、医療費控除や寄附金控除などの控除を適用するためには、確定申告が必要です。
また、複数の勤務先がある場合、1つの勤務先でしか年末調整が行われないため、もう一方の収入が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年収103万円以下で源泉徴収がされていない場合は、所得税の確定申告は不要です。ただし、年末調整を受けていない場合は、住民税の計算に影響を及ぼす可能性があるため、住民税の申告が必要となる場合があります。
年度途中での退職の確定申告の必要書類
年度の途中で退職した場合、その後の状況に応じて確定申告が必要になるケースがあります。再就職した場合と、退職後に無職のまま年を越した場合で、必要な手続きが異なります。
再就職した場合には、新しい勤務先で前職分の源泉徴収票を提出することで、年末調整で税金の精算が可能です。しかし、前職の源泉徴収票を提出しなかった場合や、医療費控除などの適用を受けるために追加で申告が必要な場合は、自分で確定申告を行う必要があります。
一方、再就職せずにそのまま無職で過ごした場合、確定申告を行わないと、源泉徴収された税金を取り戻せない可能性があります。給与所得については年末調整が行われないため、源泉徴収票を基に確定申告を行い、所得税を精算します。
退職金を受け取った年度の確定申告の必要書類
退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金にかかる所得税は既に適切に計算されており、追加の確定申告は不要です。しかし、申告書を提出していない場合、退職金の20.42%が源泉徴収されるため、確定申告を行うことで過払い分の還付を受けることができます。
退職所得は分離課税となるため、確定申告書第三表を提出する必要がありますが、特別な添付資料は不要です。
年金受給者の確定申告の必要書類
年金を受給している方が確定申告を行う必要があるかどうかは、受け取る年金の種類や金額、その他の所得の有無によって異なります。公的年金等や生命保険契約に基づく年金は雑所得に分類され、確定申告が必要になる場合がありますが、公的年金等については一定の条件を満たせば確定申告不要制度が適用されます。
公的年金等のうち、遺族年金や障害年金については所得税が非課税となるため、確定申告の対象にはなりません。
公的年金等を受給している方で、年間の公的年金等収入が400万円以下ですべての公的年金等が源泉徴収されているかつ、その他の所得が20万円以下である場合にも、確定申告を行う必要はありません。ただし、医療費控除や寄附金控除などの適用を受けるために確定申告を行う場合は、公的年金等の所得も含めて申告する必要があります。
生命保険契約や生命共済契約に基づく私的年金を受給している場合には、支払いを受ける際に交付される証明書が必要です。
贈与税の確定申告の必要書類
贈与税の確定申告を行う場合、どのような贈与を受けたかを明確にし、必要に応じて明細書を作成して確定申告書に添付します。
申告書には贈与を受けた財産の内容や評価額、贈与者との関係などを記載し、適切な税額計算を行うための重要な書類となります。
申告書(計算書や付表)は、国税庁が提供する様式に従い作成し、申告の際に漏れがないように注意が必要です。
贈与税の確定申告に関連して、住宅取得等資金の贈与を受けた場合には、一定の条件を満たせば非課税となる「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の特例が適用される可能性があります。
特例を利用することで、父母や祖父母などから住宅取得のために受けた資金について、一定額まで贈与税がかからずに済みます。ただし、非課税の適用を受けるためには、贈与税の確定申告書の提出が必須となり、住宅取得の状況に応じた書類を添付する必要があります。
必要書類は、贈与の種類によって8種類に分類されます。例として、令和76年3月15日までに新築工事が完了しており入居も完了している場合は、下記のような書類が必要です。
- 受贈者の戸籍謄本
- 源泉徴収票
- 新築に係る工事請負契約書
- 登記事項証明書
- 耐震基準適合証明書
- 建築物の耐震改修の計画の認定申請書と耐震基準適合証明書
- 住宅性能証明書 など
詳しい内容については国税庁のホームページをご覧ください。
確定申告の必要書類の提出方法
確定申告の必要書類の提出方法は下記のとおりです。
- e-Tax(電子申告)
- 税務署窓口への持ち込み
- 時間外収集箱への投函
- 郵送
中でもe-Taxを利用した電子申告は、自宅で手続きができ、修正や添付書類の省略が可能なため、最も便利な方法といえます。
一方、紙で申告書を提出する場合には、必要書類の添付が必須です。申告書には、本人確認書類のコピーや控除証明書を「添付書類台紙」に貼り付けて提出する必要があります。
添付書類台紙は2枚あり、1枚目には本人確認書類、2枚目には社会保険料控除や生命保険料控除など、各種控除を受けるための証明書を貼り付けます。
確定申告の必要書類を確実に用意しましょう
確定申告は、所得や控除の状況に応じて適切に行うことで、税負担を最適化し、必要に応じて還付を受けることができます。
申告手続きをスムーズに進めるためには、事前の準備が重要です。本記事で紹介した各種書類の取得方法や必要な添付書類を参考にし、早めに準備を進めましょう。
ABOUT監修者紹介

税理士 北川知明
1998年横浜市立大学商学部経営学科卒業。2003年税理士登録。2014年に会計事務所を退職、北川税理士事務所開設。スタートアップから上場後のさらなる発展段階のステージまで、企業の成長とともに各ステージのニーズに応じたサービス提供に定評がある。
北川税理士事務所
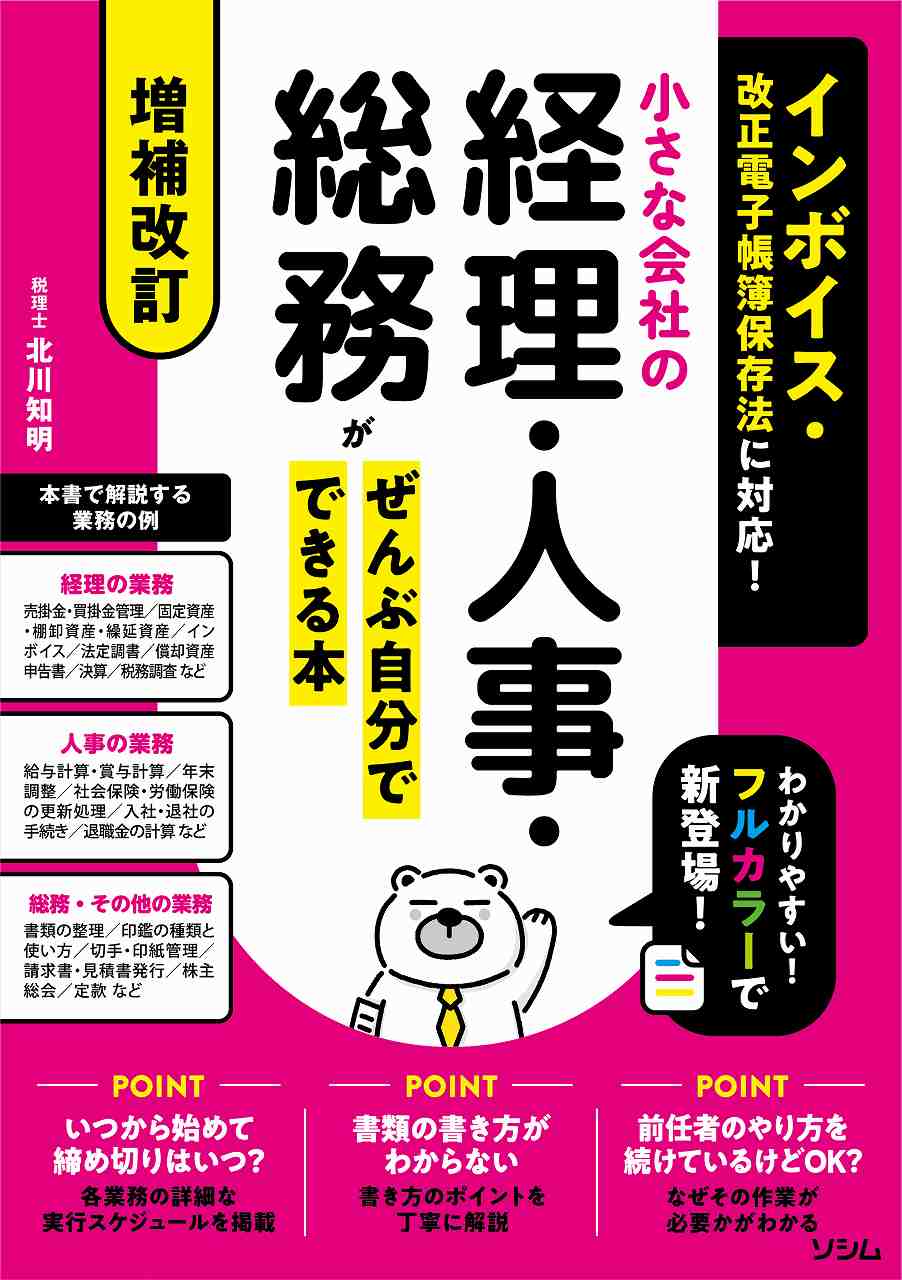
「【増補改訂】小さな会社の経理・人事・総務がぜんぶ自分でできる本」 |
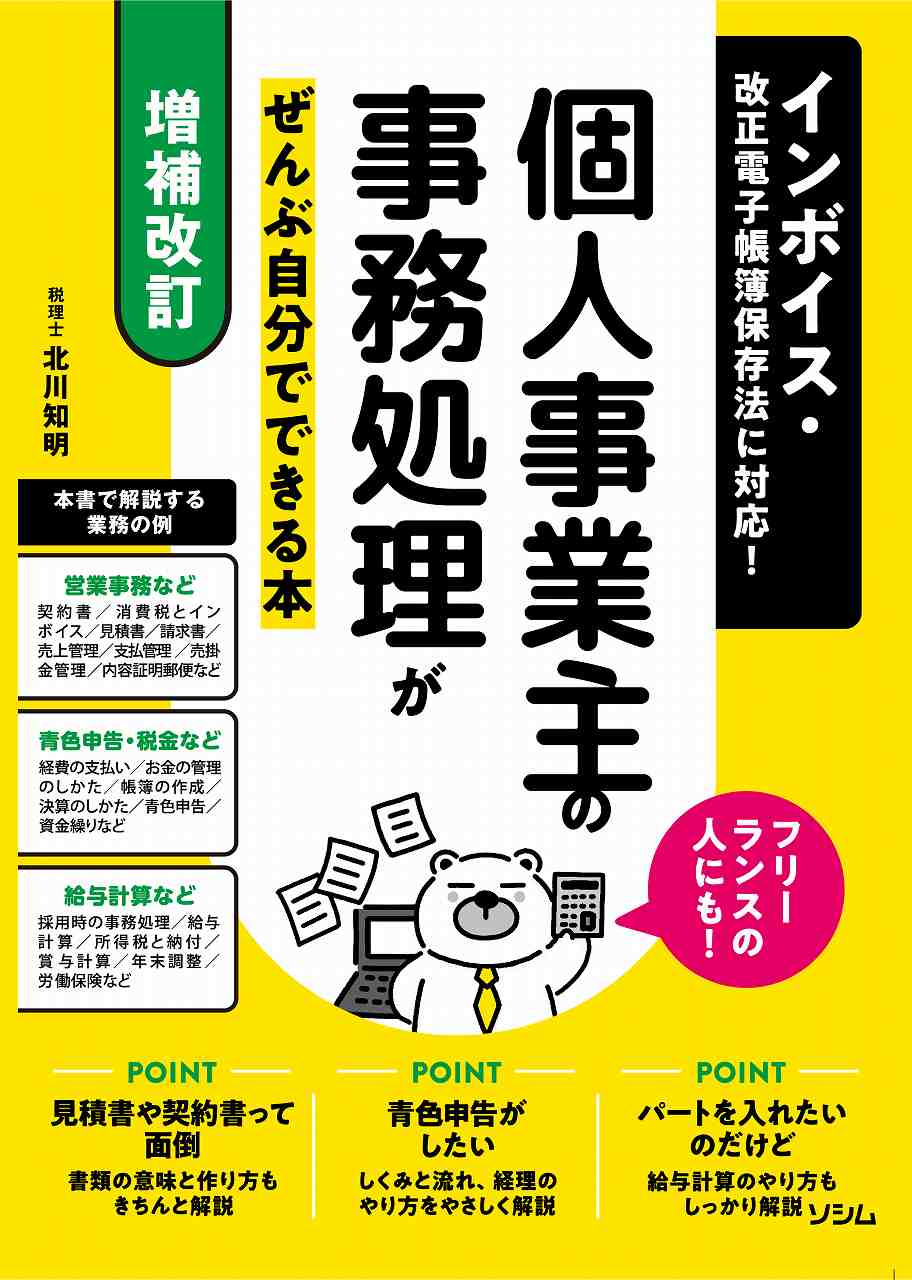
「【増補改訂】フリーランスの人にも!個人事業主の事務処理がぜんぶ自分でできる本」 |
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
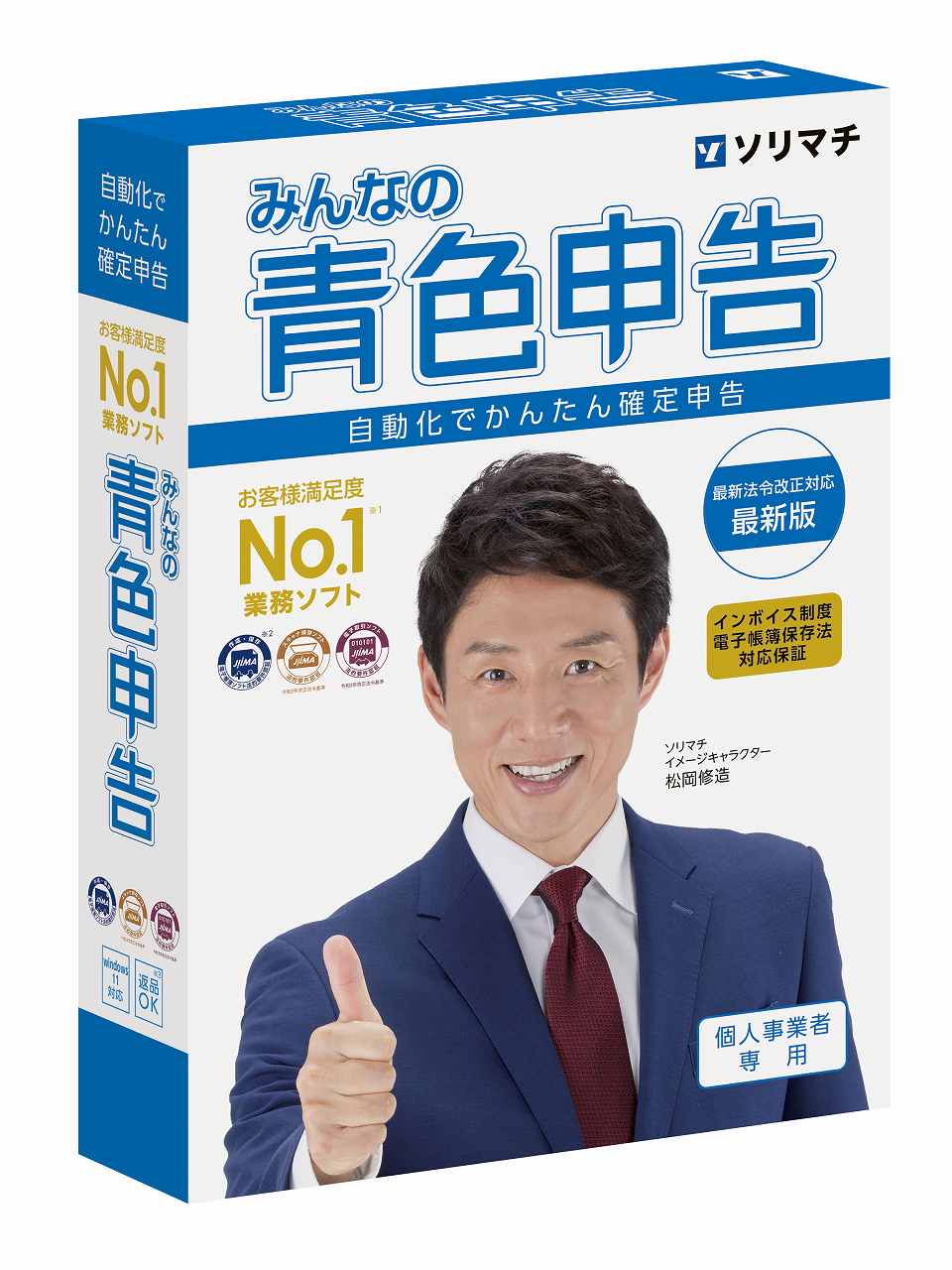 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。








