押さえておきたい重加算税実務の背景
税務ニュース
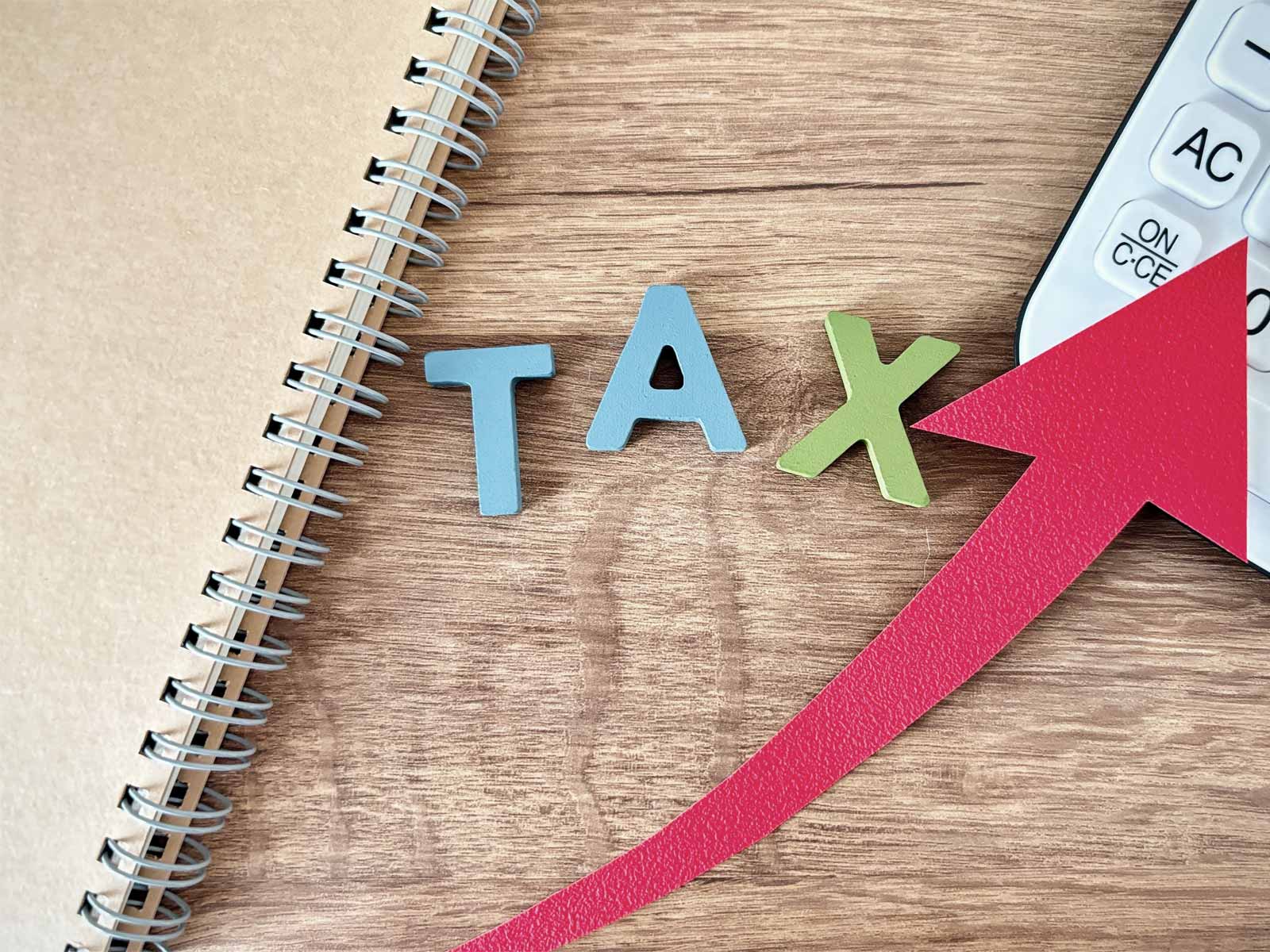
無申告の税務調査と重加算税
不正取引が税務調査で発見された場合、追徴される税額に、上乗せで重加算税というペナルティが課税されます。重加算税の対策としては、単にその法的な要件を押さえるだけではなく、税務署の実務の限界も押さえる必要があります。この実務の限界の典型例として、無申告に対する取扱いと、個人と法人という納税者の違いが挙げられます。
不正な無申告に対しても、法律上は重加算税の対象にされますが、実務で無申告者に重加算税が課されることは多くありません。数年前、とある著名人について、数年にわたる無申告と、実際に申告した年分における過大な経費の計上が問題になりました。この事例においては、申告があった年分については、不正な経費の計上があったとして重加算税が課税されましたが、無申告の年分については、重加算税は課税されておらず、無申告加算税という無申告のペナルティだけが課された模様です。
この理由は、無申告の場合には、重加算税の要件である不正の立証が難しいからです。申告という土台があれば、それを前提に不正な経費を計上しているという立証がしやすい反面、無申告はそれがないため、税金を納めないことを意図して不正に申告をしなかったのか否か、その立証が難しいのです。
重加算税は納税者にとっては大きな不利益になりますから、それを課税するためには、税務署は不正行為について立証する必要があり、これが難しいため無申告の方が重加算税は課税されにくい、という状況が実務では生じているのです。
法人と個人の違い
法人の調査と個人の調査においても、この不正の立証という点がネックになることがあります。
個人事業者には記帳の義務が設けられていますが、経理水準は高くありません。このため、個人事業主についても、不正取引の明確な立証が難しく、重加算税を課税することが法人よりも難しいのです。実際、私の現職時代、重加算税に対する税務署の決裁は法人の調査と個人の調査で大きく異なっていました。
税務署では、一定の重要性が高いとされる税務調査事案については、副署長クラスの幹部職員の決裁が必要になりますが、法人税の場合には所定の金額を超える不正取引があった場合にこの決裁が必要とされていました。一方で、所得税の場合には、このような金額基準はなく、重加算税を課税しようとする事案については、全件決裁が必要とされていました。個人については不正取引の立証が難しい分、より慎重な対応が必要という観点から、このような事務処理の違いがあったと思われます。
相続税の重加算税で重視される基準
このように、個人の税務調査では、その実態としては重加算税が課税されることは多くないと考えられます。しかし、同じ個人に対する税務調査でも、相続税についてはまた話が変わってきます。
相続税は事業主以外も申告納税しますので、金融機関に取引の記録が残る金融資産などを除けば証拠が残らず、個人事業主に対する税務調査以上に、不正取引の立証が難しいと思われます。しかし、相続税については、税務署は「税理士に対する隠ぺい行為」の有無で、重加算税を課税することが多くあります。
相続税の申告を税理士に依頼する場合、相続財産を正確に伝えなければ、申告もれが生じます。このため、納税者である相続人は当然に税理士にすべての相続財産を伝えるべきで、伝えていなければミスか、若しくは意図的に除外したかのいずれかとなります。
税務署は、後者に当たれば重加算税を課税できるとしており、税務調査では申告がもれた財産に関し、税理士と相続人との間でどのような話が合ったのか、その打ち合わせの経緯などを厳しく追及します。このため、税理士に対し、もれなく相続財産を共有するよう注意するとともに、仮に申告がもれた場合には、なぜ税理士に伝わっていないのか、その背景を慎重に調査官に説明する必要があります。
ABOUT執筆者紹介
 元国税調査官・税理士 松嶋洋
元国税調査官・税理士 松嶋洋
昭和54年福岡県生まれ。平成14年東京大学卒。国民生活金融公庫(現日本政策金融公庫)、東京国税局、日本税制研究所を経て、平成23年9月に独立。現在は税理士の税理士として、全国の税理士の税務調査や税務相談に従事しているほか、税務調査対策・税務訴訟等のコンサルティング並びにセミナー及び執筆も主な業務として活動。
著書に『最新リース税制』(共著)、『国際的二重課税排除の制度と実務』(共著)、『税務署の裏側』、『社長、その領収書は経費で落とせます!』『押せば意外に税務署なんて怖くない』などがあり、現在納税通信において「税務調査の真実と調査官の本音」という500回を超える税務調査に関するコラムを連載中。






