【税理士監修】確定申告と年末調整の違いは?両方やる人の条件や注意点も解説!
確定申告

確定申告と年末調整は、どちらも所得税に関する重要な手続きですが、その目的や対象者、申告方法には違いがあります。また、年末調整を受けた会社員であっても、すべての税金が自動的に適正に計算されるわけではなく、特定の控除を適用する場合や、給与所得以外の収入がある場合などには確定申告が必要です。
本記事では、確定申告と年末調整の違いに加え、両方が必要になるケースや注意点について詳しく解説します。
確定申告と年末調整の違い
確定申告と年末調整は、どちらも所得税に関する手続きですが、目的や手続きの方法、対象者に違いがあります。確定申告と年末調整の違いについて、詳しくみていきましょう。
確定申告と年末調整は目的や対象が異なる
年末調整と確定申告は、手続きの内容や目的が異なります。
年末調整は、企業に雇われている給与所得者を対象に、毎月の給与から源泉徴収された所得税額と、年間の実際の税額を調整するために行われます。
一方、確定申告は、個人事業主やフリーランスをはじめ、一部の会社員などが、自身の所得や控除を申告し、納めるべき税額を確定させるための手続きです。
年末調整と確定申告の違いは下記のとおりです。
| 項目 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 対象者 | 年収103万円(月8万8,000円)超の会社員、パート、アルバイト | 個人事業主、フリーランス、年収2,000万円超の会社員、副業所得が年20万円超の会社員など |
| 手続きの目的 | 会社が源泉徴収した所得税を年間の正しい税額に調整する | 1年間の所得と控除を基に、自ら納めるべき税額を計算・申告する |
| 申告・納税方法 | 勤務先が代行し、従業員本人が手続きをする必要は基本的にない | 本人が申告書を作成し、税務署へ提出(e-Tax・郵送・窓口提出) |
| 必要な書類 | 扶養控除等申告書、保険料控除申告書、住宅ローン控除申告書など | 確定申告書、源泉徴収票(該当者のみ)、収支内訳書、経費関連の領収書など |
| 税額の調整 | 年末に正しい税額を計算し、過不足を給与で調整する | 確定した税額に基づき納税する、または還付される |
確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得や控除を基に、自ら税額を計算し申告する手続きのことです。給与所得者であれば年末調整によって会社が税額を計算し納税まで行ってくれますが、一定額を超える副業所得がある会社員、年収2,000万円を超える給与所得者、株式や不動産の売却益がある人などは確定申告を行わなければなりません。
また、医療費控除や住宅ローン控除の適用を受ける場合も、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、対象となる年の翌年に行います。書類を税務署で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードし記入のうえで提出、または国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーなどで作成・提出します。
電子申告(e-Tax)を利用すれば、オンラインでの申告も可能です。申告期限は毎年決まっており、期限を過ぎると延滞税が発生することがあるため注意が必要です。
確定申告を行うことで税金の過不足が適正に調整され、還付が受けられる場合もあります。しかし、申告の必要がある人に対して税務署から通知が来るわけではないため、自分で申告義務を把握し、適切に手続きを行うことが重要です。
年末調整とは
年末調整とは、会社員が1年間に支払うべき所得税を最終的に確定し、正しい税額へと調整する手続きのことです。会社は、社員の給与を支給する際に所得税を毎月源泉徴収していますが、徴収額はあくまで概算であり、実際の納税額とは異なる場合があります。
そのため、1年間の所得が確定する年末に税額を再計算し、過不足を調整するのが年末調整の役割です。
所得税は、年間の総所得が確定しなければ正確な金額を算出することができません。また、扶養控除や生命保険料控除、住宅ローン控除などの個別の控除を適用することで、納めるべき税額が変わります。
そのため、年末調整では従業員一人ひとりの状況を反映した正確な税額を計算し、払いすぎていた場合は還付、不足していた場合は追加徴収が行われます。
年末調整を受けるためには、社員は会社から配布される申告書に記入し、必要に応じて控除証明書などの書類を提出する必要があります。会社はこれらの情報をもとに税額を再計算し、所得税の過不足を調整した上で、従業員の代わりに税務署へ納付を行います。
確定申告と年末調整の両方が必要なケース
年末調整は会社が従業員に代わって所得税を精算する仕組みですが、一定の条件に該当する場合は、年末調整とは別に確定申告を行う必要があります。確定申告と年末調整の両方が必要なケースについて詳しく見ていきましょう。
2か所以上から給与所得がある場合
給与を2か所以上から受け取っており、主たる給与所得以外の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要です。たとえば、正社員として働きながら他の企業でパートをしている場合や、会社役員を兼務しているケースなどが該当します。
年末調整は1つの勤務先でしか受けられないため、複数の勤務先から給与を受け取ると、主たる給与所得以外の所得が年末調整の対象外となります。そのため、自分で確定申告を行い、正しい税額を納めなければなりません。
副業の所得が20万円を超える場合
会社員であっても、給与所得以外に年間20万円を超える副業所得がある場合には、確定申告を行う義務があります。副業による所得は、収入から必要経費を差し引いた額を指し、単純な売上や受取金額ではない点に注意が必要です。
一般的な副業には、ブログ運営、ライティング報酬、ハンドメイド販売、YouTube広告収入などがあります。
また、投資による収益も確定申告の対象となる場合があります。ただし、株式や投資信託の売却益が「源泉徴収あり特定口座」で管理されている場合、確定申告は不要です。ただし、損益通算を適用し過去の損失と相殺したい場合には、確定申告を行うことで税額を軽減できます。
また、NISA口座で発生した利益は非課税のため、運用益にかかわらず確定申告の必要はありません。
給与や賞与の収入が2,000万円を超える場合
給与や賞与の合計収入が年間2,000万円を超える場合、年末調整の対象外となり、確定申告が必要です。給与が2,000万円を超えた場合でも勤務先は源泉徴収を行う義務がありますが、年末調整を実施しないため、そのままでは税額の納め過ぎや不足が生じます。
年の途中で転職や退職をした場合
年の途中で転職や退職をした場合、確定申告が必要になるケースがあります。前職を退職して年内に新しい勤務先へ転職した場合、新しい会社で年末調整を行えば確定申告は不要です。しかし、年度をまたいで転職すると、前年分の年末調整が行われていないため、確定申告を行う必要があります。
確定申告を行う際には、退職した会社から受け取る源泉徴収票が必要です。源泉徴収票には退職までの所得と源泉徴収された税額が記載されており、これを基に申告を行います。
災害や盗難にあった場合
災害や盗難などの被害を受けた場合、確定申告によって雑損控除を適用し、税負担を軽減することが可能です。雑損控除は、火災や地震、台風などの自然災害に加え、盗難や横領などの被害にも適用される制度で、損失額に応じて所得税や住民税を軽減できます。
雑損控除の計算は、被害に遭った財産の時価を基に行われますが、損害保険などで補填された場合は、その分を差し引いた額が控除対象です。適用を受けるためには、確定申告時に被害の状況を証明する書類を添付または提示する必要があります。
年末調整では雑損控除を適用できないため、該当する場合は必ず確定申告を行い、適正な控除を受けましょう。
会社員でも確定申告した方が良いケース
会社員の場合は年末調整が行われるため、多くのケースで確定申告が不要です。しかし、確定申告を行うことで控除が適用されると、税金の還付を受けられる可能性があります。会社員でも確定申告をした方が良いケースについて詳しくみていきましょう。
6以上の団体でふるさと納税をした場合
ふるさと納税による控除は、寄附金控除に該当します。通常、寄附金控除は年末調整の対象外のため、確定申告が必要です。
ただし、ふるさと納税による寄附金控除については、ワンストップ特例制度を利用すれば、年末調整で控除を受けることが可能です。
ワンストップ特例制度は、1年間に5つの自治体までのふるさと納税であれば適用されます。
6つ以上の自治体に寄附を行った場合は制度が適用されず、確定申告を行わなければ控除を受けることができません。
住宅ローン控除を初めて受ける場合
住宅ローン控除を初めて受ける際には、確定申告を行い、必要な書類を提出する必要があります。住宅ローン控除は、住宅を購入した際に、一定の条件を満たすことで住宅ローンの年末残高に応じた税額控除を受けられる制度です。
給与所得者であれば2年目以降は勤務先の年末調整で適用されるため、自ら申告する必要はありませんが、初年度のみ確定申告が必須です。また、個人事業主は年末調整がないため、2年目以降も確定申告を行う必要があります。
確定申告の際には、住宅の種類や購入の形態によって必要な書類が異なります。一般的に、登記事項証明書や売買契約書のコピー、住宅ローンの残高証明書などが求められますが、新築・中古、注文住宅・分譲住宅といった住宅の区分によって添付すべき書類が異なるため、事前に確認が必要です。
医療費控除や雑損控除などを受ける場合
医療費控除や雑損控除は年末調整では適用できないため、確定申告を行う必要があります。医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合に適用されます。
対象となるのは、本人だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費も含まれます。計算方法は下記のとおりです。
年間の医療費総額-保険金などで補填された分-10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)
医療費には、病院での診察や治療費、薬代、通院時の交通費などが含まれますが、美容目的の施術や健康診断の費用は対象外となるため、申請前に確認が必要です。
雑損控除は、災害や盗難、横領などによって財産に損害を受けた場合に適用される控除です。台風や地震などの自然災害で住宅や家財が損害を受けた場合、あるいは盗難や詐欺による金銭的な被害を受けた場合などに所得控除を受けることができます。控除額は、下記のいずれか多い方です。
- (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
- (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
確定申告と年末調整を両方する際の注意点
確定申告と年末調整を両方行う際は、次のことに注意しましょう。
確定申告には源泉徴収票が必要
2019年4月1日以降、確定申告書への源泉徴収票の添付は不要となりました。しかし、申告書の作成時には源泉徴収票に記載された給与所得や源泉徴収税額などの情報が必要です。
源泉徴収票は勤務先から年末調整後に交付されます。正確に申告書に反映させるため、源泉徴収票を手元に用意しておくことが重要です。
確定申告は必ず期限内に行う
確定申告の提出期間は、原則として所得を得た年の翌年2月16日から3月15日までです。2024年分の所得に対する申告期間は2025年2月17日(月)~ 2025年3月17日(月)です。
期限内に申告を行わないと、延滞税や加算税などのペナルティが課される可能性があります。年末調整後に追加で申告が必要な場合や、医療費控除などの適用を受ける場合は、早めに準備を進め、期限内に確定申告をしましょう。
確定申告と年末調整に関するよくある質問
確定申告と年末調整は、制度の違いや適用条件などについて多くの疑問が寄せられます。ここでは、確定申告と年末調整についてのよくある質問に回答します。
年末調整をしていれば確定申告は不要?
年末調整は、給与所得に関する所得税の過不足を調整する手続きです。給与以外の所得がある場合や、医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)など特定の控除を受ける場合、または年収が2,000万円を超える場合などは、年末調整だけでは適切な税額計算が行われません。
これらの場合、確定申告が必要です。確定申告を怠ると、所得税の未納となり、延滞税や加算税が課されるリスクがあるため、該当する方は必ず確定申告を行いましょう。
確定申告をすると副業が会社にバレる?
確定申告をすると、副業が会社に知られるわけではありません。しかし、確定申告後に自治体から会社へ送付される住民税の特別徴収通知書により、副業の所得が明らかになり、結果的に会社に知られる可能性があります。
これを防ぐ方法は、確定申告書の「住民税に関する事項」で「自分で納付(普通徴収)」を選択し、副業分の住民税を自分で納付することです。ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、事前に確認しましょう。
アルバイトは年末調整と確定申告が必要?
アルバイトでも、1つの勤務先で継続的に働き、年末までに在籍している場合は、その勤務先で年末調整を受けることができます。ただし、年間の給与収入が2,000万円を超える場合や、災害減免法の適用を受けて所得税の徴収猶予や還付を受けた場合は、年末調整の対象外となるため、自身で確定申告を行う必要があります。
また、年の途中で退職した場合や、複数のアルバイト先で給与を受け取っている場合は、年末調整が受けられないことがあります。たとえば、年内に退職し、新たな勤務先で年末調整を受けなかった場合、または、年間の給与収入が103万円以下であり、退職後に他の勤務先で給与の支払いを受ける予定がない場合には、年末調整の対象となることもあります。
一方で、複数のアルバイト先から給与を受け取っている場合、年末調整を受けられるのは1か所のみであり、その他の勤務先からの給与については、年間合計額が20万円を超える場合に確定申告が必要となります。
まとめ
確定申告と年末調整は、どちらも税金の適正な納付を目的とした手続きですが、適用される条件や計算方法が異なります。年末調整で税金の過不足を調整できる会社員でも、特定の条件に該当する場合は確定申告を行う必要があります。副業収入や医療費控除、ふるさと納税など、確定申告をすることで節税につながるケースもあるため、自分が申告の対象になるかどうかを事前に確認しておきましょう。
特に、申告期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生する可能性があるため、必要書類を早めに準備し、余裕を持って手続きを進めることが大切です。
税制を正しく理解し、適切な申告を行うことで、無駄な税負担を避け、適切に節税対策をしましょう。
ABOUT監修者紹介
 税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士・公認会計士 辻哲弥
税理士。公認会計士。
有限責任監査法人トーマツにて会計監査業務に従事。
23歳時、「日本一若い会計事務所」として”ACLEAN(アクリーン)会計事務所”を開業。スタートアップ、マイクロ法人を中心とした税務業務や補助金・融資等の資金調達支援、経理を対象とした業務改善コンサルティングを展開。
2023年に同事務所を”税理士法人グランサーズ”と統合。同法人の代表に就任。中小企業の税務顧問対応、内部統制構築支援、組織再編支援、事業承継・企業のクラウドサービス活用と経理効率化サービスも提供。また、自身のボディメイクの経験を活かした健康経営に関するコンサルティングも得意としている。YouTube「社長の資産防衛チャンネル」絶賛配信中!
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
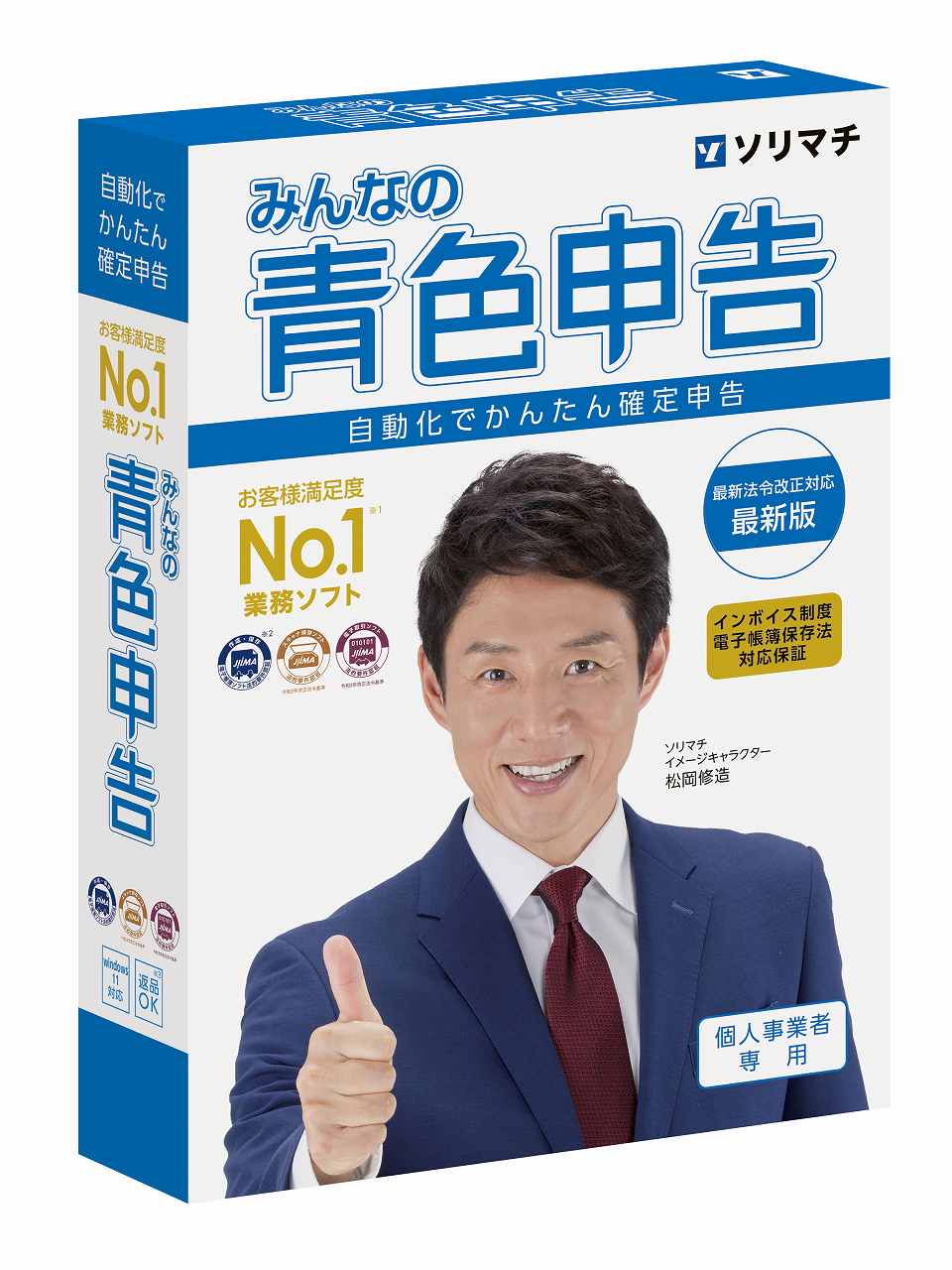 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
















