会社員で確定申告が必要な人とやり方を解説|ふるさと納税・医療費控除の条件も紹介
確定申告

Contents
会社員であれば、毎年の所得税は勤務先による年末調整で完結することがほとんどです。
そのため、「確定申告は自分には関係ない」と思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし実際には、副業や医療費、ふるさと納税、住宅ローン控除の初年度など、特定の条件に当てはまる場合は、会社員であっても確定申告が必要です。
また、確定申告を行うことで払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)ケースもあります。
本記事では、会社員が確定申告をする必要がある具体的な条件や、申告のやり方、還付を受けられる主なケースまで、わかりやすく解説します。
会社員でも確定申告が必要な人の条件
会社員として働いている場合、基本的には勤務先で行われる年末調整によって所得税の計算と納税が完了するため、自分で確定申告を行う必要はありません。
しかし、収入や働き方によっては、確定申告が義務となるケースもあります。以下に該当する方は、確定申告が必要です。
確定申告と年末調整の違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
給与収入が2,000万円を超える場合
1年間の給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外となり、自身で確定申告を行う必要があります。
給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超える場合(副業など)
1ヶ所から給与を受け取っており、給与所得と退職所得以外に、副業や不動産収入、株式の売却益などで20万円を超える所得がある場合は確定申告が必要です。
2か所以上から給与を受けている場合
複数の勤務先から給与を受け取っている場合で、給与の全額が源泉徴収の対象となるケースにおいて、下記に該当する場合は確定申告が必要です。
年末調整が行われなかった給与収入と、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える
上記以外のケース
以下のケースに該当する場合も、会社員であっても確定申告が必要です。
- 同族会社の役員などで、その会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
- 災害減免法により源泉徴収の猶予等を受けている人
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
- 退職所得について正規の方法で税額を計算したところ、源泉徴収された税額よりも多くなる人
確定申告の概要
「確定申告」と聞くと、難しそうで面倒なイメージを持つ方も多いかもしれません。
しかし、税金の仕組みを正しく理解し、自分に必要な手続きを把握しておくことで、還付を受けたり、無駄な納税を避けたりと、得をする場面も少なくありません。
確定申告の基本的な意味や、申告できる期間、申告を忘れた場合のペナルティなどについてわかりやすく解説します。
そもそも確定申告とは
確定申告とは、1年間の所得とそれにかかる税金を自ら計算し、税務署に申告・納税する手続きのことです。
毎年1月1日から12月31日までの間に得たすべての所得を集計し、そこから必要な控除を差し引いたうえで、所得税や復興特別所得税の納付額を確定させます。
また、年の途中で源泉徴収された税金や、予定納税として納めていた金額がある場合は、確定申告によってそれらの過不足を精算し、追加で納税したり還付を受けたりします。
確定申告の申告期間
令和7年分(2025年1月〜12月)の所得税に関する確定申告書の提出期間は、令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までです。この期間中に、税務署に相談や申告書の提出を行うことができます。
税務署は土日・祝日などの閉庁日には通常、相談や受付業務を行っていません。
ただし、以下の方法で申告書を提出することは可能です。
- e-Tax(電子申告)を利用して提出
- 郵送または信書便で送付
- 税務署の時間外収受箱に投函
また、還付申告(払いすぎた税金の還付を受ける手続き)を希望する方は、確定申告期間が始まる前でも申告書を提出できます。
確定申告を忘れるとどうなる?
確定申告を期限内に行わなかった場合、税金の本来の納付額に加えて「無申告加算税」が課されることがあります。加算税の割合は、申告のタイミングによって異なります。
税務署から調査の事前通知があった後に申告した場合……納付すべき税金に対して10%
さらに、期限後申告には延滞税が課されます。
詳しい内容は、国税庁ホームページをご確認ください。
確定申告はややこしい手続きが多く、めんどくさいと感じる人も多いのではないでしょうか。そんな人はこちらの記事もチェックしてみてください。
会社員でも確定申告をした方が良い主なケース
前述のとおり、会社員でも一定の条件に該当する場合は「確定申告が義務」となります。一方で、確定申告の義務はないものの、自ら申告することで税金の還付を受けられる「申告した方が得になるケース」も存在します。
ここでは、確定申告が必須ではないが、行うことで節税や還付につながるケースについて解説します。
医療費控除を受ける人
その年の1月1日から12月31日までの間に、本人または生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が一定額を超えている場合は、「医療費控除」を受けることで所得税の一部が還付される可能性があります。年末調整では反映されないため、自ら確定申告を行う必要があります。
医療費控除の対象になるのは、以下2つの条件を満たす医療費です。
- 納税者本人が、自己または生計を一にする配偶者や親族のために支払ったものであること
- その年(1月1日〜12月31日)中に実際に支払った医療費であること(未払い分は除く)
控除される金額は、以下の計算式で求められます(控除上限額は200万円)。
(実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされた金額) − 10万円
総所得金額が200万円未満の人は、10万円の代わりに「総所得金額の5%」を差し引きます。
ふるさと納税でワンストップ特例を利用しない人
ふるさと納税は、地方自治体への寄附金として「寄附金控除」の対象となり、ふるさと納税の金額について一定の限度額までは、自己負担額2,000円を除いた寄附額が、所得税および翌年度の住民税から控除されます。
会社員であっても、一定の条件を満たせば「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告をせずに控除を受けられます。
ただし、以下のような条件に1つでも当てはまる方は、ワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告が必要になります。
- 給与所得者ではない
- 2か所以上から給与の支払いを受けている
- 年間の給与収入が2,000万円を超えている
- 給与以外の所得(たとえば副業収入)がある
- ふるさと納税の寄附先が6自治体以上
- 住宅ローン控除(初年度)や医療費控除など、別の理由で確定申告をする必要がある
住宅ローン控除が1年目の人
マイホームの新築や購入、あるいは一定の増改築を行い、住宅ローンを利用した場合には、要件を満たすことで所得税の一部が減額される「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」を受けることができます。
この控除を受けるには、最初の年に限って自分で確定申告を行う必要があります。年末調整では対応できないため、会社員であっても申告手続きが必須です。
住宅ローン控除を受ける1年目は、確定申告書に必要な情報を記載したうえで、次のような書類を添付して税務署に提出します。
- 家屋の「登記事項証明書」などで床面積が50平方メートル以上(特例居住用家屋または特例認定住宅等の場合は、40平方メートル以上50平方メートル未満)であることを明らかにする書類
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
- 家屋の「工事請負契約書」または家屋の「売買契約書」の写し など
2年目以降は、税務署から送付される「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられます。
住宅ローン控除の確定申告については、こちらの記事でも詳しく解説しています。
災害や盗難などで損害を受けた人
災害、盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、一定の要件を満たせば「雑損控除」として所得控除を受けることができます。
なお、所得が1,000万円以下の方については、雑損控除とは別に「災害減免法」に基づく所得税の軽減・免除制度もあり、いずれか有利な方を選択できます。
雑損控除として控除できる金額は、次のいずれか大きい方となります。
- (損害金額 + 災害等関連支出 - 保険金など)- 総所得金額等の10%
- (災害等関連支出 - 保険金など)- 5万円
ここでいう「損害金額」とは、被害を受けた資産の直前の時価に基づいて計算された金額を指します。対象資産が減価償却資産である場合には、取得価額から償却費を控除した残額を基に計算します。
「災害等関連支出」とは、主に以下のような費用を指します。
- 災害により滅失した住宅・家財などを撤去するための費用
- 盗難や横領による損害を原状回復するための費用
また、「保険金など」とは、災害や損害に対して支払われた保険金、損害賠償金などを含みます。これらの金額は損害額や支出額から差し引かれるため、実質的な控除額に影響します。
雑損控除の対象となる資産には、以下の要件があります。
- 納税者本人、またはその生計を一にする配偶者や親族(所得48万円以下の人※令和元年分以前は38万円以下)が所有していること
- 棚卸資産、事業用固定資産、「生活に通常必要でない資産」に該当しないこと
「生活に通常必要でない資産」とは、たとえば別荘や高額な貴金属、ゴルフ会員権、美術品(30万円超)など、日常生活に通常必要でないものを指します。
控除の対象となる損害の原因は、次のいずれかに限られます。
- 地震・台風・洪水・落雷・大雪など自然現象による災害
- 火災・爆発など人為的な災害
- 害虫や鳥獣など生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
ただし、詐欺や恐喝による損害は、雑損控除の対象にはなりませんので注意が必要です。
会社員の確定申告のやり方
会社員であっても、医療費控除や住宅ローン控除の初年度、ふるさと納税でワンストップ特例が使えない場合などは、確定申告が必要になります。
ここでは、会社員が確定申告を行う手順を3つのステップに分けてわかりやすく解説します。
①会社員の確定申告に必要な書類をそろえる
確定申告の第一歩は、必要な書類の準備です。主に次のような書類をそろえておきましょう。
- 源泉徴収票(必要な情報を得るために利用。添付不要。マイナポータル経由で情報を取得して必要事項を自動で入力することも可能)
- マイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類
- 控除に関する証明書(該当する場合のみ)
②確定申告書を作成する
書類がそろったら、確定申告書の作成に進みます。現在は、以下の3つの方法で申告書の作成が可能です。
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で書類を作成する
- 税務署で手書き記入または相談しながら作成する
- 会計ソフトを使って確定申告書を作成する
この中でも特におすすめなのが、会計ソフトを使う方法です。収入や経費の入力項目が整理されており、ガイドに沿って情報を入力していくだけで済みます。控除の入力漏れや計算ミスも防ぎやすく、電子申告(e-Tax)との連携機能を備えたソフトであれば、そのままオンラインで申告まで完了させることも可能です。
③確定申告書を提出する
申告書が完成したら、期限内に提出します。提出方法は次のいずれかを選べます。
- e-Taxで申告する
- 郵送・信書便で送付する
- 税務署に直接持参する
申告期限は例年、2月16日から3月15日までとなっています(翌年のカレンダーにより変動)。期限を過ぎると無申告加算税などが課される可能性があるため、余裕を持って準備しましょう。
まとめ
会社員であっても、すべての人が年末調整だけで完結するとは限りません。
確定申告には、「申告書の作成」や「必要書類の準備」などの手間がかかりますが、税金の還付を受けられる可能性があります。
e-Taxや郵送など、提出方法も複数あるため、自分に合った方法でスムーズに申告を進めましょう。
ABOUT監修者紹介
 税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
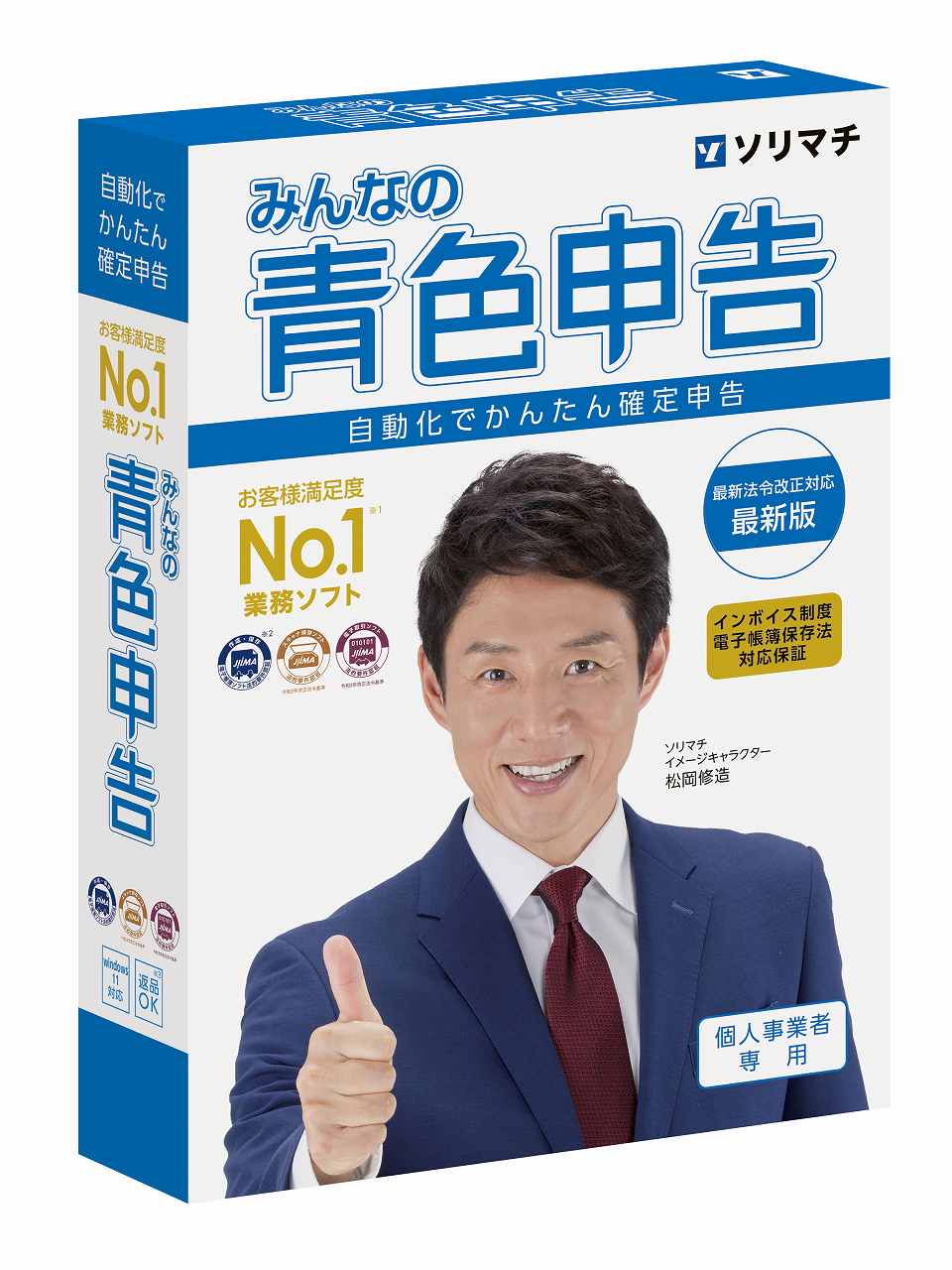 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。


















