【初心者必読】個人事業主や自営業の経理は何をする?年間の流れや効率化のポイントを解説
確定申告

Contents
個人事業主やフリーランスとして事業を始めると、避けて通れないのが「経理業務」です。日々の記帳や書類の整理、確定申告の準備など、やるべきことは多岐にわたり、特に開業したばかりの人にとっては「何から手をつければいいのか分からない」と感じる場面も少なくありません。
本記事では、個人事業主の経理の基本業務から、青色申告・白色申告の違い、申告や納税のスケジュール、経理を効率化するためのポイントまで詳しく解説します。
個人事業主の経理の基本業務
個人事業主が日常的に行う経理業務は、大きく分けて次の3つに分類されます。
(1)日々の記帳
売上や仕入れ、経費といった全ての取引を、日付や金額、取引内容とともに帳簿へ記録します。このとき、納品書や請求書、領収書などと照らし合わせ、記載内容に誤りがないかを確認し、必要があれば修正します。さらに、科目ごとに1~12月の累計を計算します。
(2)帳簿や領収書の保管
記帳したものの中には、当年の収入や経費に含めない前受金や前払費用がある一方で、未記帳でも当年分として計上しなければならない未収入金や未払経費もあります。これらを正しく判別し、帳簿に反映させます。
(3)決算書の作成と申告
決算書の作成と申告を行います。帳簿や棚卸表をもとに年間の収支を集計し、損益計算書や貸借対照表といった決算書を作成します。
記帳の重要性や帳簿・領収書などの保管義務、決算書の作成について詳しく見ていきましょう。
日々の取引を記帳することの重要性
所得税は、納税者が自ら所得金額と税額を正しく計算し、納める「申告納税制度」を採用しているため、売上や経費などの取引内容を記録しておくことは法律上も、事業運営上も欠かせません。
記帳が必要なのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある方で、売上や仕入、経費などに関する事項を、取引の日付、取引先の名称、金額などとともに帳簿へ記載します。
記帳方法は1つひとつの取引ごとに入力するほか、日ごとの合計金額をまとめて記載する簡易な方法も認められています。重要なのは、後から見ても取引の内容が明確にわかるように記録することです。
1年間(1月1日から12月31日まで)に発生した所得を正確に計算するためには、日々の収入と経費の動きを記帳し、併せて取引に伴い発行・受領した請求書や領収書、契約書などを保管しておく必要があります。
レシートやメモをため込まず、こまめに整理・記帳する習慣を身につければ、確定申告の時期に慌てることなく、正確な申告と納税が可能になります。
帳簿や領収書の保管義務
経理の基本として、帳簿や領収書などの証拠書類をきちんと保管することも大切です。
帳簿類や領収書にはそれぞれ保存する期間が明確に定められています。
青色申告の場合、仕訳帳や総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿や、損益計算書・貸借対照表といった決算関係書類、領収証・預金通帳・借用証書などの現金預金取引等関係書類は7年間、請求書・見積書・契約書などのその他の書類は5年間の保存が必要です。
ただし、現金預金取引等関係書類に関しては、前々年の事業所得および不動産所得の合計が300万円以下の場合に5年となります。
白色申告の場合も保存義務はあり、収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年間、それ以外の任意帳簿は5年間の保存が必要です。棚卸表や契約書、領収書などの書類も5年間保存します。2022年度以降分については、前々年の雑所得が300万円を超える場合に、請求書や領収書といった現金預金取引等関係書類を5年間保存する必要があります。
決算書の作成と申告
1年間の取引を正確に記帳し、帳簿などを整理したら、その集計結果をもとに決算書を作成します。
また、確定申告が必要な場合は、確定申告を行います。青色申告か白色申告かによって提出する書類が異なります。青色申告者は「青色申告決算書」を、白色申告者は「収支内訳書」と確定申告書を提出します。
青色申告と白色申告の違い
個人事業主やフリーランスが行う確定申告には、青色申告と白色申告の2つの方法があります。いずれも1年間の所得を計算して税務署に申告する点は同じですが、記帳方法や提出書類、受けられる税制上の特典に大きな違いがあります。
白色申告の特徴
白色申告は、比較的簡易な単式簿記でも申告できる制度です。記帳は取引ごとに行うことが原則ですが、日々の合計金額をまとめて記録するなど、簡易な方法も認められています。
白色申告は記帳や保存の要件が比較的緩やかで、取引の少ない事業者や開業間もない人でも始めやすい反面、青色申告のような特別控除や赤字の繰越しなどの節税メリットはありません。
青色申告の特徴
青色申告は、不動産所得、事業所得、山林所得のある人が、一定の水準で記帳を行い、その記録に基づいて正確な申告をすることで、税制上の有利な取扱いを受けられる制度です。
記帳は正規の簿記の原則、一般的には複式簿記によることが原則ですが、簡易な記帳も認められています。
青色申告の特徴は、節税効果の高い特典が多数用意されていることです。代表的なのが青色申告特別控除で、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告すれば、所得から最高55万円を控除できます。さらに、e-Taxによる申告または優良な電子帳簿の保存などの要件を満たした場合は、最大65万円の控除が可能です。
なお、簡易な記帳で、損益計算書を確定申告書に添付して提出する場合でも、10万円の控除を受けることが可能です。
このほか、家族を青色事業専従者として届け出れば、その給与を必要経費に算入できる制度や、売掛金などの貸倒れに備えて貸倒引当金を経費にできる制度、赤字が出た場合に翌年以降3年間繰り越して黒字と相殺できる純損失の繰越し、前年分にさかのぼって還付を受けられる純損失の繰戻しなど、多様な特典があります。青色申告を希望する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
提出期限は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日です。その年の1月16日以降に新たに事業を開始したり不動産の貸付けを始めた場合は、事業開始日(非居住者は国内で事業を開始した日)から2ヶ月以内に提出します。確定申告が必要になる条件や、その方法について、さらに詳しく知りたい方は以下をご覧ください。
個人事業主の経理の具体的な流れ
日々の経理業務
日々の取引を正確に記帳し、帳簿や書類などを整理・保存することが重要です。売上や仕入、経費の内容を取引日、取引先、金額とともに帳簿に記録し、領収書や請求書などを紛失しないよう整理して保管します。
こまめな記帳と整理の習慣をつけることで、申告作業をスムーズに進められます。
所得税の確定申告(原則毎年3月15日締切)
年間の経理業務の締めくくりとなるのが、所得税の「確定申告」です。個人事業主は、1月1日から12月31日までの所得を集計し、翌年の申告期間(原則2月16日から3月15日まで)に税務署へ申告します。
売上や経費、減価償却費、棚卸資産などの情報をまとめ、白色申告の場合は収支内訳書、青色申告の場合は損益計算書や貸借対照表、青色申告決算書を添付します。
確定申告で必要な書類については、こちらの記事も確認してみてください。
消費税の申告(課税事業者のみ、3月31日まで)
消費税および地方消費税の申告は、課税事業者に該当する個人事業主が行う必要があります。課税事業者となるのは、インボイス発行事業者として登録している場合、基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円を超える場合、または基準期間が1,000万円以下でも自ら「消費税課税事業者選択届出書」を提出している場合です。さらに、基準期間の課税売上高が1,000万円超でなくても、特定期間(前年1月1日~6月30日)の課税売上高および給与等支払額がいずれも1,000万円を超える場合も課税事業者となります。
詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
住民税・事業税の納税(翌年6月以降)
所得税や消費税の申告が終わった後も、翌年度に住民税や事業税などの納税が控えています。 これらは確定申告の内容をもとに各自治体や都道府県が税額を計算し、後日通知してくるものです。
個人住民税は、前年の所得をもとに算定される「所得割」と、所得に関係なく定額で課税される「均等割」で構成されています。個人事業主の場合の納付方法は「普通徴収」です。
普通徴収は、市区町村が納税義務者に直接納税通知書を送り、納税義務者が指定された期日に自ら納める方法です。
個人事業税は、事業所得や不動産所得など一定の業種を営む場合に都道府県が課税する税金で、原則として毎年8月31日と11月30日が納期限です。8月に都道府県税事務所から送られてくる納税通知書を用いて納税します。
経理を効率化するポイント
最後に、初心者の個人事業主が経理業務を無理なくスムーズに行うためのコツを紹介します。経理はコツコツ継続することが大事ですが、工夫次第で負担を大きく減らすことができます。
日々の経理を習慣づけて後回しにしない
取引内容や支出の詳細は、時間が経つほど記憶が薄れ、領収書の紛失や記帳漏れを招きやすくなります。
経理作業は「思い出しながらまとめる」よりも、その日のうちに記録する方が圧倒的に効率的です。毎日の終わりや週末など、あらかじめ時間を決めて帳簿を更新するルールをつくれば、記録の正確性が高まり、年度末に慌てることもありません。小さな積み重ねが、正確な経理とスムーズな申告への近道になります。
会計ソフトを活用して自動化
もう一つの強力な味方が、会計ソフトの活用です。
とく青色申告での確定申告を行う場合、複雑な手続きが必要なため、手書きや表計算ソフトのみでの管理は難しいケースが多いです。
ソリマチ株式会社の個人事業主専用の会計ソフト 「みんなの青色申告」 は、初心者でも使いやすい機能で日々の記帳業務や申告の手続きを効率化できます。
例えば、銀行のWeb明細を取り込んで自動で仕訳を作成したり、業種に合った勘定科目を自動設定してくれたりと、面倒な経理作業を大幅に省力化できます。
決算書の作成や確定申告ソフトへの連携も自動で行われるため、確定申告時の手続きも簡略化することができます。
会計ソフト導入時には初期設定で戸惑う人もいますが、「みんなの青色申告」では業種に応じた設定テンプレートや充実したサポートが用意されています。困ったときは専用の電話サポートで使用方法について説明させていただきます。
まとめ
個人事業主の経理は、日々の記帳・帳簿や書類の保管・決算書の作成と申告という基本業務を軸に、1年間を通して継続して行うことが大切です。開業届や青色申告承認申請といった開業時の手続きから、所得税・消費税・住民税・事業税の申告・納付までの流れを把握しておくことで、税務スケジュールに追われることなく計画的に対応できます。
経理は「面倒な作業」ではなく、事業の健康状態を確認し、将来の成長戦略を立てるための業務です。会計ソフトを活用し、正確かつ効率的な経理体制を整えましょう。
ABOUT監修者紹介
 税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
税理士、1級ファイナンシャルプランニング技能士
伴(ばん)洋太郎
BANZAI税理士事務所
大学卒業後、一般企業や税理士事務所での勤務を経て税理士試験に合格し、2018年にBANZAI税理士事務所を開業。個人事業主や中小法人を対象とした業務の経験が豊富で、業務のデジタル化支援やスモールビジネスの立ち上げや個人事業の法人化に数多く携わる。
著書「7日でマスター フリーランス・個人事業主の確定申告がおもしろいくらいわかる本」(ソーテック社)
ABOUT執筆者紹介
 加藤良大
加藤良大
フリーライター
ホームページ・ブログ
歴12年フリーライター。執筆実績は26,000本以上。
多くの大企業、中小企業のWeb集客、
【個人事業主向け青色申告ソフト】みんなの青色申告
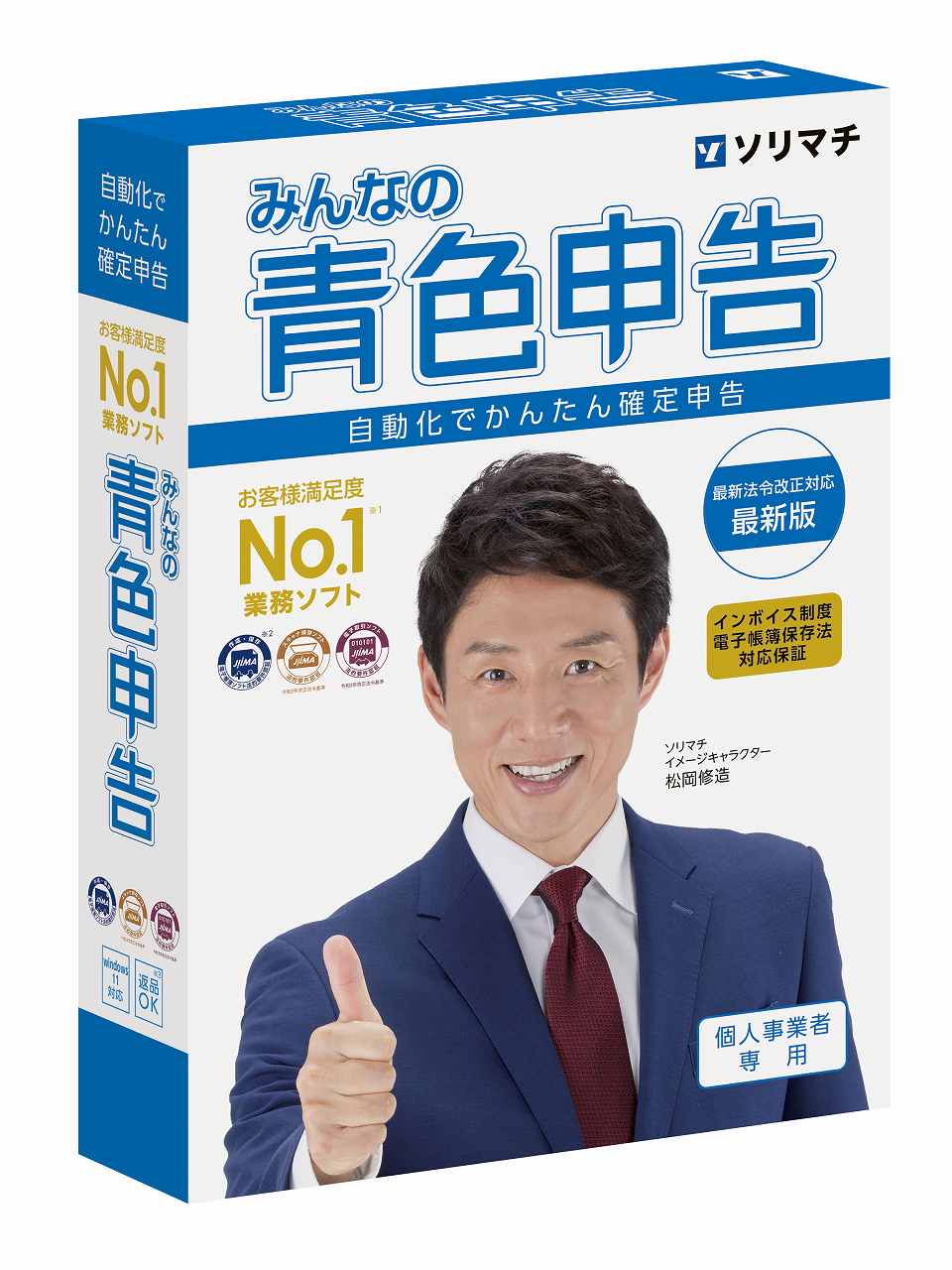 はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。
はじめての青色申告にオススメ!AI自動仕訳や充実したサポート体制など、簿記に詳しくない方でもスムーズにお使いいただけます。発売当初から改良を重ね、初心者からベテランまで、どなたでも使いやすい製品です。







